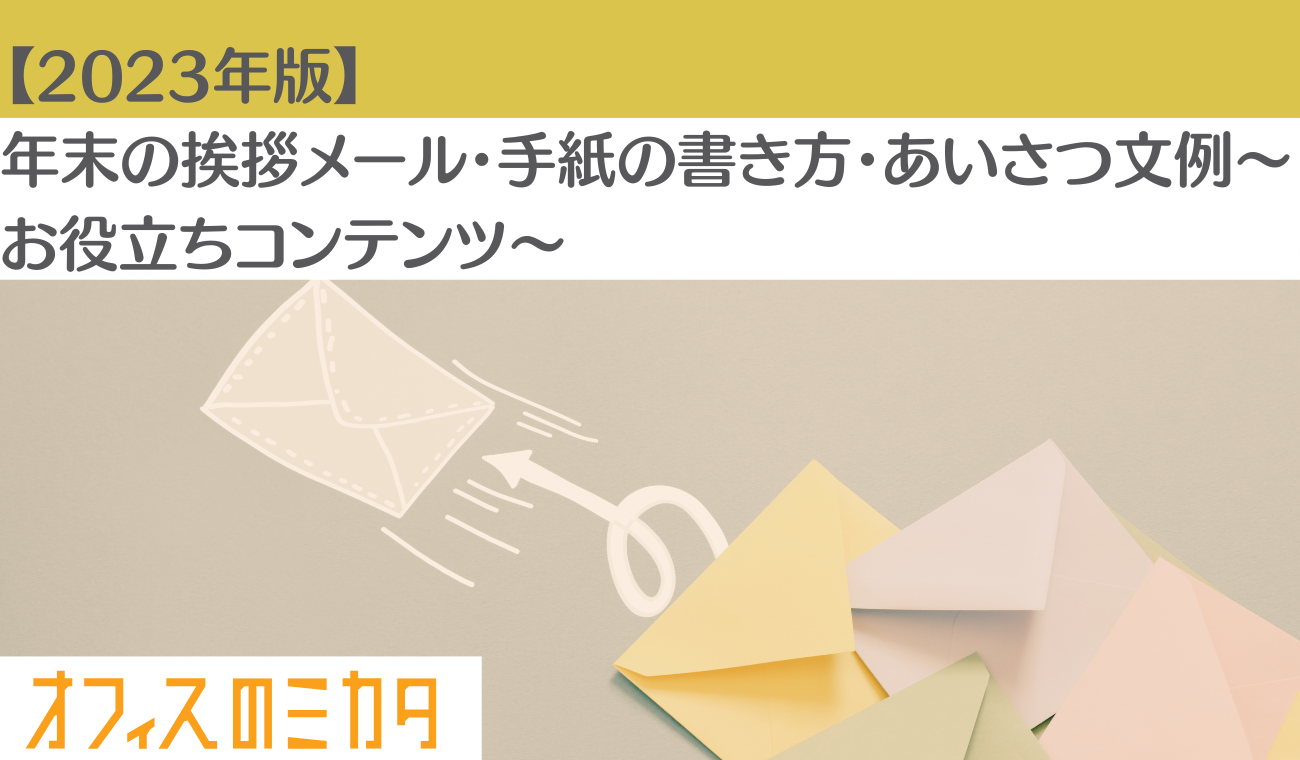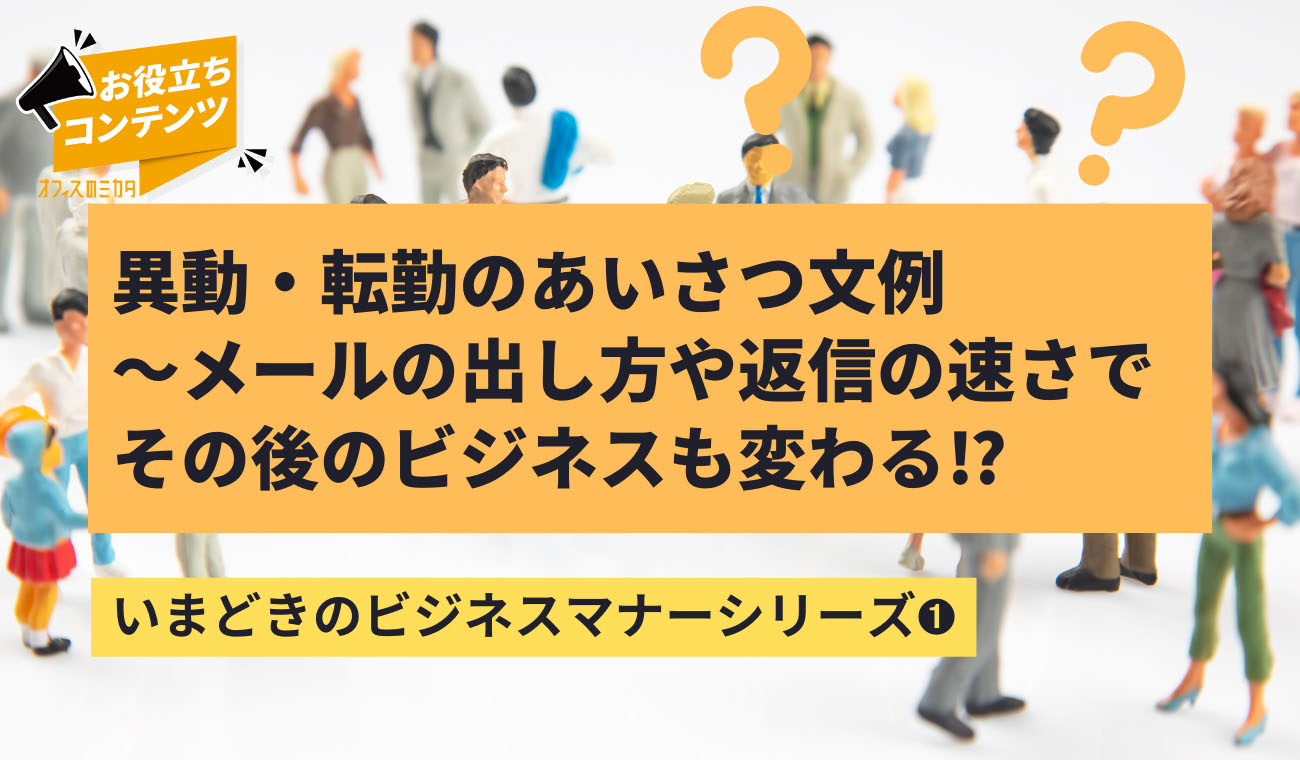「SaaS is Not Dead」ラクスが語るAI時代の共存戦略と製品再編
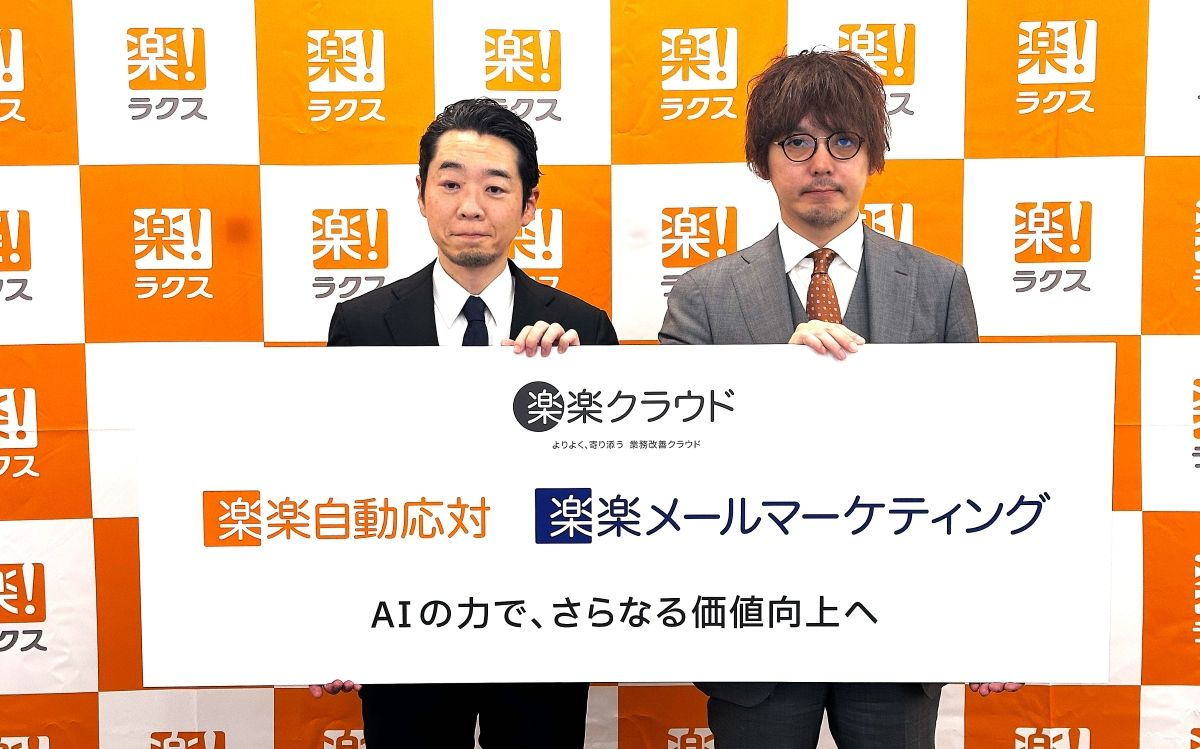
2025年10月21日、株式会社ラクスは記者勉強会を開催し、生成AIの進化がもたらすSaaSの役割の変化と、今後の事業戦略を発表した。近年広がる「SaaS is Dead(SaaSの時代は終わった)」という論調に対し、同社は明確に「SaaS is Not Dead」と宣言。SaaSとAIエージェントがそれぞれの強みを生かし、共存しながら進化していく未来像を提示した。
SaaSの価値は「業務基盤」にある
業界で広がる「SaaS is Dead」論とは、「SaaSは、そのうちAIエージェントに置き換えられてしまうのではないか」という議論だ。 生成AIの進化により、業務の自動化・効率化が進む中で、従来型SaaSの存在意義が問われている。

最初に登壇した取締役の本松慎一郎氏は、SaaSとAIエージェントの再定義を提案。まずはSaaSの本質を「特定業務向けのオールインワン業務ソフト」と定義し、正確性、法令対応、監査性、安定運用といった業務基盤としての価値は、AIエージェントが代替しきれない領域だと語った。
一方で、AIエージェントは自律的に業務を遂行するシステムであるが、得意領域と苦手領域がある。たとえば、領収書の読み取りや社内規定との照合など、定型的な処理に強みを持つ。手順が決まっていることや例外が少ないことは得意だが、臨機応変さに乏しく、例外が多い作業は苦手だ。交際費の妥当性や正当性を判断するには、その支出がビジネス上持つ価値の理解が前提となり、AIエージェントには判断が難しい。
つまり、実際業務を考えたとき、AIエージェントに任せづらい業務が存在するということを、念頭に置いておかなければならない。
「SaaS × AI」の共存モデルへ
本松氏は「AIエージェントとSaaS、そして人間が役割分担することで、業務はさらに効率がアップし、かつ確実なものとなる」と提言。

記者勉強会では、経費精算業務を例に、AIエージェントが申請書を起票し、SaaSがデータを管理、人間が承認を担うという役割分担が紹介された。
将来は「埋め込み型」から「ハブ型」へ~SaaS is Not Dead~
ラクスでは現在、SaaSのインターフェースを維持しながら裏側でAIエージェントが支援する「組み込み型」のアプローチを採用している。人間がSaaSを使用し、AIが補助的な役割を担う仕組みだ。
しかし未来では「ハブ型」のアプローチが主流になってくるだろうと、本松氏は語る。ハブ型では、AIエージェントがフロントエンド(操作画面)となり、SaaSは前面に出てこない。人間から指示を受けたAIエージェントが、必要な機能やデータを持つ複数のSaaSと連携し、業務を遂行する。

現在、ハブ型モデルは未成熟だが、今後はどんどん登場してくるとみられる。本松氏は「AIエージェントとSaaS、人間の共存により業務は効率化され、人間は企画・戦略立案や業務プロセス改善、顧客との対話といった高付加価値業務に注力できるようになる」と話す。
ラクス社内でもAI活用の成果が現れており、業務効率化を原資とした給与のベースアップ(※)も実施された。
(※)2025年10月時点 全社平均3.0%、2026年4月時点 年収ベース平均6.5% 定期昇給も含む
製品群の再編とブランド統合
勉強会では次に楽楽クラウド事業本部⻑の吉岡耕児氏が登壇し、AI時代を見据えて製品の役割と価値を明確化するため、サービス名を変更したことを発表した。「MailDealer」は「楽楽自動応対」に、「配配メール」は「楽楽メールマーケティング」となる。

改名の具体的な理由は「メール」という言葉の限定的な響きにあるという。「MailDealer」はメール対応状況の可視化や共有管理を行うシステムだったが、AIを組み込むことにより問い合わせ回答文の自動生成など、大幅に機能が拡張している。「配配メール」は顧客へのメール一斉配信を行うシステムだったが、メールマーケティング機能の提供や継続的に成果を出すための運用構築サポートも行うようになってきた。
なお、これらは「楽楽クラウド」ブランドに統合され、バックオフィスからフロントオフィスまでを包括的に支援する体制へと進化していくという。
ラクスは「SaaSは死なない」との立場を明確にし、AIエージェントとの共存を前提とした業務設計と製品再編を進めている。今後、こうした取り組みがどのように実装され、企業活動に浸透していくかが注目されるだろう。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする