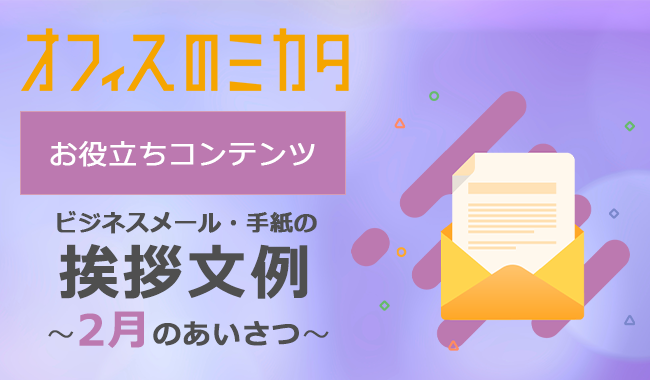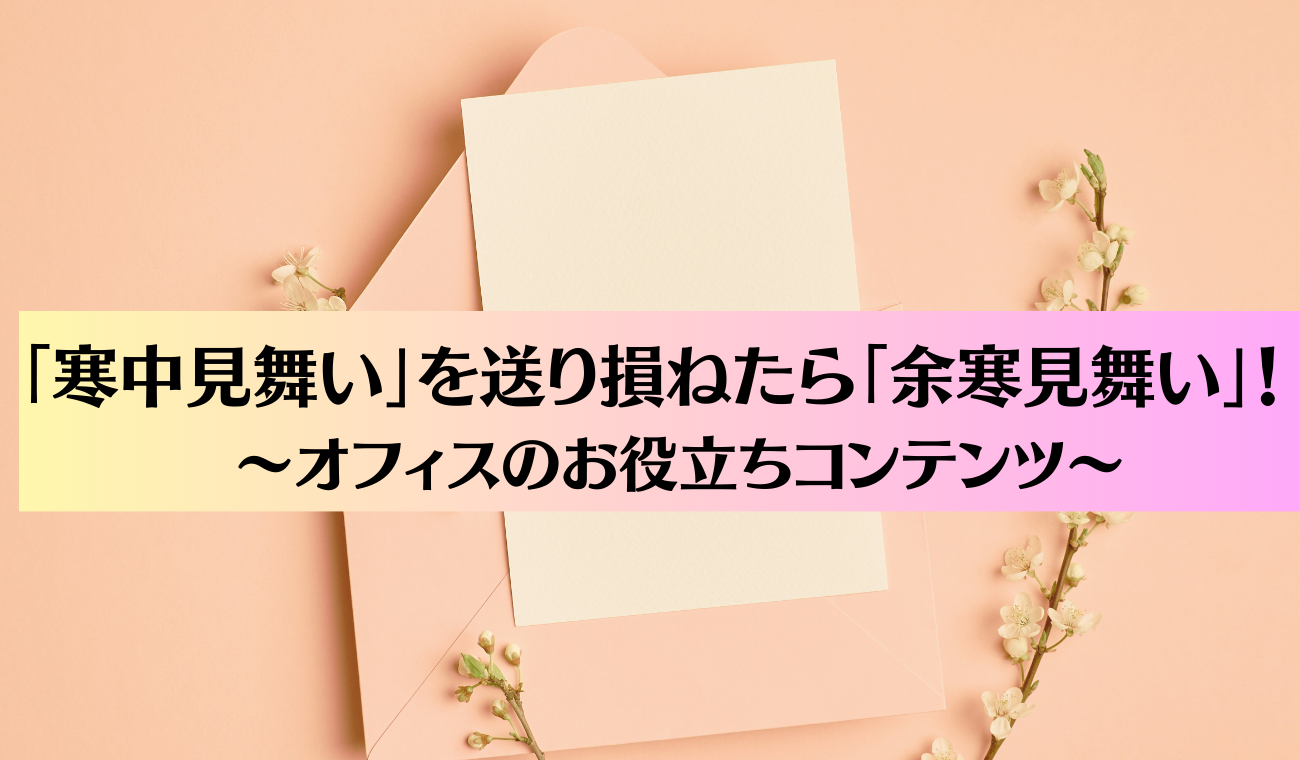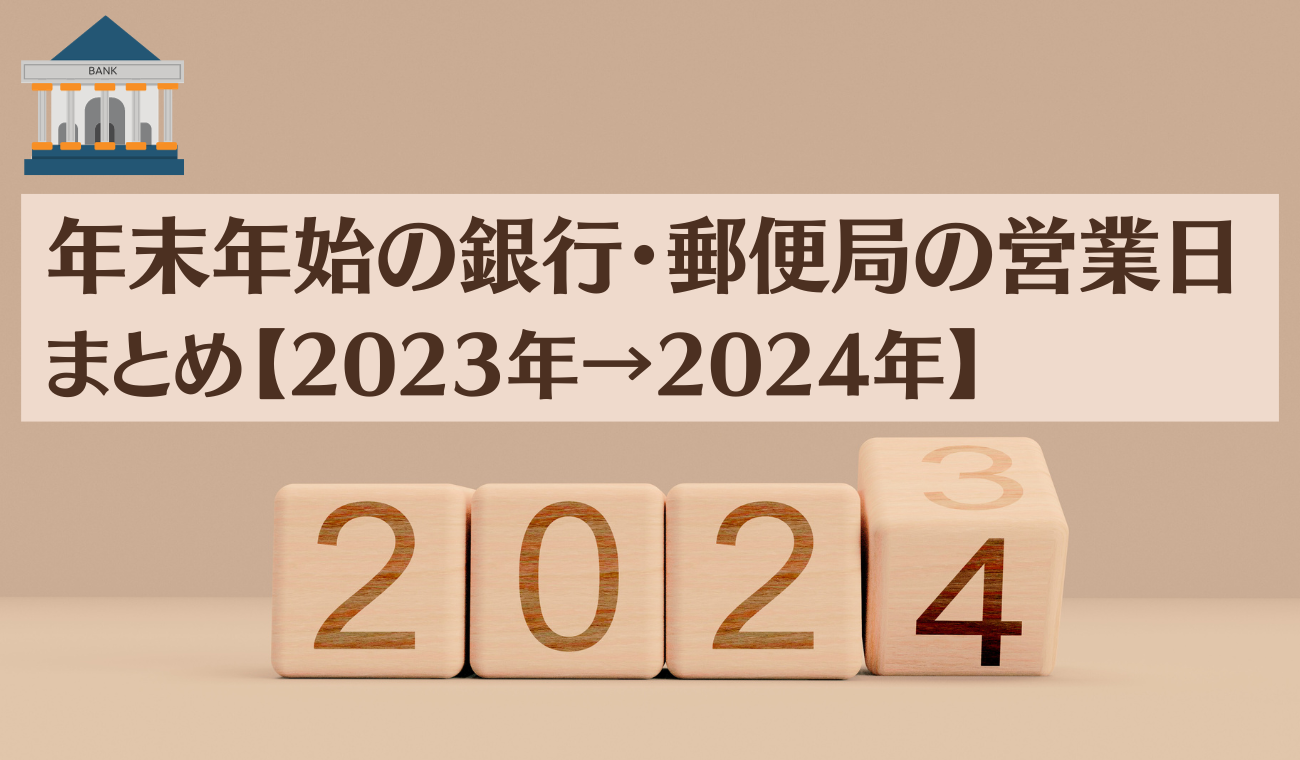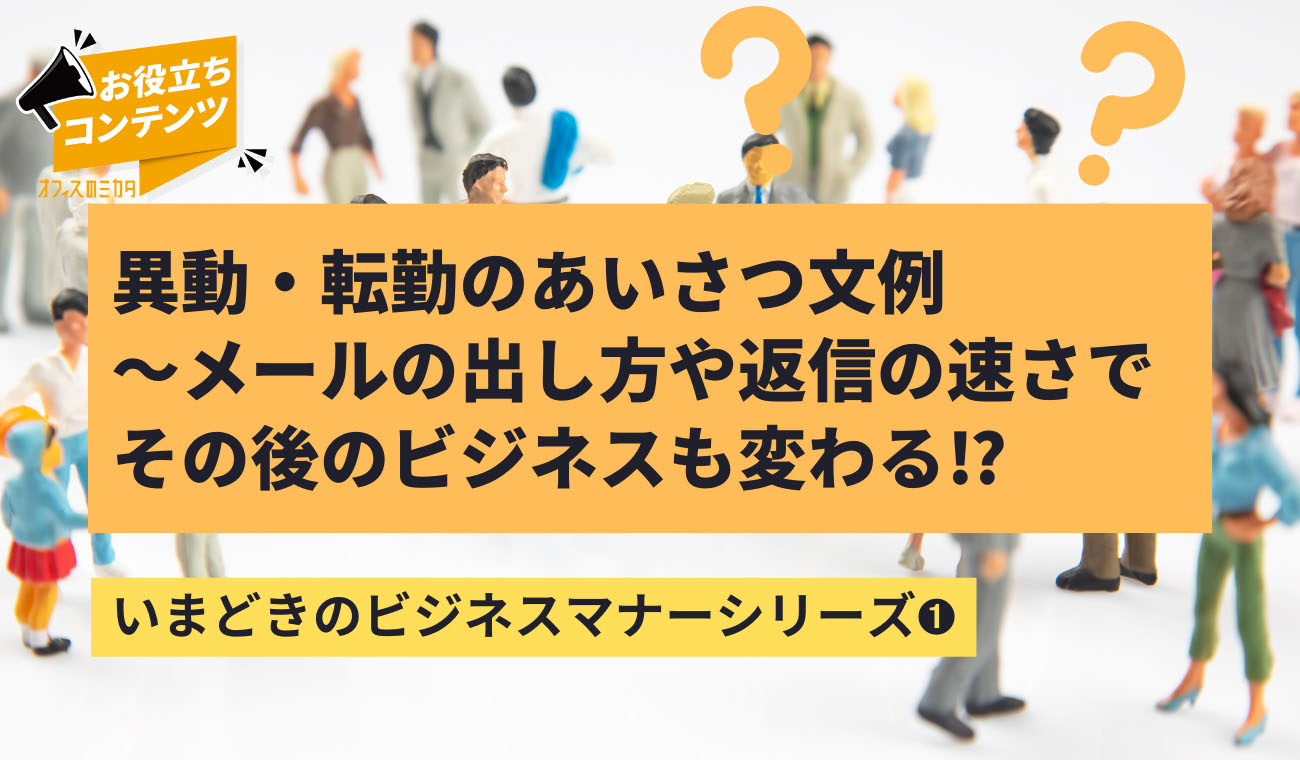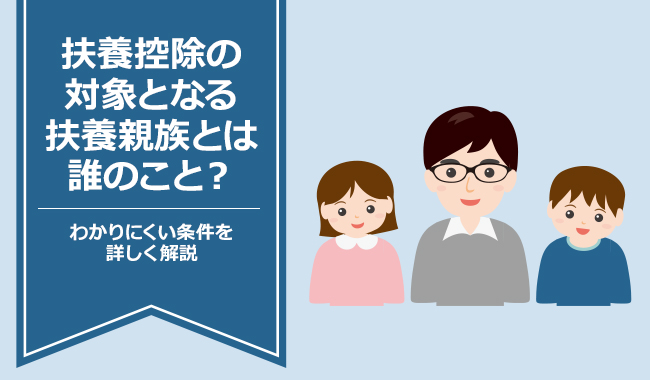定額減税対応をスケジュールと合わせて解説! いつまでに何をすればいい? OBC解説セミナーより
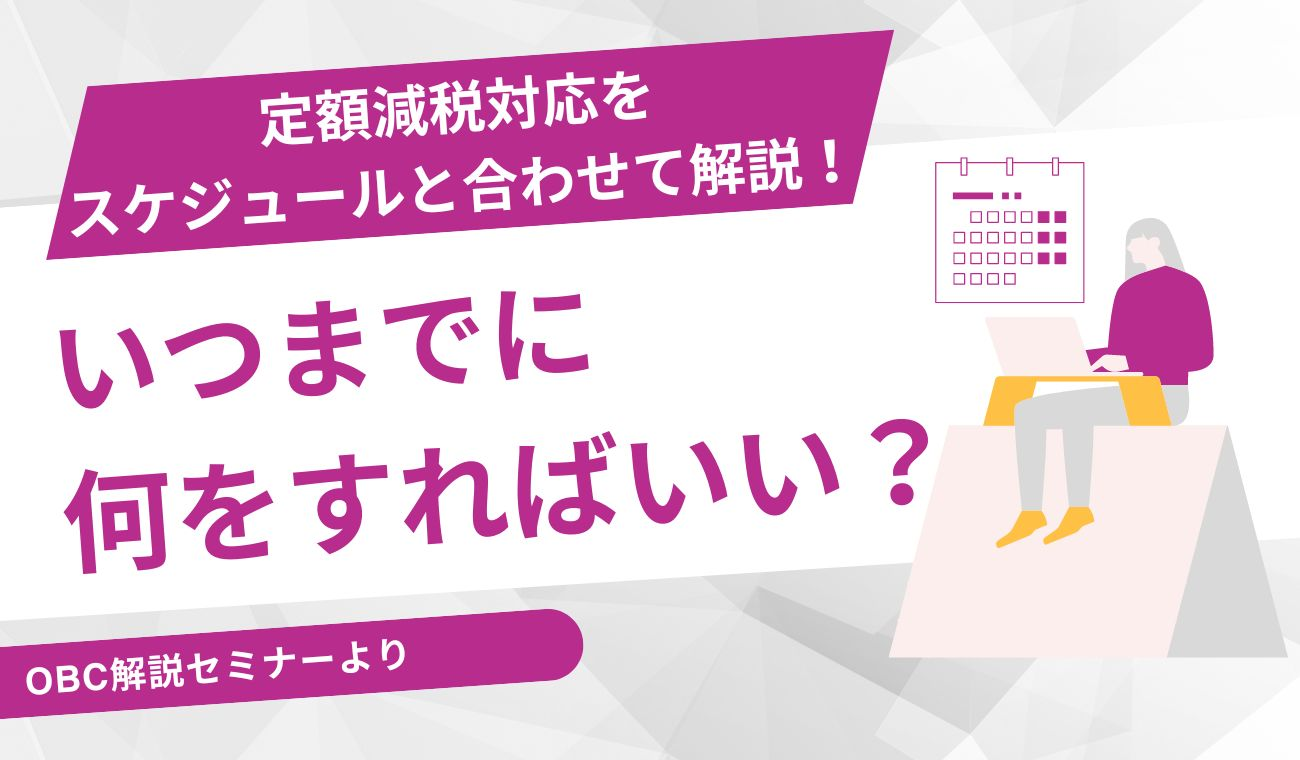
会計システム「勘定奉行」などバックオフィスの実務を支援するサービスを数多く手がける株式会社オービックビジネスコンサルタント(以下、OBC)が、令和6年(2024年)の定額減税に関するセミナーをオンラインで行っている。6月以降の給与計算に大きく影響する定額減税の制度概要や具体的な実務対応について、社会保険労務士がポイントを解説する内容だ。とくに直近で必要になる対応や注意点について、同セミナーの内容を踏まえてご紹介したい。
目次
●定額減税とは
●定額減税の方法は2つ
●「月次減税」の方法
●「年調減税」の方法
●実務上の注意点
●定額減税の対応スケジュール
●まとめ
定額減税とは
定額減税とは、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、個人住民税1万円の計4万円を減税するものだ。賃金上昇が物価高に追いついていない状況を鑑み、デフレからの脱却を図る一時的措置として実施が決定された。
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である日本国内居住者で、かつ令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1805万円以下の人となる。給与収入のみの場合は、2000万円以下だ。
本人だけではなく、同一生計配偶者や扶養家族(16歳未満も)も対象となる。
定額減税の方法は2つ
住民税については各自治体が計算してくれるため、労務担当者が実務上特に注意すべきなのは所得税のほうだ。OBCのセミナーでは、定額減税の方法としてまず押さえておきたいこととして、所得税は対象者全員に対し「月次減税」と「年調減税」のいずれも必要になることが示された。
月次減税とは、6月以降、控除合計額を控除しきれるまで、毎月の給与・賞与の所得税から定額を減税すること。対象者は、令和6年6月1日の時点で給与の支払者のもとで勤務しており、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額票の甲欄適用者(扶養控除等申請書を提出している人)をいう。そして年調減税は、年末調整の対象となる人の年調所得税額から定額を減税することだ。
「月次減税」の方法
対象者ごとに算出した減税額を、6月1日以降に支払う給与または賞与の所得税額から差し引いて控除する。控除しきれない場合は、次の月の給与など、次に支払われる賞与・給与の所得税額から差し引き、これを控除しきれるまで行う。
例えば、定額減税の対象者である社員Aさんに扶養対象となる配偶者がいるとしよう。(所得税の)定額減税額は、3万円×2人で6万円だ。6月分の給与にかかる所得税額が1万2000円だった場合、まずは所得税額を0円として1万2000円を控除する。これで、控除すべき減税額の残りは4万8000円となる。
7月には給与の前に賞与が支払われたとする。賞与にかかる所得税額が4万円だった場合、残りの減税額は4万8000円なので、減税額の残りは8000円。これを7月給与分の所得税から控除し、次の給与からは控除対応が不要になる。

※引用元:OBC「令和6年 定額減税の制度と実務ポイント解説セミナー」資料より(登壇:アクタス社会保険労務士法人)
「年調減税」の方法
年末調整において定額減税を反映するときには、例年行っている年末調整の通りに年税額を計算し、最終段階で定額減税額を反映する必要がある。所得税額を算出し、そこから住宅借入金等特別控除額を差し引いて年調所得税額を算出した上で、定額減税額を差し引くのだ。

出典元:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた」より
そして、令和6年中に徴収した所得税と最終的な年税額を比較するときは、減税分がきちんと反映されていることを必ずチェックしなければならない。反映されないまま比較してしまうと、せっかく減税を受けたのに追加徴収となってしまう可能性があるためだ。
実務上の注意点
合計所得1805万円(給与のみの場合2000万円)を超える人も、月次減税を行わなければならない。減税制度の対象外ではあるものの、月次減税事務の対象外ではないためだ。
また、令和6年6月2日以降に入社した人や、扶養状況の変更が生じた人については、月次減税で調整は行わず、年調減税で調整することになる。
定額減税の対応スケジュール
今後、労務担当者はどのように定額減税に対応していけば良いだろうか。OBCのセミナーでは、具体的な対応スケジュールが示された。以下に紹介したい。
5月下旬まで:扶養情報を把握し内容を精査
(対応済みの担当者にとっては確認事項となるが)5月下旬までに、甲欄適用者である社員の扶養情報の把握を。扶養情報の調査は、扶養控除等申告書などからも情報収集できるが、改めて従業員全員の現況を知る必要がある。書類を提出した時点から、扶養状況が変わっている可能性もあるためだ。
定額減税の対象となる配偶者や扶養親族は以下の通り。
・配偶者:居住者であり、納税者と生計を一にしており、かつ合計所得金額が48万円以下(給与収入のみ103万円以下)
・扶養親族:居住者であり、納税者と生計を一にしており、かつ合計所得金額が48万円以下であり、6親等内の血族及び3親等以内の姻族。16歳未満の人を含み、配偶者は除く。
6月上旬~中旬:給与・賞与計算への反映
給与計算時に注意したいのが、6月1日以降、最初に支給される給与・賞与から順に税額を控除する必要があるということだ。6月に賞与を予定している会社もあるだろう。6月分の給与よりも、賞与を支払う日にちが早ければ、賞与から先に控除する必要がある。「6月末までに準備が終われば良い」と考えていると、慌てる羽目になるかもしれない。
6月最初の給与・賞与の所得税から定額減税を反映し、減税しきれない場合は、次回支給へと繰り越すことになる。
なお、減税すべき金額や減税の実績を管理する、各人別控除事績簿を作っておくとよい。作成は義務ではないが、管理が煩雑になることが見込まれるため、作成が望ましい。
6月給与支給日まで:給与明細書への反映
従業員に対して、給与(賞与)明細書へ減税額を表示することで月次減税を行った実績を伝える義務がある。明細への記載場所は、どこでもOKだ。
6月に改めて確認しておきたい注意点
6月に改めてすべきなのが、5月までに確認すべきことができているかの再確認だ。具体的には、以下の内容をチェックしておこう。
・従業員情報の収集・精査が終了しているか
・いつの給与から反映し、いつ対応が終わるか従業員ごとに把握できているか
・給与明細の項目に定額減税を盛り込めているか
漏れがあったら迅速に対応し、次の給与までに体制を整えておきたい。
まとめ
OBCのセミナーでは、業務の負荷やミスを減らすためにも、定額減税を自動計算・自動管理できる仕組みの必要性が提示された。特に、負荷が大きい次の3つの業務を自動化し、効率的な給与計算を実現できることが求められる。

OBCが展開する「給与奉行クラウド」は、この3つの業務を自動化することが可能であるとされた。
「急すぎて対応が間に合わない」と感じている労務担当者もいるだろう。しかし6月の給与から対応しないと、「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」と定めている労働基準法違反になる恐れがある。直ちに罰則が適用されることはないが、労働基準監督機関による指導が入り、自主的改善を促される可能性が否めない(※1)。
OBCでは今後も定額減税に関するオンラインセミナーを積極的に開催していくとのこと。実務上の不明点が出たときなどに、活用してみてはいかがだろうか。
※1:「2024年年5月29日の内閣官房長官記者会見」で、林芳正内閣官房長官が記者の質問に答えた内容より
※参考:厚生労働省「労働基準法第24条(賃金の支払)について」

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする