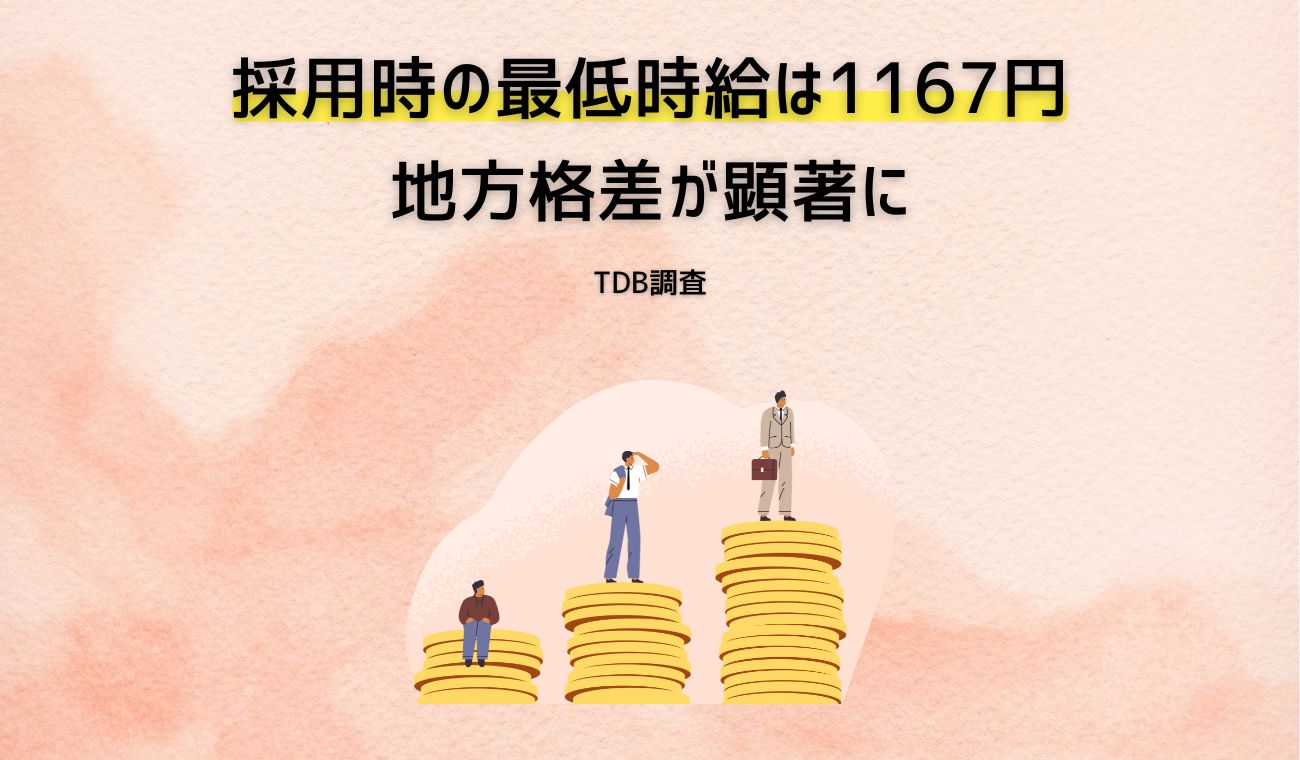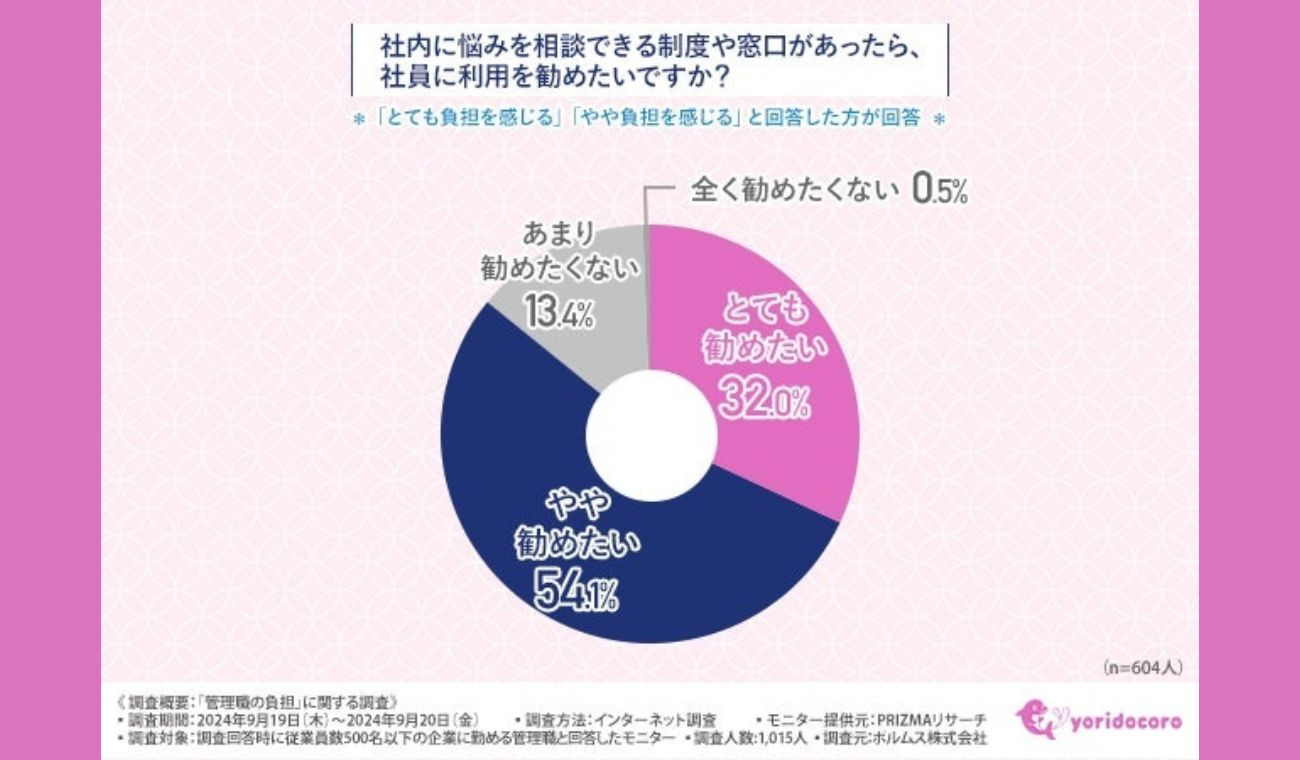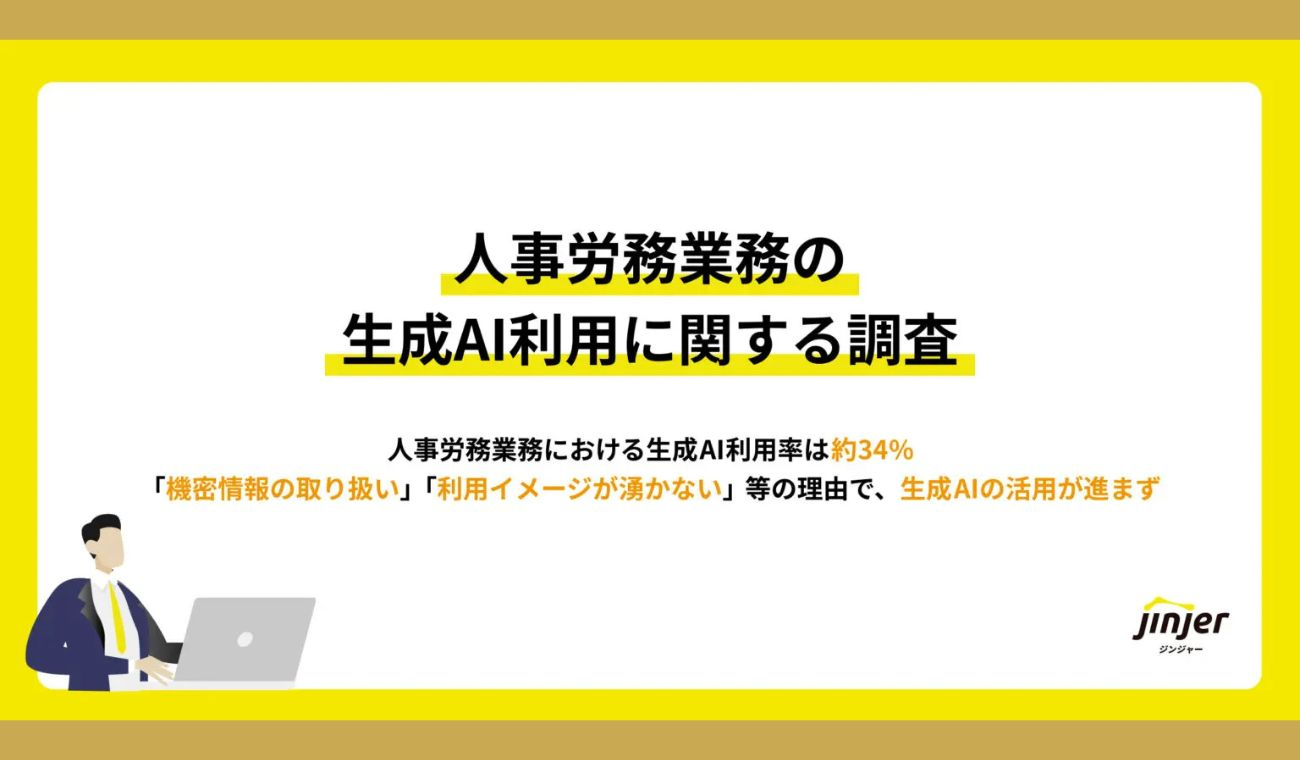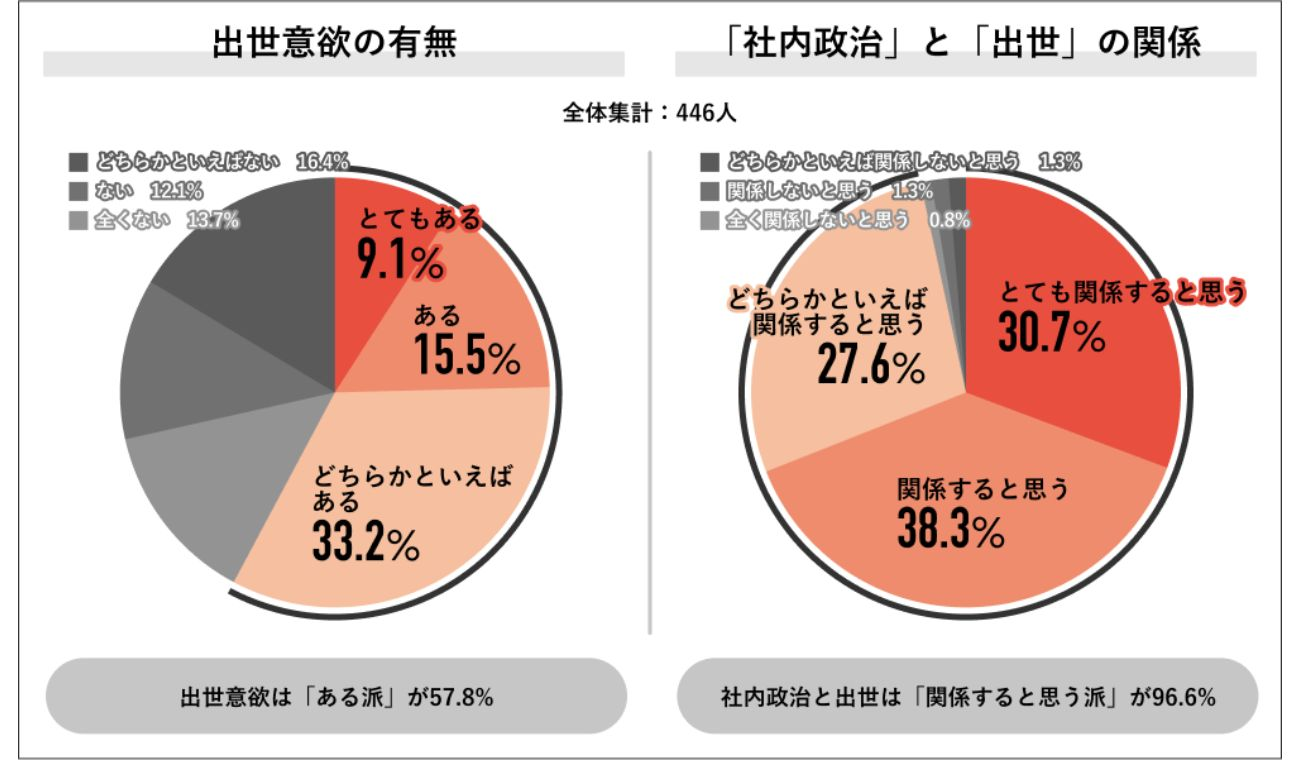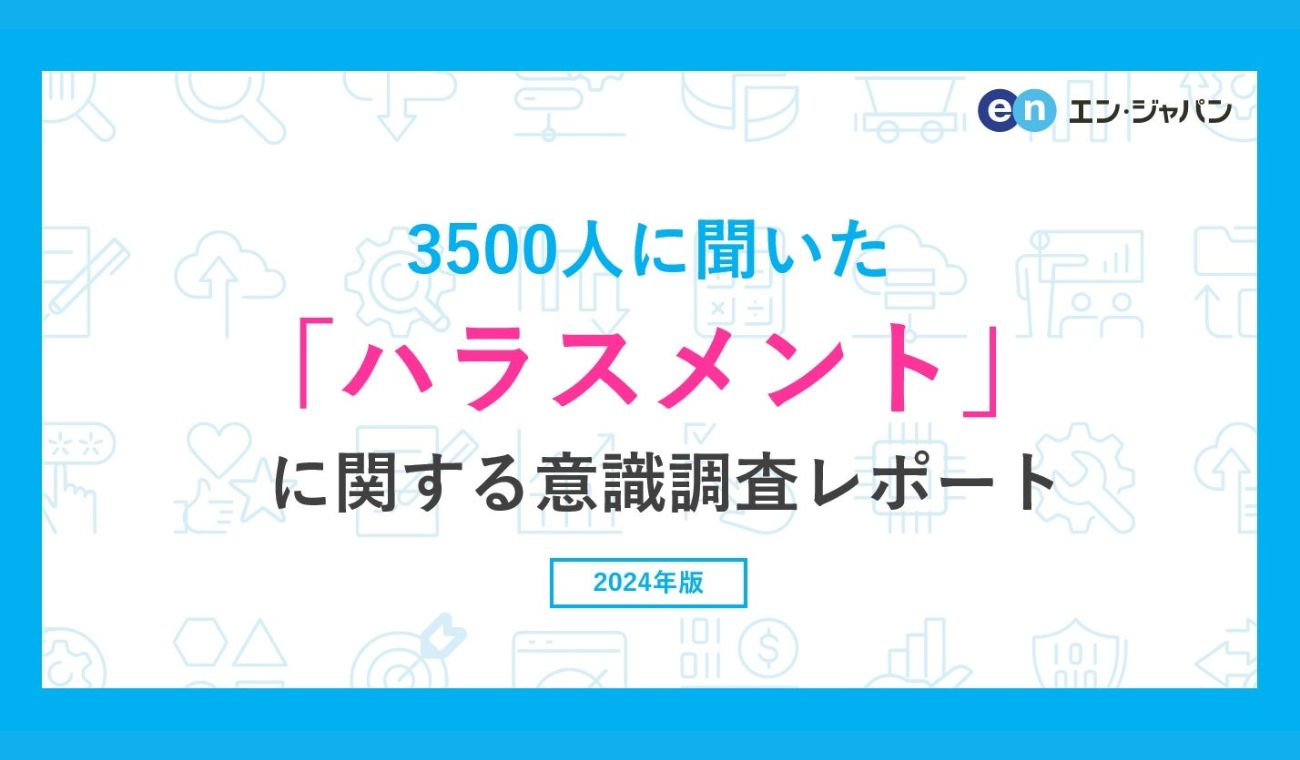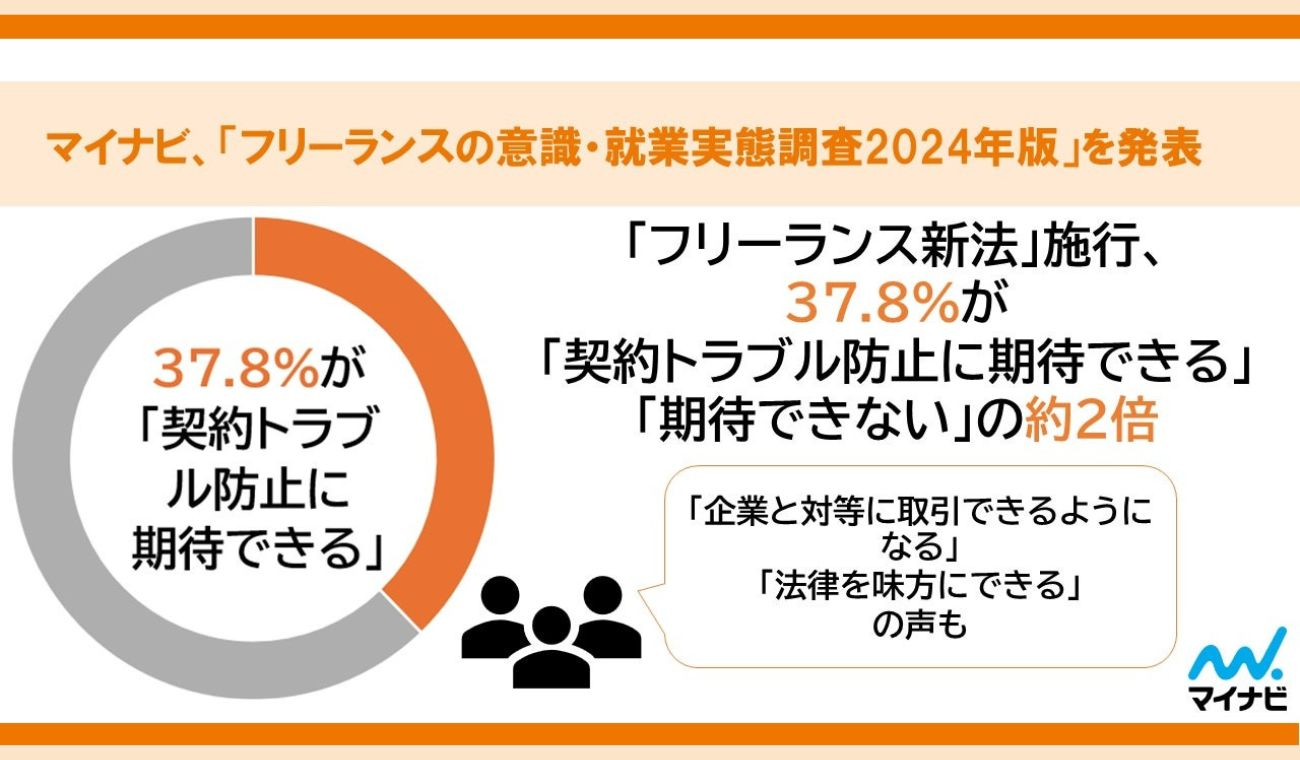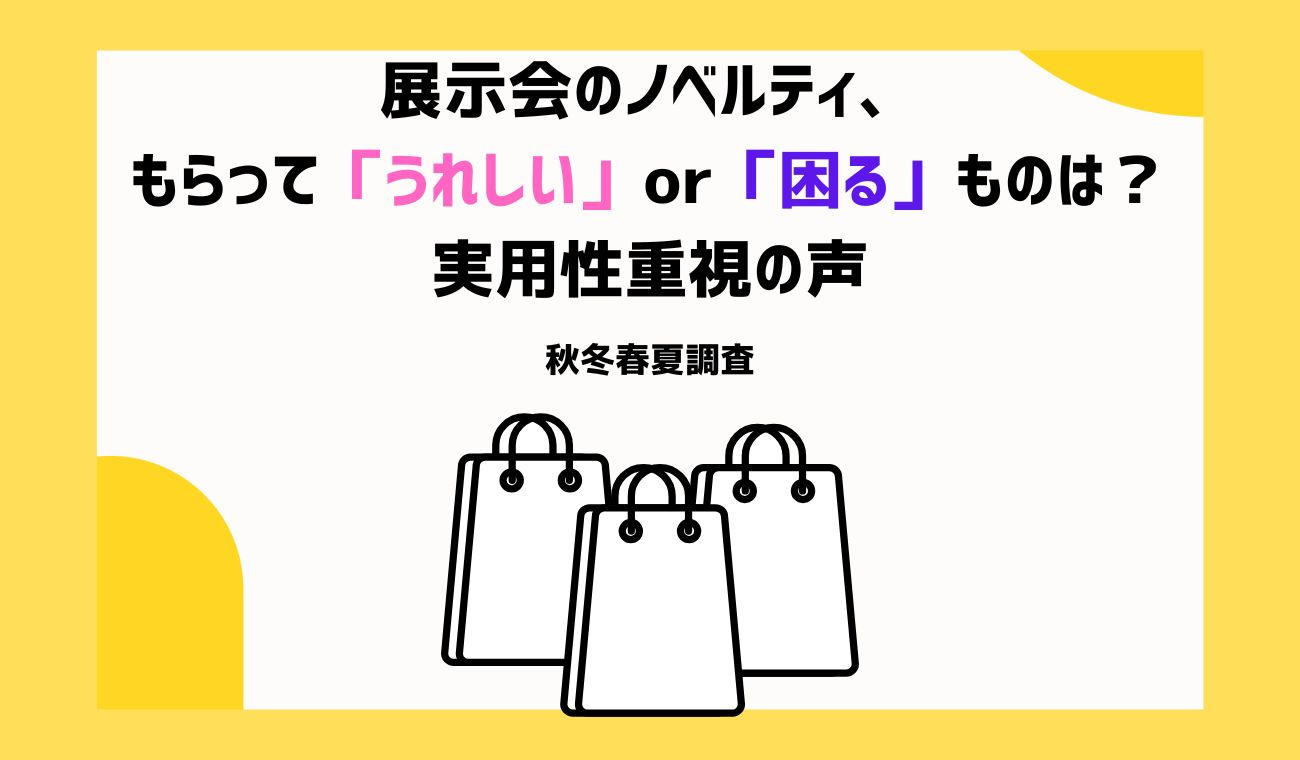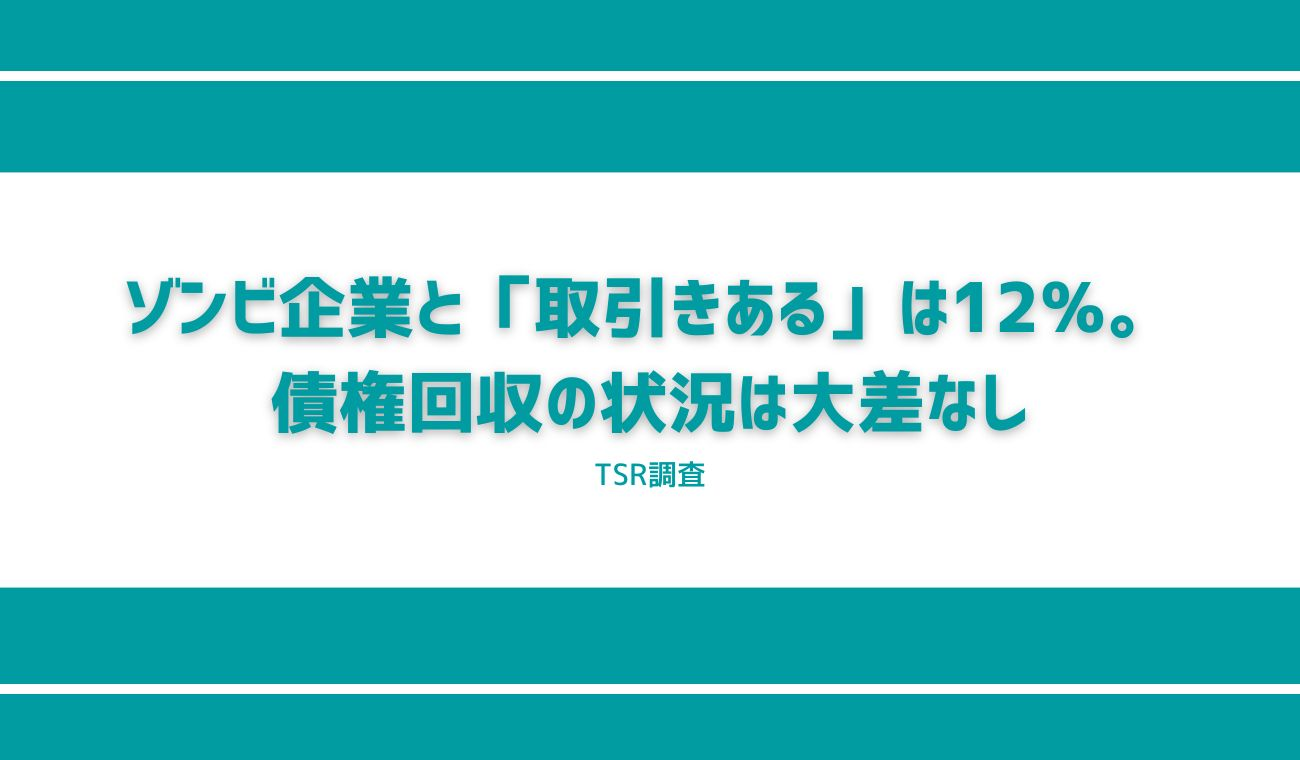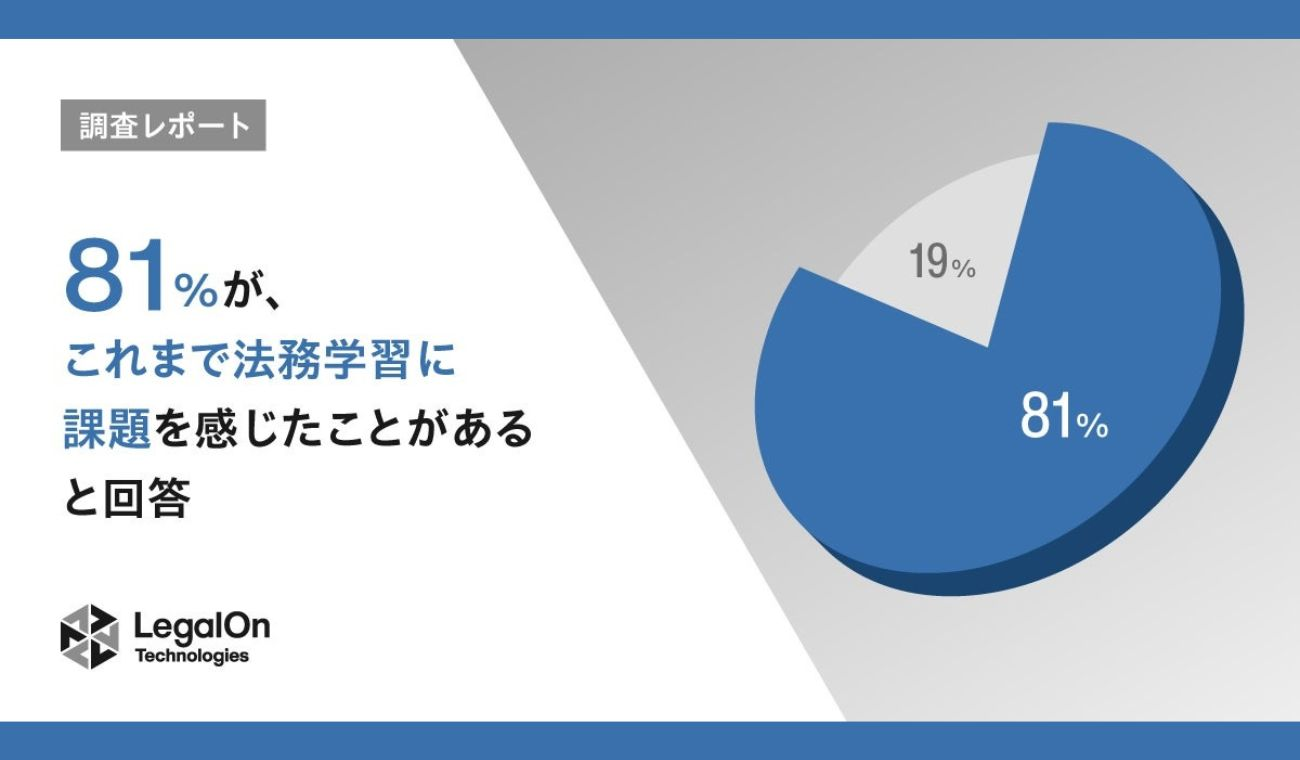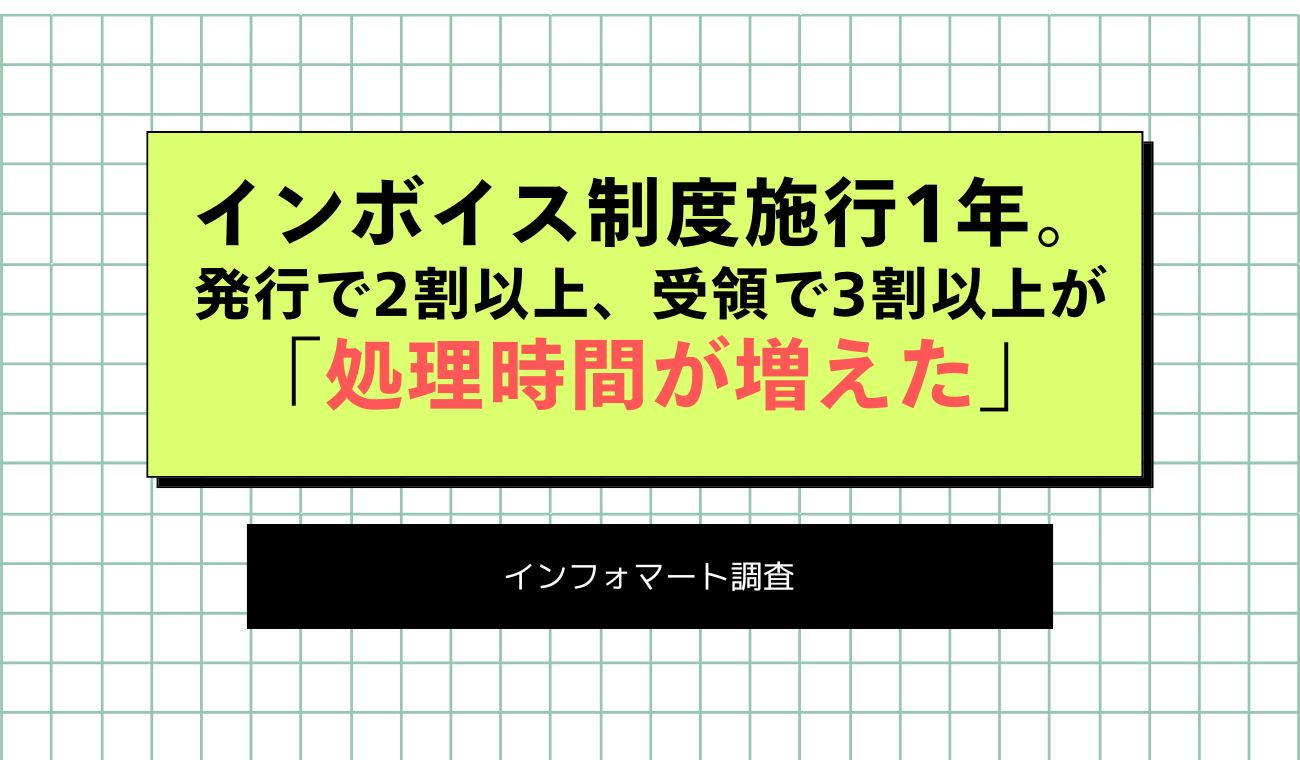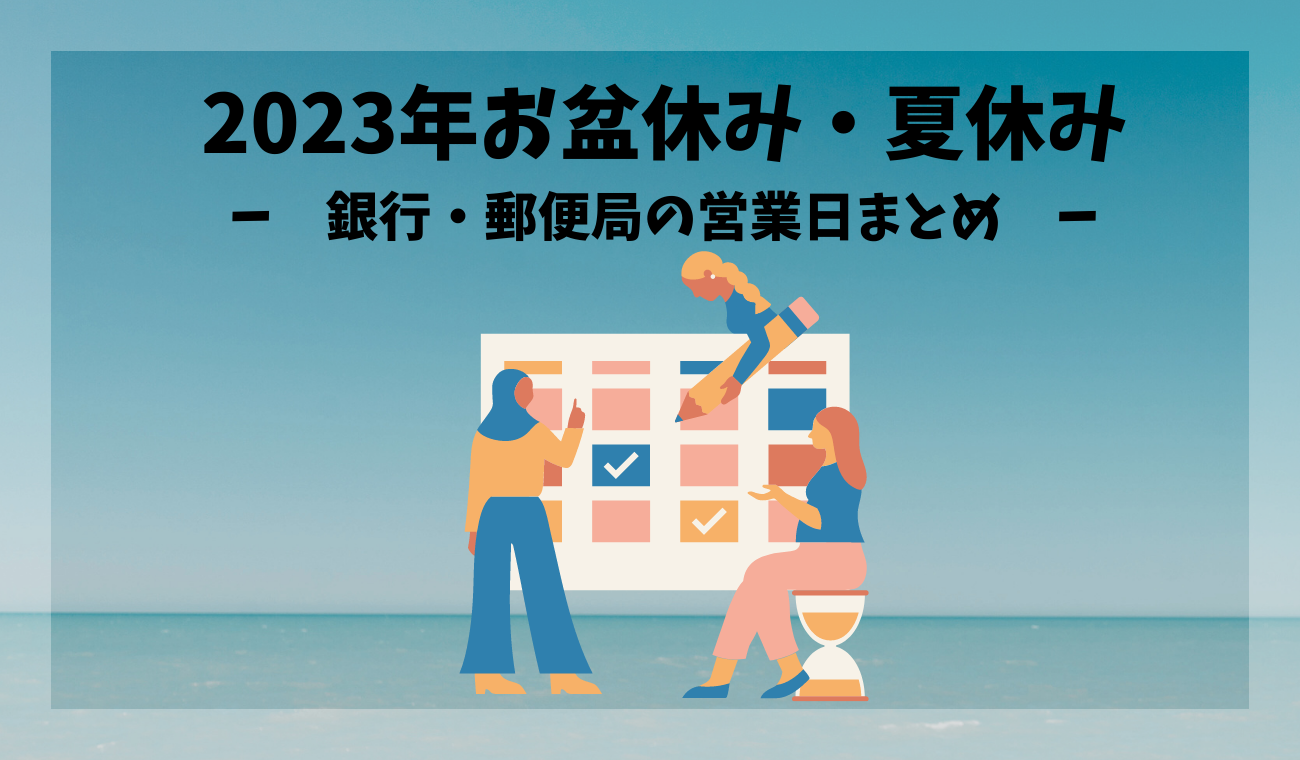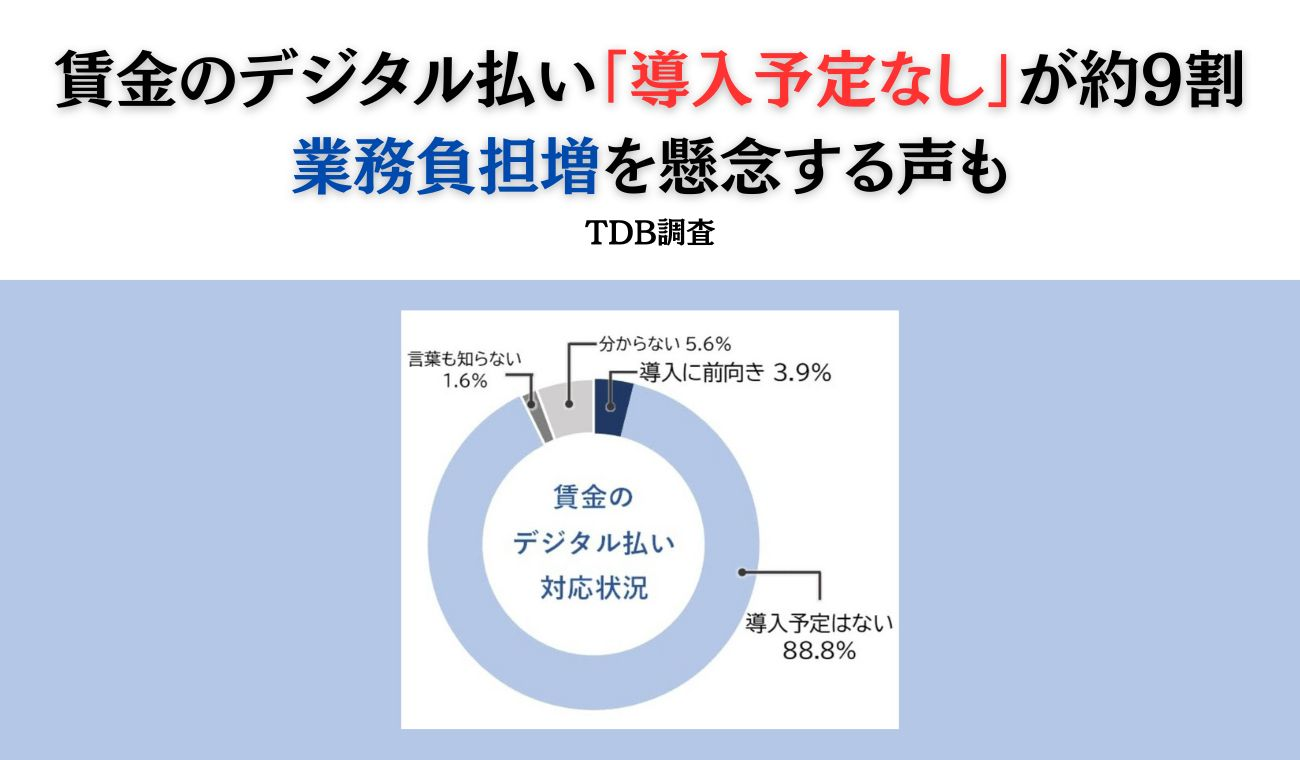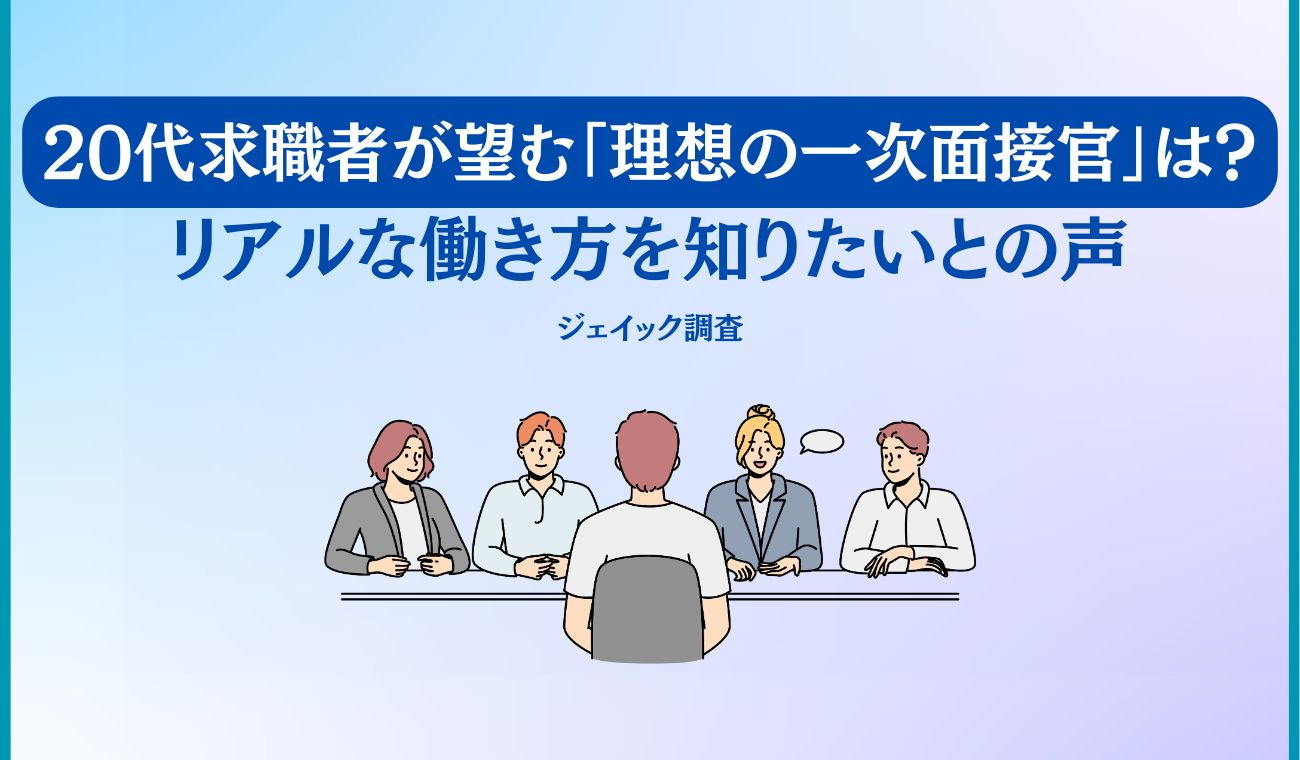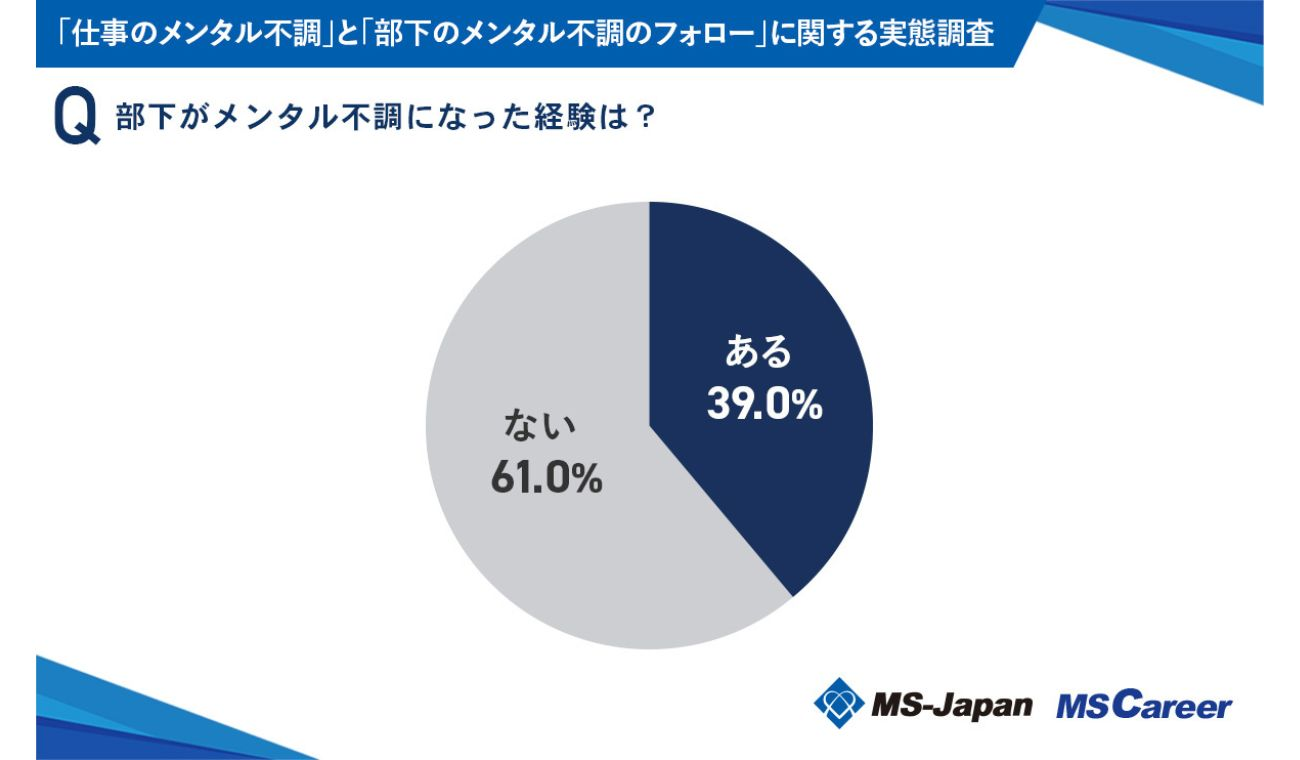シチズン時計がビジネスパーソンの「待ち時間」 意識調査 コロナ禍を経て「気長傾向」に

シチズン時計株式会社(本社:東京都西東京市、社長:佐藤敏彦)では、6月10日の「時の記念日」を前に、日常生活のさまざまなシーンでの「待ち時間」について、全国のビジネスパーソンを対象に調査した。5年前の2018年に同社が実施した同様の調査との比較も加え、待ち時間に関する意識を探っている。
調査概要
期間:2023年4月7日~9日
方法:インターネットによる調査(インターネット調査会社を通じてサンプリング・集計)
対象:20代・30代・40代・50代の全国のビジネスパーソン400人
※文中・表内の百分率(パーセント)の数値は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない(99.8%~100.2%)場合がある。
調査結果について

本調査では、「さまざまな場面・状況でイライラを感じるまでの限界時間」と、「行列して待つとき覚悟する時間」を尋ねたが、2018年に実施した同様の調査と比較すると、多くの項目で、イライラを感じるまでの時間が少し伸び、気長傾向になっていることがわかった。
大きな理由として以下の3つが考えられる。
① コロナ禍による時間意識・感覚の変化
リモートワークの拡大など働き方の変化、外出・移動の自粛による対面時間の減少、自宅で過ごす“巣ごもり”時間の増加など、コロナ禍で社会活動がスローダウンした。これまでとは異なる時間の流れ・生活リズムの中に身を置いたことで、無意識のうちに時間に対する意識や感覚が多少変化したのかもしれない。
② DX化に伴うオンライン予約やモバイルオーダーなどの普及
コロナ禍により世の中のDX化が進み、オンライン予約やモバイルオーダーなどが普及。これにより、待ち時間が予めわかるようになったことで、心の余裕が生まれたことや、待ち時間を有効に使えるようになったことが、気長になった一因と考えられる。
③ スマートフォンなど携帯端末向けコンテンツの充実
従来からスマートフォンなど携帯端末が、待ち時間中のイライラ解消に役立っていることは言われてきたが、端末で視聴できる動画やゲーム、音楽など配信コンテンツが一層充実したことでスマートフォンの使用機会が増大したことも影響しているのではないだろうか。
まとめ
調査の結果、この5年間で社会にさまざまな変化があり、ビジネスパーソンの待ち時間に対する意識は気長傾向となっていることが判明した。参考にしていただきたい。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする