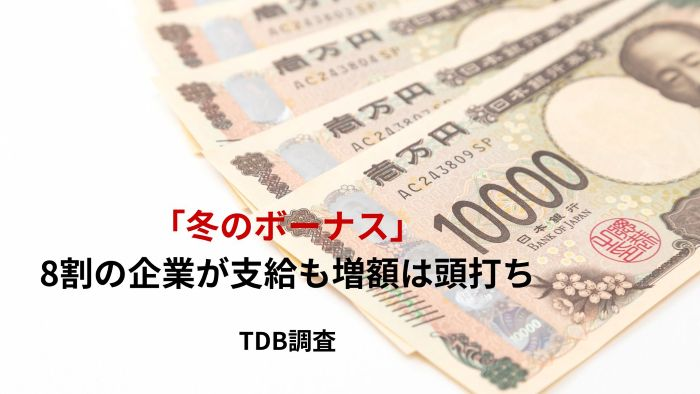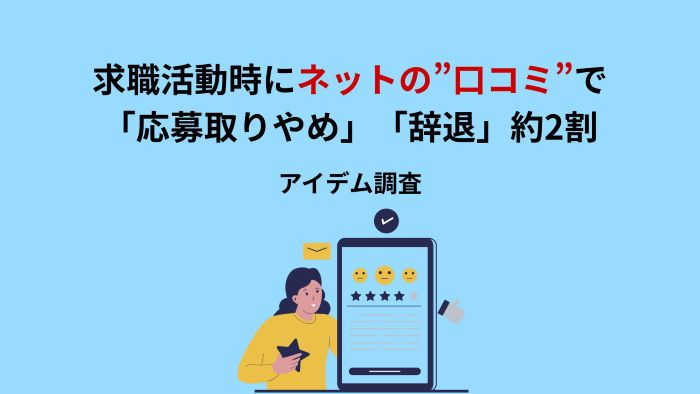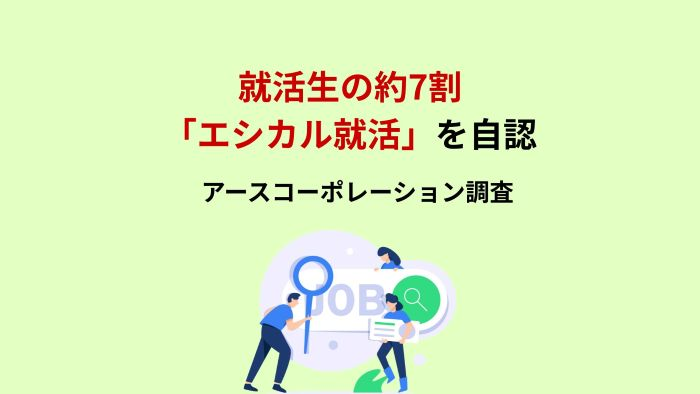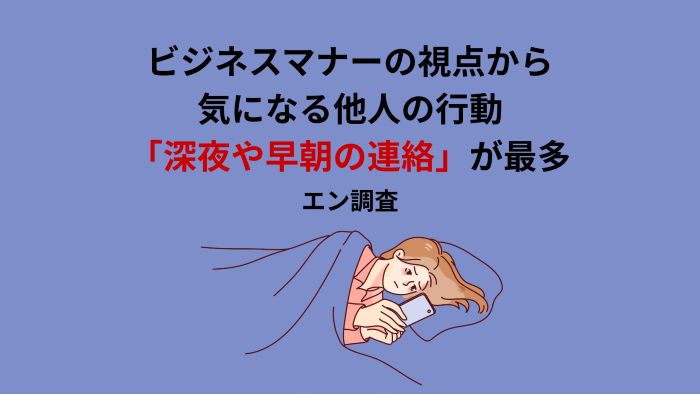7割の企業が「精神・発達障がい者の職場定着」に課題感 レバレジーズ調査
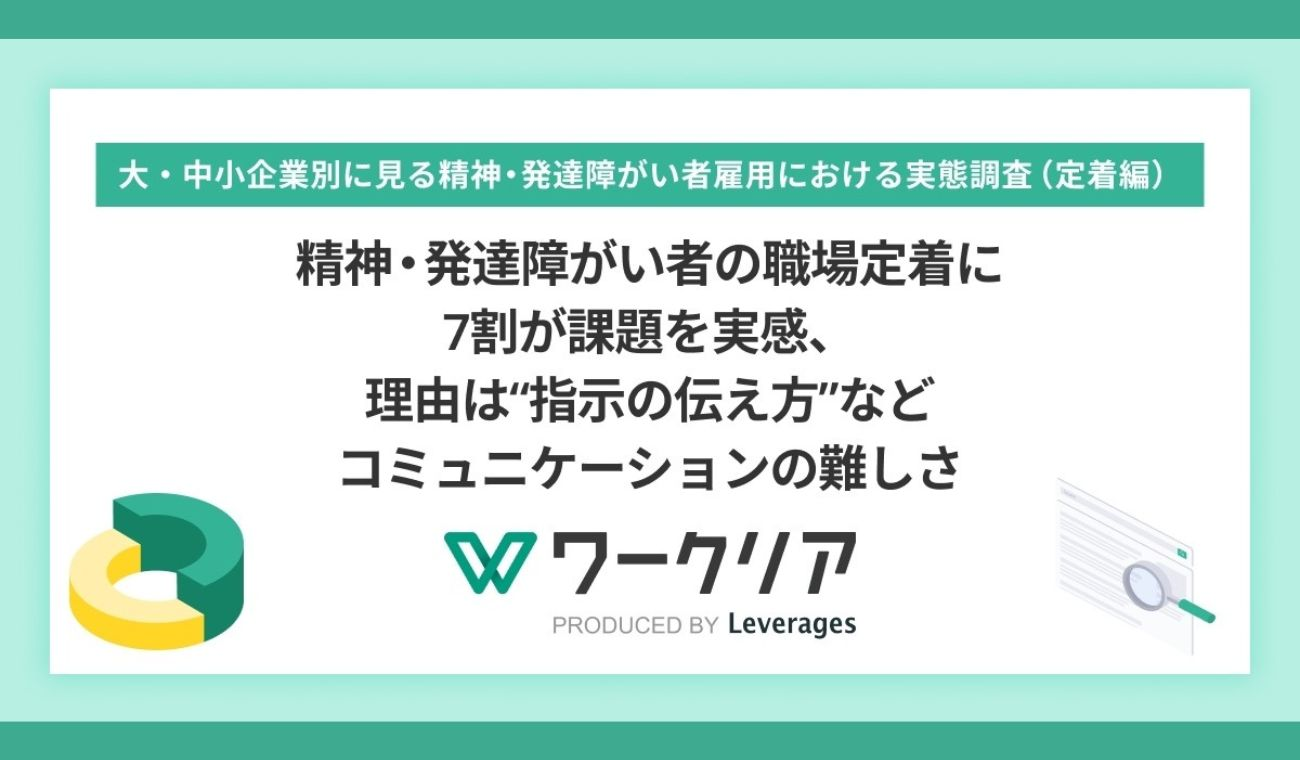
レバレジーズ株式会社が運営する障がい者就労支援サービス「ワークリア」は、障がい者雇用の担当者を対象に調査を実施。近年増加傾向にある精神・発達障がい者の雇用について、入社後の定着に関する課題や具体的な取り組みの実態を明らかにした。
調査概要
調査対象:精神・発達障がいをお持ちの従業員を採用している担当者156名
調査年月:2025年4月25日~30日
調査方法:インターネット調査
回答者数:156人
調査主体:レバレジーズ株式会社
実査委託先:GMOリサーチ&AI株式会社
本調査における企業規模の定義:
中小企業/従業員数~999人以下の企業
大企業/従業員数1000人以上の企業を指す
出典元:精神・発達障がい者の職場定着に7割が課題を実感、理由は“指示の伝え方”などコミュニケーションの難しさ(レバレジーズ株式会社)
精神・発達障がい者の職場定着「コミュニケーション」が課題か

本調査ではまずはじめに「精神・発達障がい者の定着に関して課題を感じるか」と質問。その結果、約7割の採用担当者が「非常に感じている(23.1%)」と「どちらかというと感じている(45.5%)」と回答したことが判明した。
課題を感じる理由としては「コミュニケーションが難しいから(44.9%)」「体調変動に応じた業務量や勤務時間の調整が難しいから(41.1%)」「既存社員の障がいへの理解が不足しているから(39.3%)」との声が多いようだ。
さらに、企業規模別に見ると、中小企業では大企業に比べて「職場環境の整備が不十分」や「適切な評価制度の構築ができていない」「相談体制が不足している」といった、物理的・制度的な基盤に関する課題が、より多く挙げられていることも判明している。
大企業では「体調に応じた業務量や勤務時間の調整が難しい」「障がい特性に合わせた教育・研修制度が不足している」との声が多いという。雇用する障がい者の数が多い分、一人ひとりの障がい特性に合わせた配慮が行き届いていない現状があるようだ。
精神・発達障がい者の早期離職防止に向けた取り組み

続いて本調査では、精神・発達障がい者の早期離職を防ぐための取り組みの実施状況について質問。その結果「取り組んでいる」と回答した企業は、中小企業で53.5%、大企業では63.3%にとどまったという。
具体的な取り組みとしては、企業規模に関わらず「定期的な面談の実施」や「採用前の配属先上司や既存社員との面談」が上位に並んだことも判明。特に、中小企業では「採用前の配属先社員との面談の実施」や「必要な合理的配慮の確認」などの入社前の施策に、大企業では、「定期的な面談の実施」や「オンボーディングの実施」といった、採用後の取り組みに力を入れていることがわかった。
精神・発達障がい者の就労における最大の壁は?

次に本調査では「障がい者が働くうえで不足していると感じるもの」について質問。上位の回答には「障がい特性に合わせた合理的な配慮(40.4%)」「業務内容の適性を見極めること(38.5%)」「社内の理解(35.9%)」が挙げられたという。
同社はこの結果から、一人ひとりに合わせた配慮やフォローが求められる中で、企業側が具体的な対応策や判断基準に迷うケースが多いと推察。現状の施策が適切であるという確信を持てていない可能性を指摘した。
また、企業規模別で比較した結果、中小企業は「社内の理解」「相談しやすいサポート体制」「キャリア形成の制度・機会」について、大企業よりも不足していると感じていることが判明。一方で大企業では、中小企業よりも相対的に「業務内容の適性を見極めること」や「柔軟な出勤体制を構築すること」が足りないと感じている様子がみられた。
まとめ
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センターの調査によれば、精神障がい者の入社後1年以内の定着率は49.3%と、ほかの障がい種別と比較して低い傾向にあるという。しかし本調査では約半数の企業が精神・発達障がいがある従業員の定着に取り組めていない現状が明らかになった。
精神・発達障がいがある従業員の離職を防止する上では、一人ひとりの特性を知り、適切な配慮ができる環境を整備する必要がある。担当者だけでは判断が難しい場面も多くあるだろう。福祉業界のネットワークを活用することや、専門家によるサポートを受けることも検討するといいのではないだろうか。
また同社は、外見から特性がわかりづらい精神・発達障がいに対して、配慮の必要性が伝わりにくく、社内理解の不足も大きな課題のひとつだと指摘する。障がい者雇用率の上昇や定着に向けては、まず社内で共通認識を持つことから取り組む必要がありそうだ。
参照:障害者の就業状況等に関する調査研究(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター)

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする