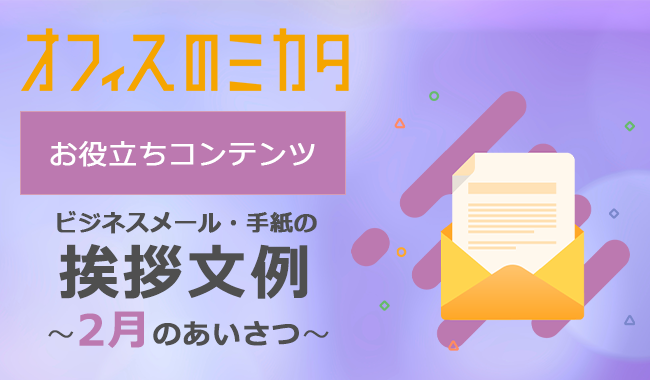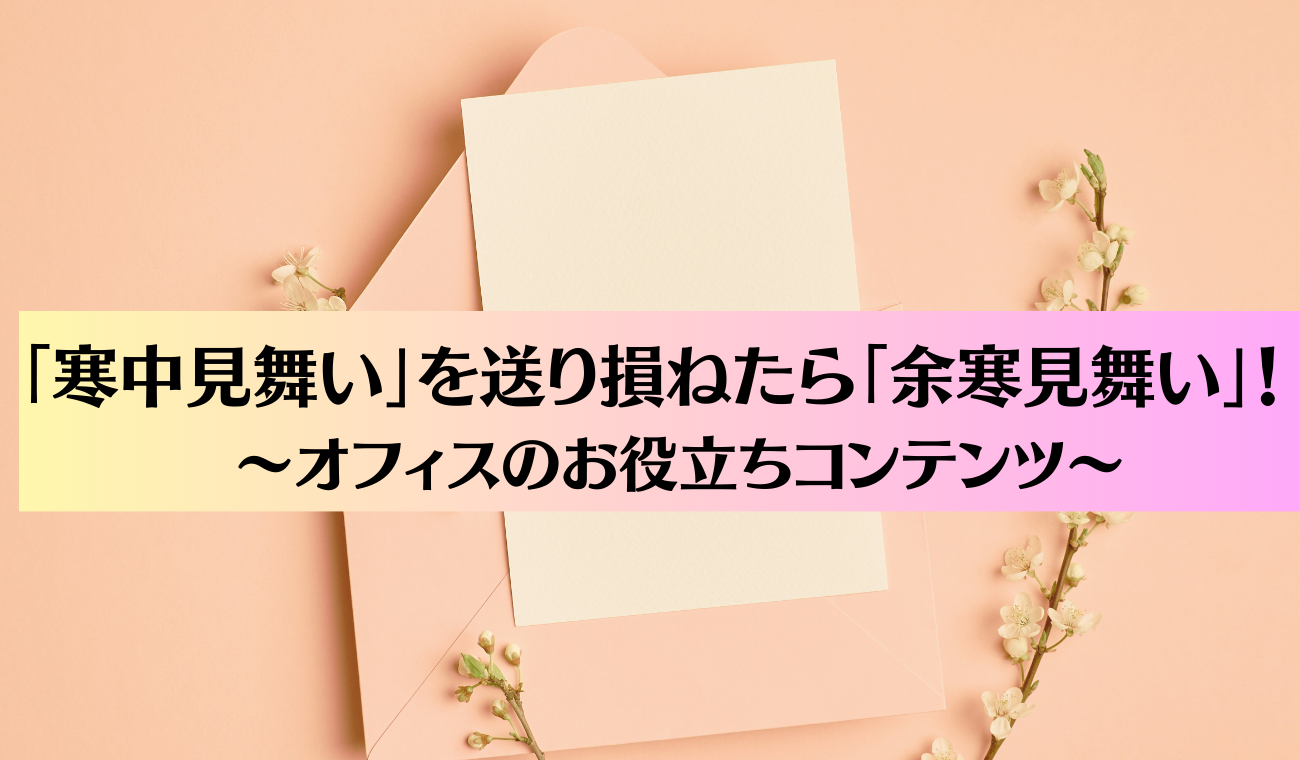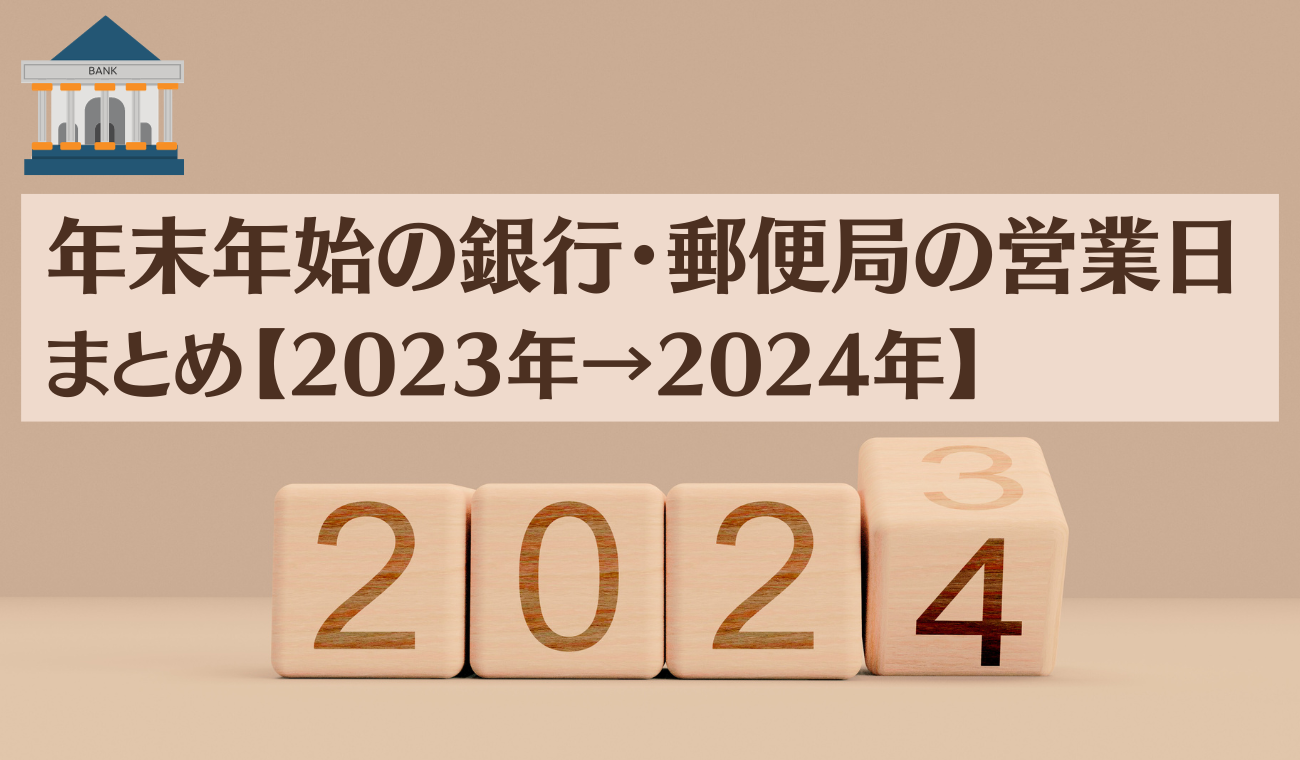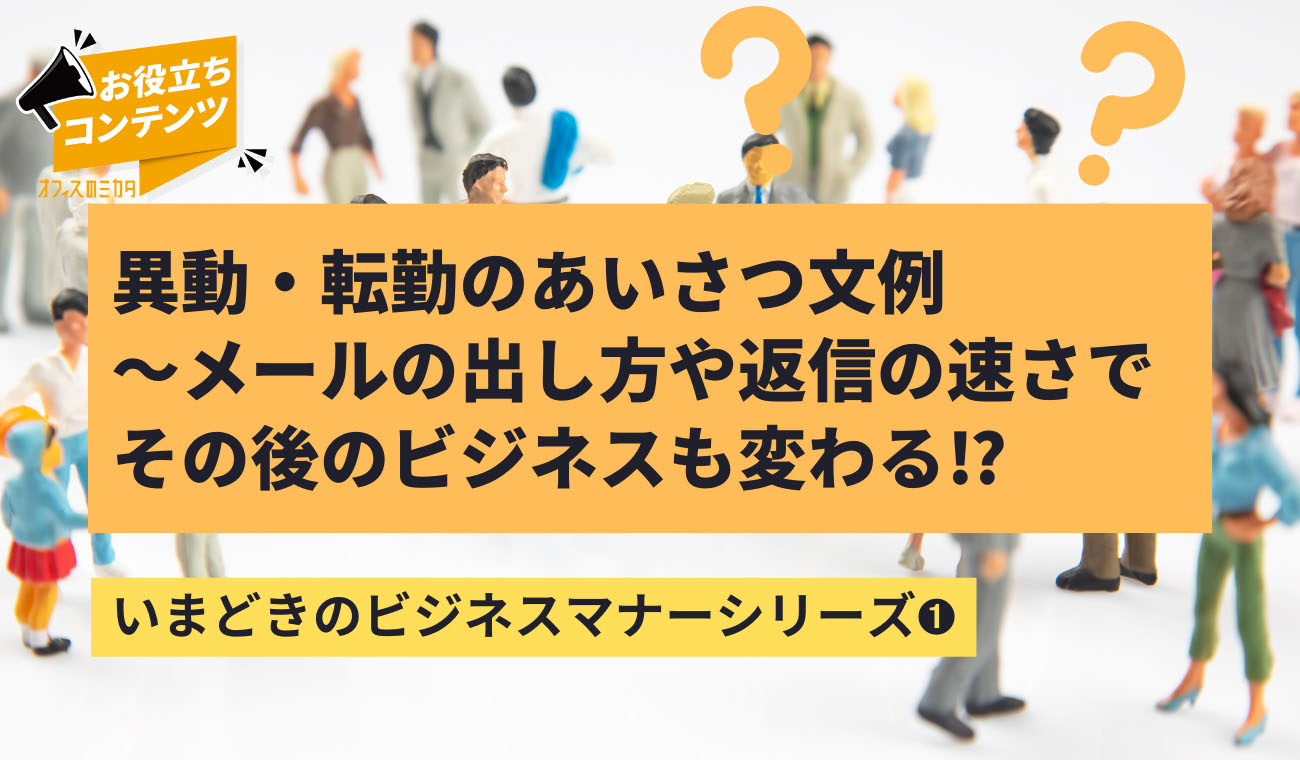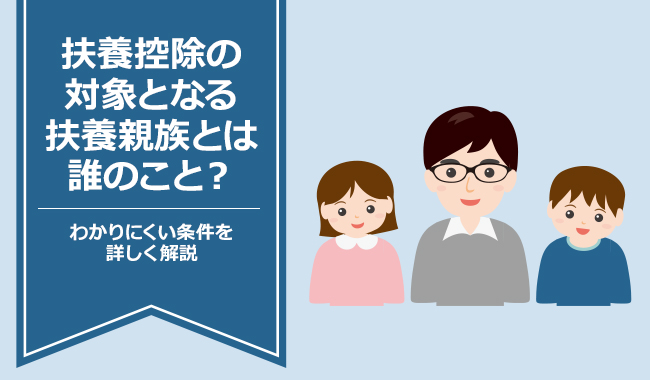eシール認定制度とは?電子署名と何が違う? 総務省が指針の最終とりまとめを策定
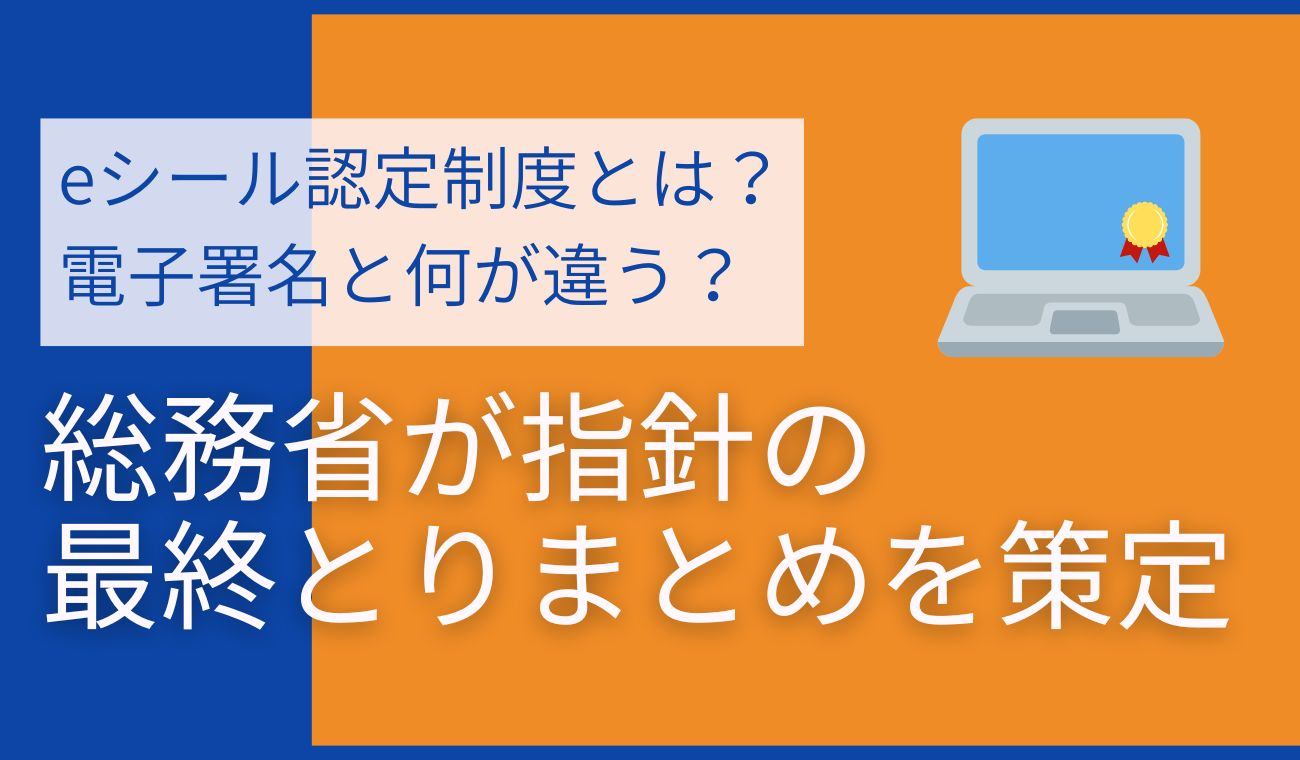
2024年4月16日、総務省は「eシールに係る検討会 最終取りまとめ」および「eシールに係る指針(第2版)」を策定した。2024年度中にもeシールの認定制度を開始できるよう、関係規程等の整備について検討を進める予定としている。電子データを安全に流通する基盤となりうるeシールの内容や、活用メリットをまとめた。
目次
■2024年度中にもeシール認定制度の運用検討へ
■eシールと電子署名の違い
eシールは発行元を証明するもの
電子署名は署名者の意思を証明するもの
■eシールのメリットと活用場所
紙ベースの企業間取引が電子化される
発行元証明の機械的、自動的処理による業務効率化
請求関係、デジタル名刺、保証書などに利用可能
■企業間取引では保証レベル1の活用を想定
■電子化や電子商取引を加速させるチャンス
2024年度中にもeシール認定制度の運用検討へ
eシールとは、企業等が発行する電子データの発行元を証明し、またデータに改ざんがないことを証明するものだ。
デジタル化推進の波を受け、総務省は2021年にeシールのあり方等を示した旧指針を策定した。その上で2023年9月からeシールに係る検討会を開催し、検討会の結果をまとめた中間取りまとめ案に対する意見を募集するなどして電子取引を安全安心に行うことができる基盤づくりを進めてきた。
2024年4月16日には、「eシールに係る検討会 最終取りまとめ(案)」および 「eシールに係る指針(第2版)(案)」に対する意見を踏まえた最終とりまとめを策定。今後、取りまとめの内容を踏まえ、2024年度中にも総理大臣によるeシールに係る認定制度の運用を開始できるよう検討を進める運びだ。
バックオフィス担当者にとって、今後対応が必要になりうるeシールの存在は注目しておきたい。eシールとは何か、利用によりどんなメリットが考えられるかを改めて解説する。
eシールと電子署名の違い
電子データに改ざんがないことを証明する物として、現状で広く利用されているのは電子署名だ。eシールと電子署名の違いは2つある。
eシールは発行元を証明するもの
違いの1つは、発行元を証明できるか否かという点だ。
eシールの定義の一つとして、「情報の出所または起源を示すためのものであること」(eシールに係る指針(第2版))がある。対して電子署名には、発行元そのものを公的に証明できる効果はない。
電子署名は署名者の意思を証明するもの
違いの2つめは、署名者の意思表示の証明ができるか否かという点だ。
電子署名の定義の一つとして、「当該情報が当該措置を行ったものの作成に係るものであることを示すためのものであること」がある(「電子署名および認証業務に関する法律」第二条)。つまり自然人のサインと同様の効果がある。
一方でeシールの付与は発行元の証明と改ざんがないことの証明が目的で、発行元となる組織等にひもづくものだ。eシールが付された電子文書等には自然人の意思が表れないため、大量の電子文書等に機械的、自動的に付与することができる。

eシールのメリットと活用場所
eシールの利用がもたらすメリットは、主に以下の2つが想定される。想定される活用場所とともに解説したい。
紙ベースの企業間取引が電子化される
これまで人手を介し、紙で行われていた企業間のやりとりを、電子的に安全に行うことが可能になる。紙そのもののコストはもちろんのこと、保存管理のためのコストや紛失リスクがなくなることも期待できる。
発行元証明の機械的、自動的処理による業務効率化
eシールは機械的、自動的処理が可能なため、組織が日常的に発出する各種の証明書などを大量に、低コストで発行することができる。バックオフィス担当者の作業効率向上に役立つだろう。
請求関係、デジタル名刺、保証書などに利用可能
企業がeシールを利用できるユースケースとしては、以下のようなものがある。
・領収書
・請求書
・見積書
・納品書
・受領書
・デジタル名刺
・企業間でやりとりされる一般的なデータ
・生産者証明書
・加工証明書
・機器の保証書
自社で利用すると利便性が高いと思われるものはあるだろうか。もし、活用することでメリットが大きいと考えるなら、今後の認定制度関連の動きに注目されたい。
企業間取引では保証レベル1の活用を想定
eシールの保証レベルは「保証レベル1」と「保証レベル2」の2段階に分かれる。各分野において、異なる保証レベルのeシールを使い分ける必要が出てくるだろう。
「保証レベル1」は、総務大臣による基準を定めず、より低コスト・簡易な手続きで大量発行されるeシールに期待されるレベルだ。一方で「保証レベル2」は、より信頼性が高くなる。認証業務のうち、総務大臣が定める基準に適合するものとして認定を受けたものだけが獲得できる。

※画像引用元:e シールに係る指針(第2版)(総務省)
企業間で日常的にやりとりされるデータ等については、保証レベル1に該当する。先ほどユースケースで例に出した取引のような、大量発行される傾向がある請求関係や名刺、保証書や証明書といった文書については、保証レベル1に該当する。
一方で、資格証明書や財務諸表など、特に高い信頼性を求められるものは保証レベル2に該当する。

※画像引用元:e シールに係る指針(第2版)(総務省)
電子化や電子商取引を加速させるチャンス
eシールを活用すれば、これまで電子化の導入をためらい紙ベースでの発行を余儀なくされていた各種請求書や証明書について、簡易的に電子化できることが予想される。紙を使うことによるコストに悩まされている企業には朗報だ。
また、電子上での商取引を安心して行えるようになるため、取引の場が広まることも想定される。すでに電子化を推進している企業にとっては、たくさんの企業がeシールを導入することにより、新規取引が期待でき、また円滑な取引が可能になるだろう。
なお、このたび紹介した「eシールに係る指針(第2版)」については認定制度の運用開始以後に適応となるため、それまでは旧指針が適用される。旧指針についても、確認しておきたい。
参考:e シールに係る指針(第2版)(総務省)

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする