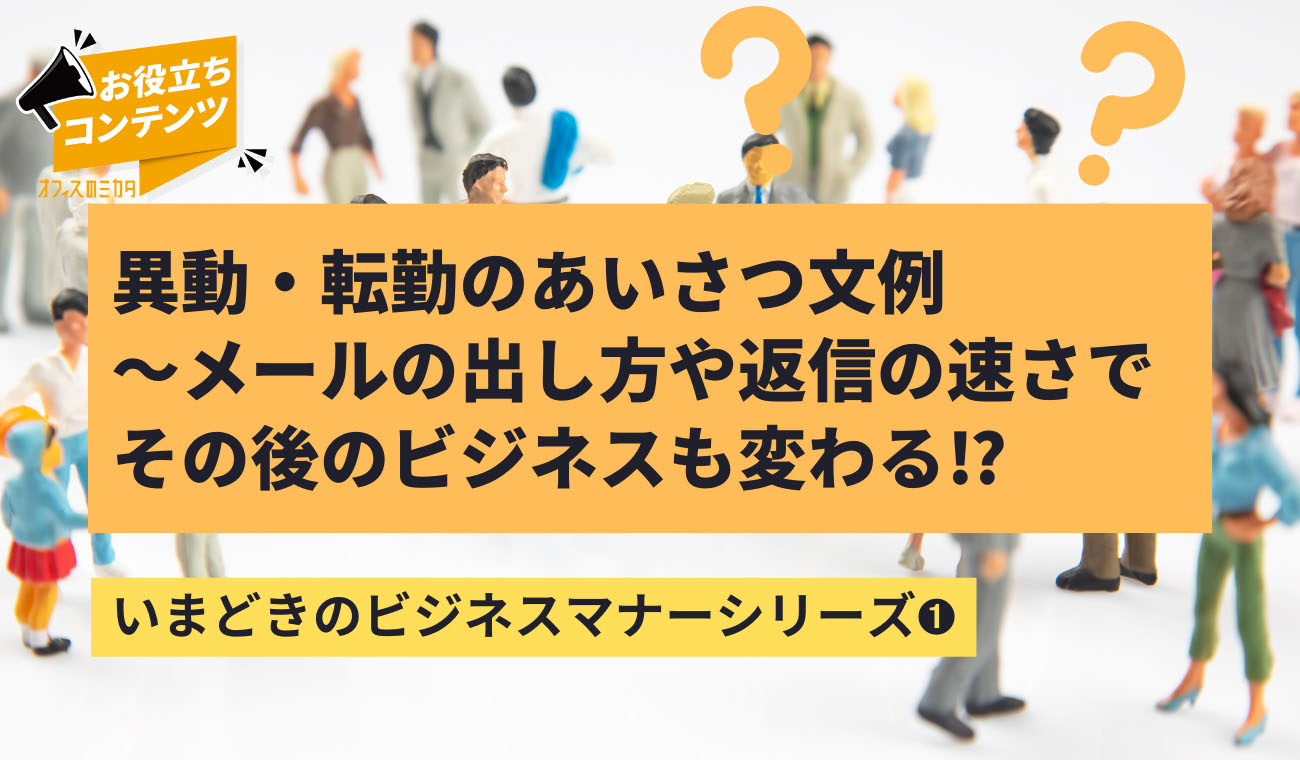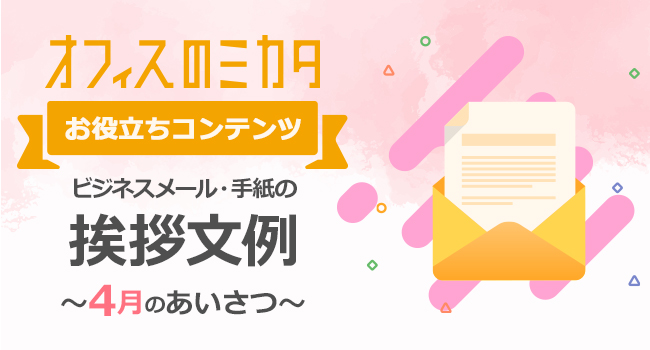HRテックから見る従業員エンゲージメント最前線 5社が語る“課題解決に向けて企業が今、できること”
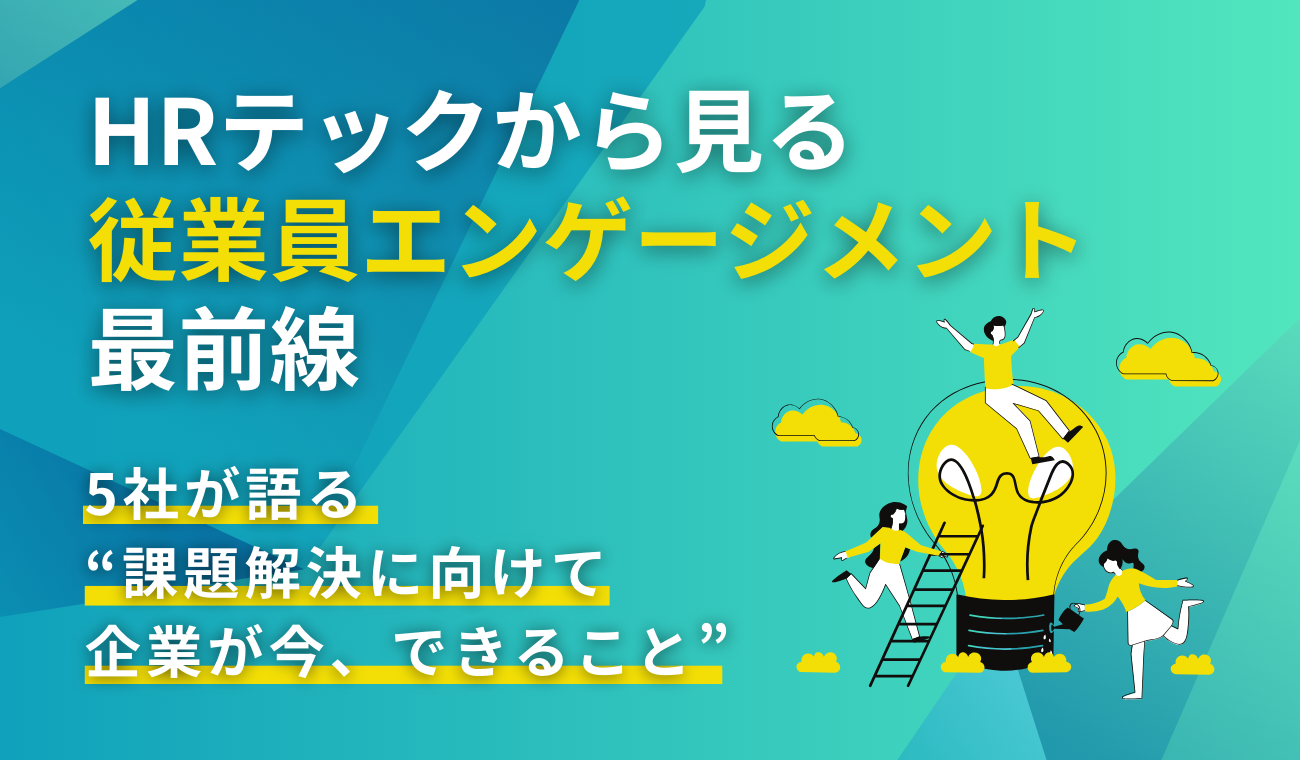
国民の5人に1人が後期高齢者(75歳以上)となり、高齢化が一層進むことでさまざまな領域に影響が及ぶとされる「2025年問題」。労働力減少による人材難に直面する企業にとって、従業員のエンゲージメントを向上させることは不可欠だが、具体的な方法が見つからず、先延ばしになってしまっている事業者も多いのではないだろうか。
そのような課題を解決するための実践的アプローチを提示するのが、今回レポートする5社だ。2025年2月に行われた合同ラウンドテーブルのテーマは「ウェルビーイングの実現と業績向上を両立するための新しいエンゲージメント戦略」。最新の調査結果や成功事例を引きつつ、それぞれの専門フィールドから語られた取り組みを紹介する。
ノンデスクワーカーの「人と組織の最大化」こそ事業成長への道(株式会社スタメン)
最初に登壇した株式会社スタメン 広報室の上田すなお氏は、ノンデスクワーカー=エッセンシャルワーカーに向けたDXとエンゲージメント強化の重要性を強調。現在多くのHRソリューションが登場しているものの、日本における全労働者の半数以上を占めるノンデスクワーカーには、テクノロジーのメリットがいきわたっていないことを指摘した。
「例えばトラックドライバーは運転を始めれば一人なのでコミュニケーションも少なく、会社への帰属意識も醸成しにくい。しかし、配達員の雰囲気が良ければ集客力向上が期待できます。ノンデスクワーカーの多い会社において、人と組織の力を最大化することによる事業へのインパクトは大きいと言えます」(上田氏)。
とはいえノンデスクワーカーの多い業種でIT人材を確保し、ソリューションの運用を定着させて成果に結びつけることは難しい。そこで上田氏は同社が提供する、従業員エンゲージメントを高めるクラウドサービス「TUNAG(つなぐ)」を活用した事例を紹介した。
「創業80年になる大阪の食品商社様が宮崎のある製造会社様をM&Aした際、お互いの企業文化や業務内容がわからないという課題がありました。そこで、『TUNAG』を活用いただき、社内インタビュー記事や従業員の仕事に対する思いに関する情報発信をすることで拠点間の相互理解が深める取り組みを実施。結果、コミュニケーションが活性化し、投稿をきっかけに新卒社員の知識を活かした商品開発も実現しています 」(上田氏)。

人事データの「ばらばら・ぐちゃぐちゃ・まちまち」問題を解決(jinjer株式会社)
続いて、クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供するjinjer株式会社 広報室の赤繁遥氏が、人事にまつわるデータを効果的に蓄積・運用できていなければ、エンゲージメント向上と事業成長にはつながらないことを解説した。
「複数の人事システムを使うことでデータが『ばらばら』に分散し、そのデータはシステムごとの表記揺れによって『ぐちゃぐちゃ』になりやすく、さらに時系列で継続的に蓄積できていないため人によって『まちまち』のデータができてしまう。私たちはこれを“人事データの三大疾病”と呼んでいます。業績に直結するエンゲージメントを生み出すためには、人事データをしっかりと統合し分析できる土台を構築して、エンゲージメントを引き上げていく必要があります」(赤繁氏)。
また、赤繁氏は「単にエンゲージメントにフォーカスすれば業績が上がる」という誤解を正し、エンゲージメント向上の“前提”となるメンタルヘルスから安定させる必要があると語る。加えて労働時間や給与情報等の「オペレーショナルデータ」と、スキルや評価、研修受講等の「タレントデータ」を、エンゲージメントやメンタルヘルス等の「センチメントデータ」に紐づけることで、人事施策をより業績に紐づけることができるようになるという(例:勤怠の欠勤情報とメンタルヘルスサーベイの結果との相関分析等)。
「経営層はエンゲージメントとその先にある業績を見ており、人事部門はメンタルヘルスを問題視するといった、意識の乖離があると施策が分散してしまいます。経営層や人事部門、各種ステークホルダーと認識を合わせられるよう、適切な権限のもと、いつでもメンタルヘルスデータやエンゲージメントデータに関係者がアクセスできる共通基盤を構築することが重要なんです」(赤繁氏)。

コストから投資へ。令和の福利厚生トレンド(株式会社KOMPEITO)
次に登壇したのは、株式会社KOMPEITO のPR・ブランディンググループ 白井小百合氏。福利厚生は明治時代からあったが、現代では従業員を「資源」として捉えるのではなく、「資本」としてその価値を最大化するために活用される時代だと、その意義の変遷を説明した。福利厚生もコストから投資へと変化し、従業員の能力開発も福利厚生の重要な役割になっているという。
「国全体を見渡すと医療健康費用のうちヘルスケアサポートの比重が上がっています。また、およそ5人に1人が後期高齢者となる『2025年問題』を前に、労働力不足への対処や介護と仕事の両立が重要な課題になっています。企業の福利厚生もメンタルヘルスケア、語学学習、女性の健康サポートなど、従来のハコモノ的サービスから自己啓発やウェルビーイングにつながるものへとシフトしています」(白井氏)。
こうした情勢の中で、株式会社KOMPEITOはオフィスに冷蔵庫を貸し出してサラダやフルーツ、お惣菜などを届ける“置き社食”サービス「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」を展開中。大手〜中小企業やホテル、病院など全国累計1万5000拠点超の導入実績を持ち、次世代型自動販売機「SALAD STAND(サラダスタンド)」の運営もスタートさせている。

多様化するリゾートバイトでウェルビーイング向上(株式会社ダイブ)
観光施設に特化した人材サービス事業を展開する株式会社ダイブの広報 原由利香氏は、観光業で働く人のウェルビーイングについて、リゾートバイトの観点から解説した。
日本政府が目標に掲げる2030年の旅行消費額は、コロナ禍前の2019年度の26.8兆円から+10兆円となる37兆円。日本経済の成長エンジンとも言える観光業だが、原氏はその分だけ人材確保が急務と話す。
「リゾートバイト(※1)は観光人材を確保できる新しい働き方です。20代を中心に50代以上まで幅広い層の方がさまざまな理由で従事し、旅をしながらの仕事や、新たな体験・出会いを求めて働いています。リゾートバイトで語学力を養いつつ資金をため、オーストラリアでのワーキングホリデーに飛び立った方という方もいらっしゃいます」(原氏)。
また、リゾートバイトは若い人の仕事というイメージが強いが、ダイブの調査によれば応募者の10人に1人が50歳以上で、その割合は急増しているという。自分の趣味や関心のある領域の仕事で若い世代と関わることによって学びを得たり、培ってきたスキルや知識を活かして働いたりと、リゾートバイトは人生の選択肢を広げる機会ともなる。
「リゾートバイトは単なる『仕事』ではなく、個人の成長やウェルビーイングの向上に貢献できます。若年層だけでなく50代、60代の方が増え、より多様な世代が活躍する場へと進化していると考えています」(原氏)。従事する人が心身ともに充足し、幸福を感じられる働き方は、生涯現役時代のキーワードになりそうだ。

※1:株式会社ダイブではリゾートバイトを「日本全国のリゾートホテルや旅館、飲食店、テーマパーク、レジャー施設、スキー場等に短期間移住し、従業員寮で生活しながら勤務するはたき方」と定義している
そもそも何のために? 人的資本経営の目的に立ち返る(株式会社リンクアンドモチベーション)
「人的資本経営において重要なのは、生産性向上など中長期的な企業価値の向上につなげる視点」と語るのは、株式会社リンクアンドモチベーション グループデザイン室の栁澤沙紀氏。同社は、20年以上にわたって組織人事コンサルティング事業を行っているが、近年多くの企業が実施している賃上げや福利厚生の拡充といった人的資本への投資にとどまるのではなく「生産性向上」との好循環をつくることが重要だと言う。
栁澤氏は、「生産性向上」に関する自社の取り組みとして、コンサル・クラウド事業における生成AI活用の効果を紹介。同社では「AIによるナレッジの蓄積・活用のサイクルなど事業インパクトを創出できる仕組み」を構築したことによって、従業員一人当たりの売上高が前年比約140%の事業インパクト創出につながったという(※2)。こうした成果を受けて、「人的資本経営の目的をしっかりと捉え直し、生産性向上につなげるモデルを自らつくることで、影響力を発揮していきたい」と話した。
「エンゲージメントと企業の投資指標には正の相関がありますが、表層的な取り組みを行うだけでは意味はない。目的を『中長期的な企業価値の向上』と設定して、経営陣が人的資本経営に本気で向き合って取り組み続けることが必要だ」と締めくくった。

※2:一部のコンサルティング部門における従業員一人当たりの売上高
まとめ
「2025年問題」に代表される働き手不足・人材難は、日本の企業にとって避けることのできない差し迫った現実。労働人口減少に歯止めがかからない以上、企業が生き残っていくには、自社の従業員が健康的に働ける環境を作り、離職を防ぎ、なおかつ一人ひとりの生産性を上げていくことが求められる。今回プレゼンに登壇した5社は、厳しさを増すビジネス環境の中で、HR領域における企業の課題を乗り越えるヒントを示したと言えるだろう。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする