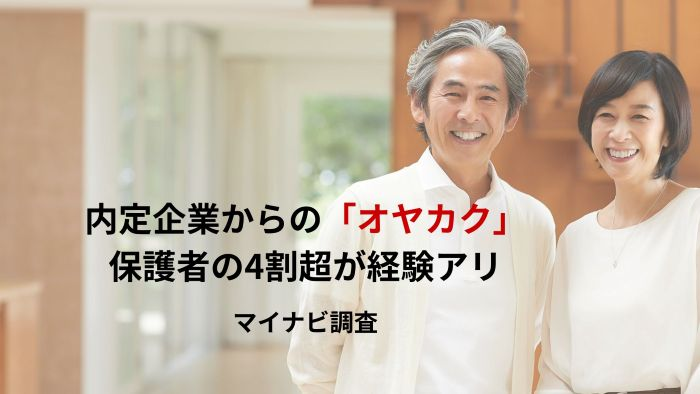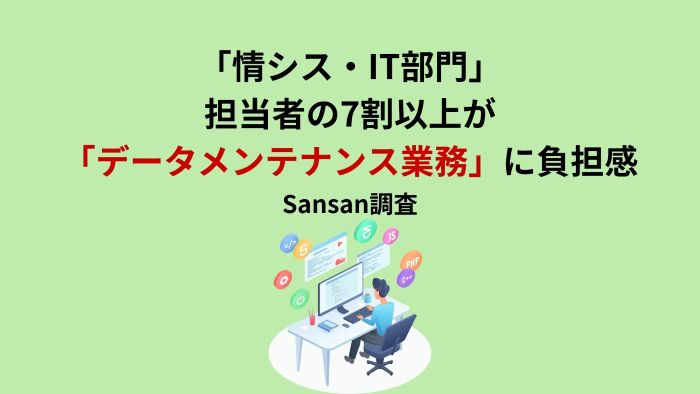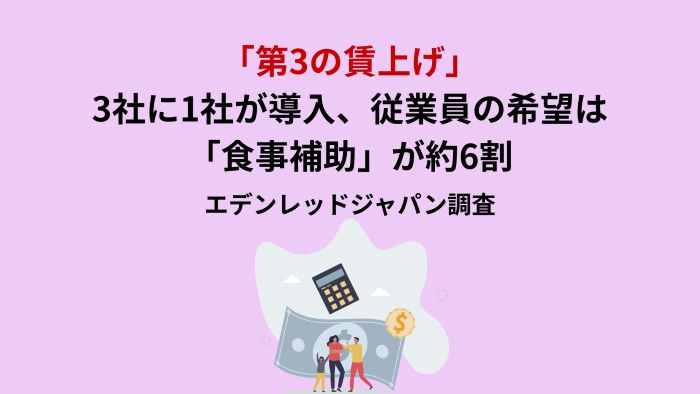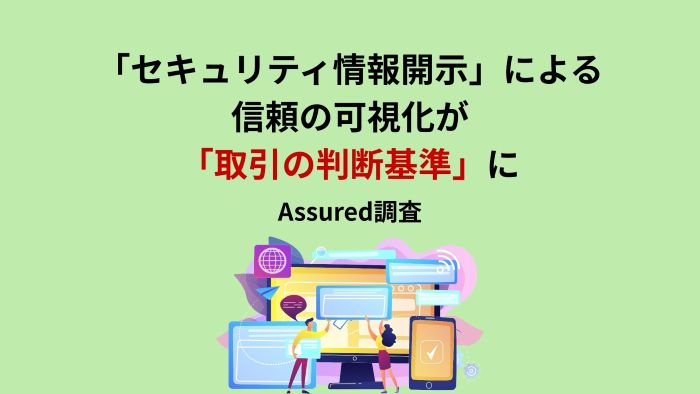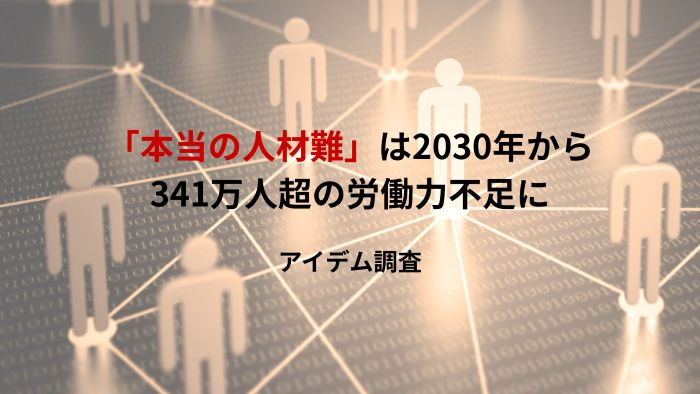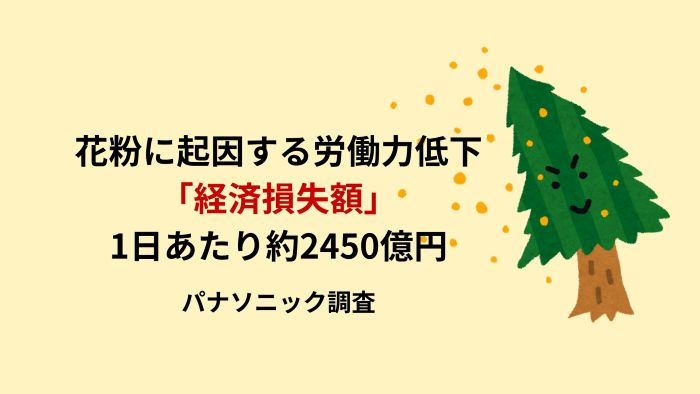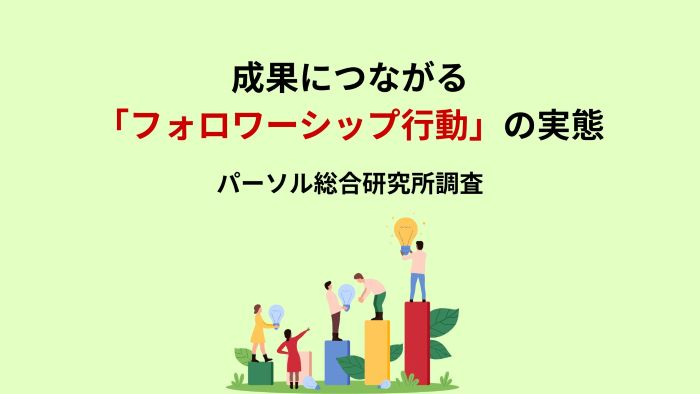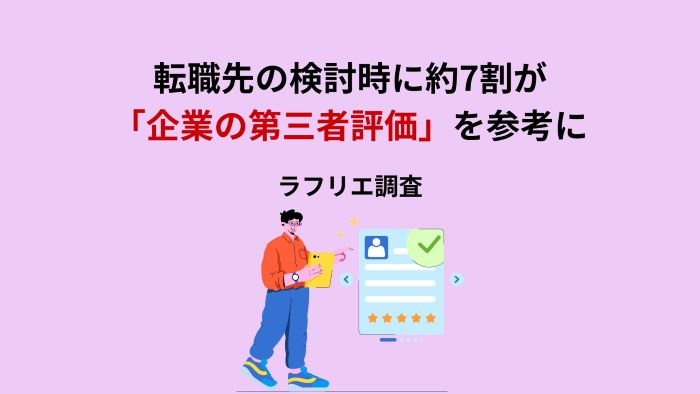自身の健康認識、男女間での差と実態は? 内閣府、男女の健康意識に関する調査結果を公表
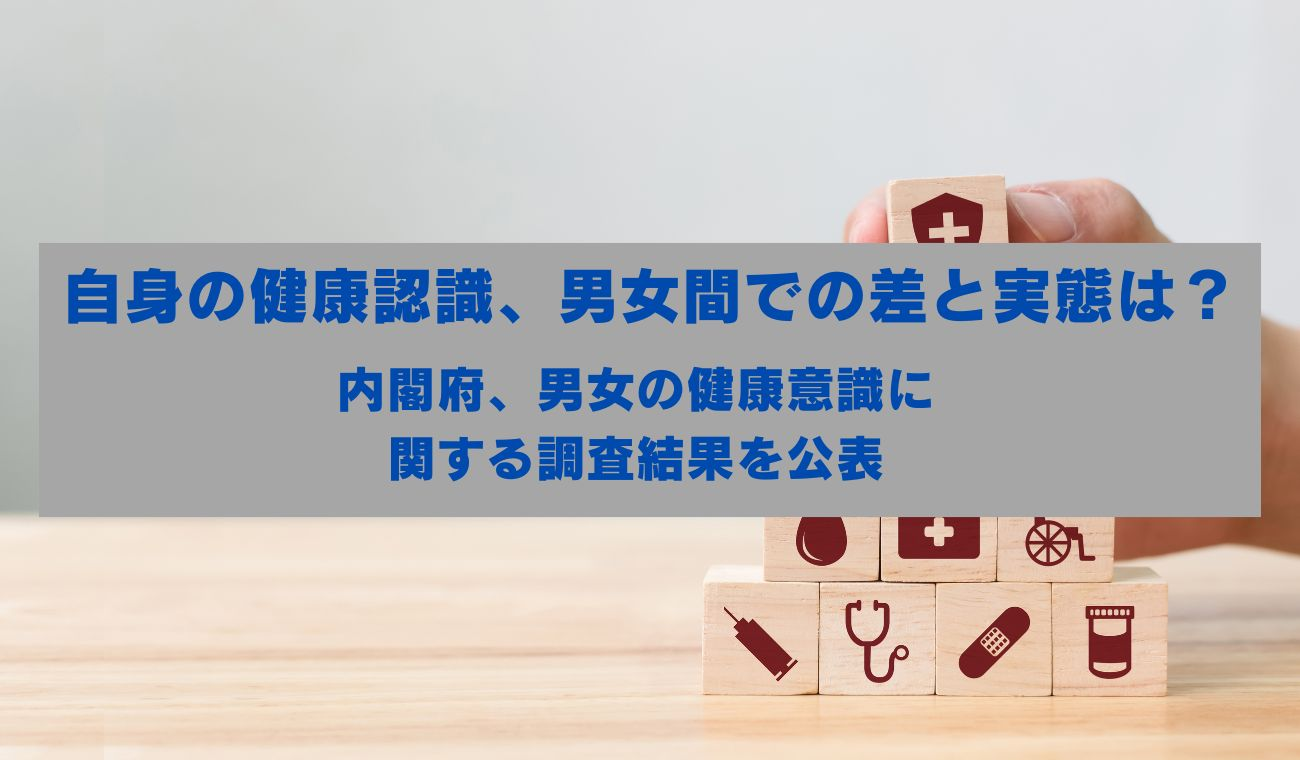
内閣府男女共同参画局は、健康に関する意識、職業生活において健康課題に関して抱える困難や悩みを明らかにすべく、国内在住の20歳以上70歳未満の男女を対象に、健康意識に関する調査を実施した。調査結果の概要について紹介する。
調査概要
調査方法:インターネット・モニターに対するアンケート調査
調査名:あなた自身に関する調査
調査対象:国内在住のインターネット・モニター(株式会社マーケティング・アプリケーションズの登録モニターで20歳以上70歳未満の男女)
調査期間:2023年12月12日~2023年12月25日
出典元:令和5年度 男女の健康意識に関する調査報告書(内閣府男女共同参画局)
調査実施の背景
内閣府は、企業が従業員の健康に投資することで従業員の心身の健康状態が改善すれば、企業の生産性の向上のみならず、組織の活性化による従業員の満足度向上にもつながると言われている点に注目。就業世代の活力向上により、その後の健康寿命が延伸され、公的医療・介護費用の削減にもつながるとしている。
また内閣府は、女性の社会での活躍においても健康課題への理解促進が重要となることを指摘。女性はキャリア形成において重要な時期である30代から40代にかけて、妊娠・出産などを含めた身体の大きな変化を迎えやすいこと、仕事での責任を負う40代後半から50代後半にかけて更年期を迎えることなどを挙げ、企業の取り組みが女性活躍の推進に欠かせないとの考えを示した。
そうした意識のもと、本調査では健康に関する意識、職業生活において健康課題に関して抱える困難や悩みについて、男女、年代別に把握。働きたいと考える全ての人が生き生きと働き続けるために必要なことを明らかにし、企業での健康経営を後押しすることで、今後の経済発展や男女共同参画推進に向けた材料とすることを目的に実施した。
自身の健康状態に対する認識に男女差

本調査によれば、女性より男性の方が「健康でないと思う(計)」とする割合が高い傾向がみられており、自身が「健康である」という認識は、女性の方が高いことが明らかに。また「健康でないと思う(計)」については、男性では20〜40代で2割、50〜60代では3割とその割合が高くなり、50〜60代女性(2割程度)との差が大きくなることもわかった。
一方で、体調が悪い日の頻度を見てみると、男性より女性の方が割合が高いという結果になっている。内閣府は「月に3〜4日程度以上(計)」体調が悪い割合において、特に男女差が大きいのは20〜40代だと報告。女性に関しては、若い年代ほど体調が悪い日の頻度が高い傾向がみられたという。
また、心理的なストレスの状況については、男女ともに全体の約1/4が「10点以上(要注意)」であり、40〜50代については男性の方がその割合が高いことを明らかにした。
気になる症状とその対処法

本調査では、1カ月の間で気になる症状について「特にない」の割合は、女性と比べて男性の方が高いことが報告されている。特に男女差の大きい症状としては「手足の冷え、むくみ、だるさ」「肩こり、関節痛(腰、膝、手足)」「頭痛、めまい、耳鳴り」が挙げられた。
また、最も気になる症状によるプレゼンティーイズム損失割合についても調査を実施。仕事においてはほとんどの症状で女性の方が高く、家事・育児・介護においては、ほとんどの症状で男性の方が高いことがわかった。
さらに、最も気になる症状への対処法として、男女ともに「十分に対処できていない(計)」が約55%となっていることも明らかに。具体的な対処法として挙げられたのはに「市販の薬や漢方、サプリメントを飲む」が男女ともに最多であったという。
検診等の受診率については女性の方がやや低く(男性:71.7%/女性:67.3%)、30代においてその差が最も大きくなり、男女間で9%の差がみられている。
仕事と健康課題の関係性

健康課題による仕事への影響・支障の有無については、男女ともに「人間関係がスムーズにいかなくなった(男性:15.6%/女性:16.0%)」が最多に。また「配置・部署が変わった」「休職した(現在も休職中)」については、男女ともに若い年代ほど高い傾向にあることもわかっている。
働く上で健康課題に関しての困りごととしては「ストレスなどメンタルに関わる悩みが言い出しにくい」が、20〜50代の男女に共通して最も多く挙げられている。60代になると「自分が休もうとしても代わりに任せられる人がいない」が最多となった。女性に関しては「月経(生理)の不調など女性ならではの悩みが言い出しにくい」も多く挙げられているという。
こうした働く上での健康課題や困りごとについての改善策としては、男女ともに「待遇・給与の改善」「仕事の量・仕事時間の改善」が上位に挙げられた。「女性の健康問題への理解」「育児・介護との両立支援」については女性の方が高い傾向がみられている。また、男性における「男性の健康問題への理解(6.6%)」と女性における「女性の健康問題への理解(16.2%)」についても、男女間の差が明確であった。
まとめ
本調査では、女性の方が自身を健康だと認識している一方で、気になる症状が「特にない」とする割合は男性の方が高いことが明らかに。また、プレゼンティーイズム損失割合についても、仕事においては女性の方が高い傾向にあった。月経や更年期など、女性特有の健康課題も背景にあると推察される。
企業として健康経営に取り組む上で、本調査結果は重要な参考資料となるのではないだろうか。誰もが活躍できる組織づくりは、人材不足が大きな課題となっている今、欠かせない取り組みのひとつである。健康課題について、内容によっては言い出しにくいと感じている人がいることも明らかになっている。従業員が安心して健康に関する相談ができる体制を整えることも、ぜひ検討していただきたい。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする