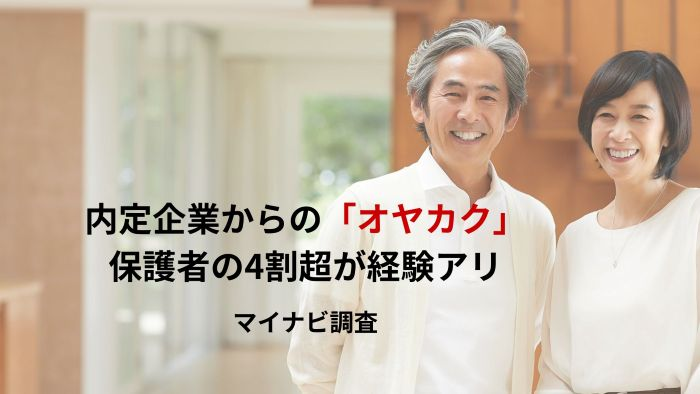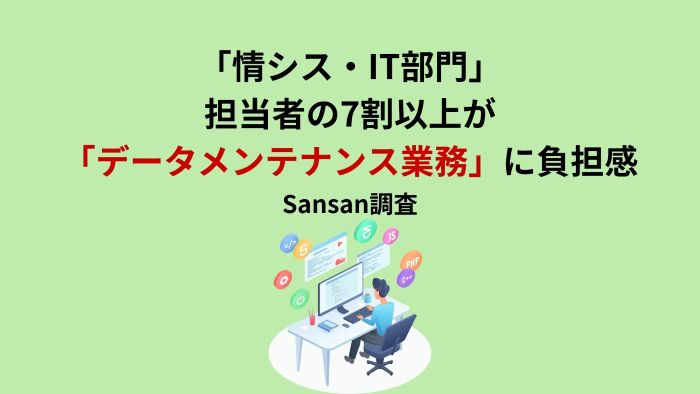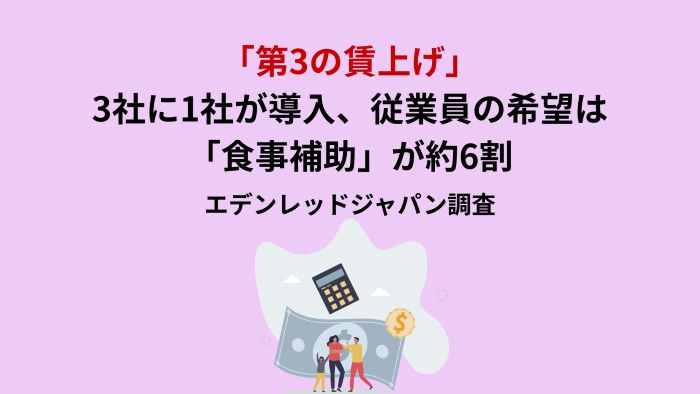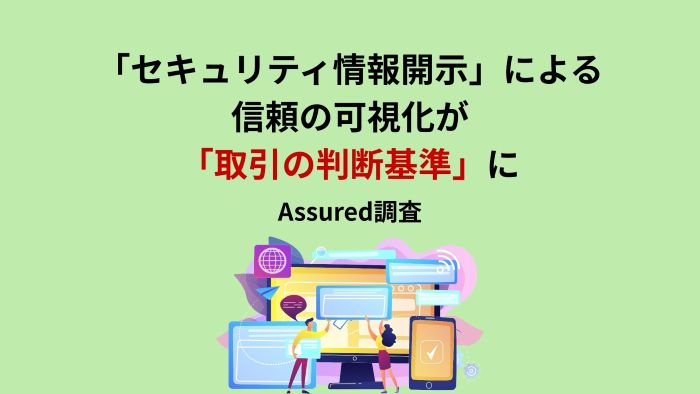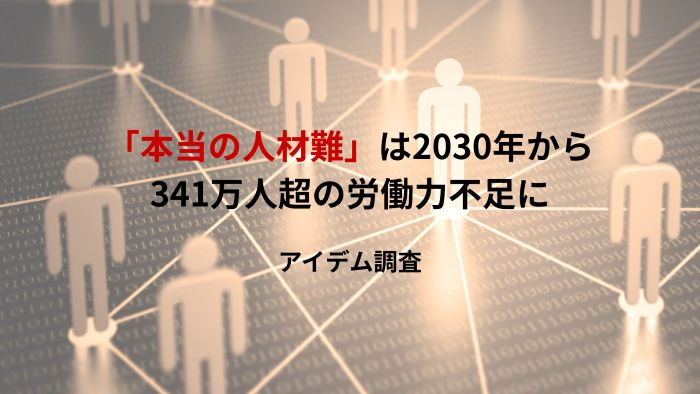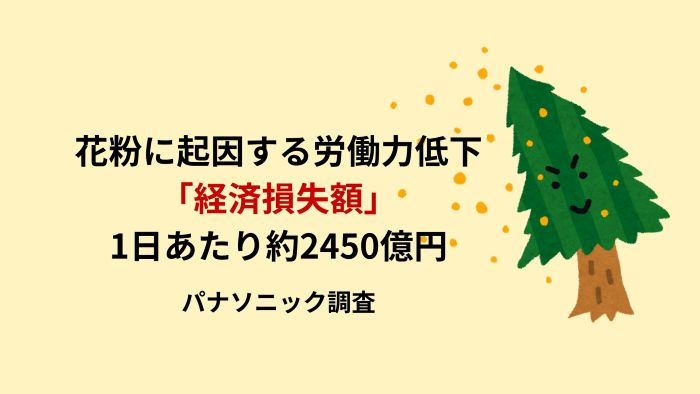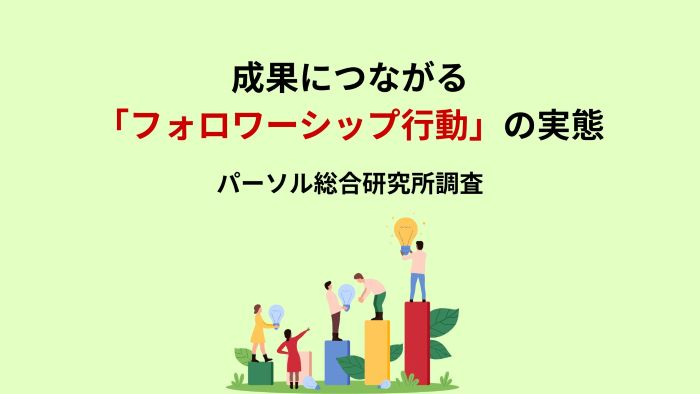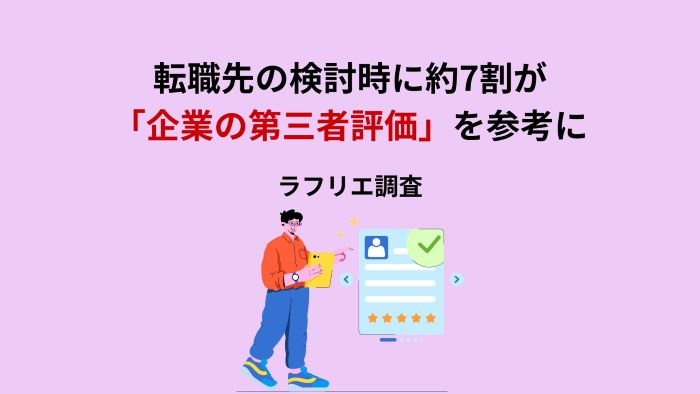年上部下が増加傾向、年下上司への相談で幸福度が低下? Smart相談室調査
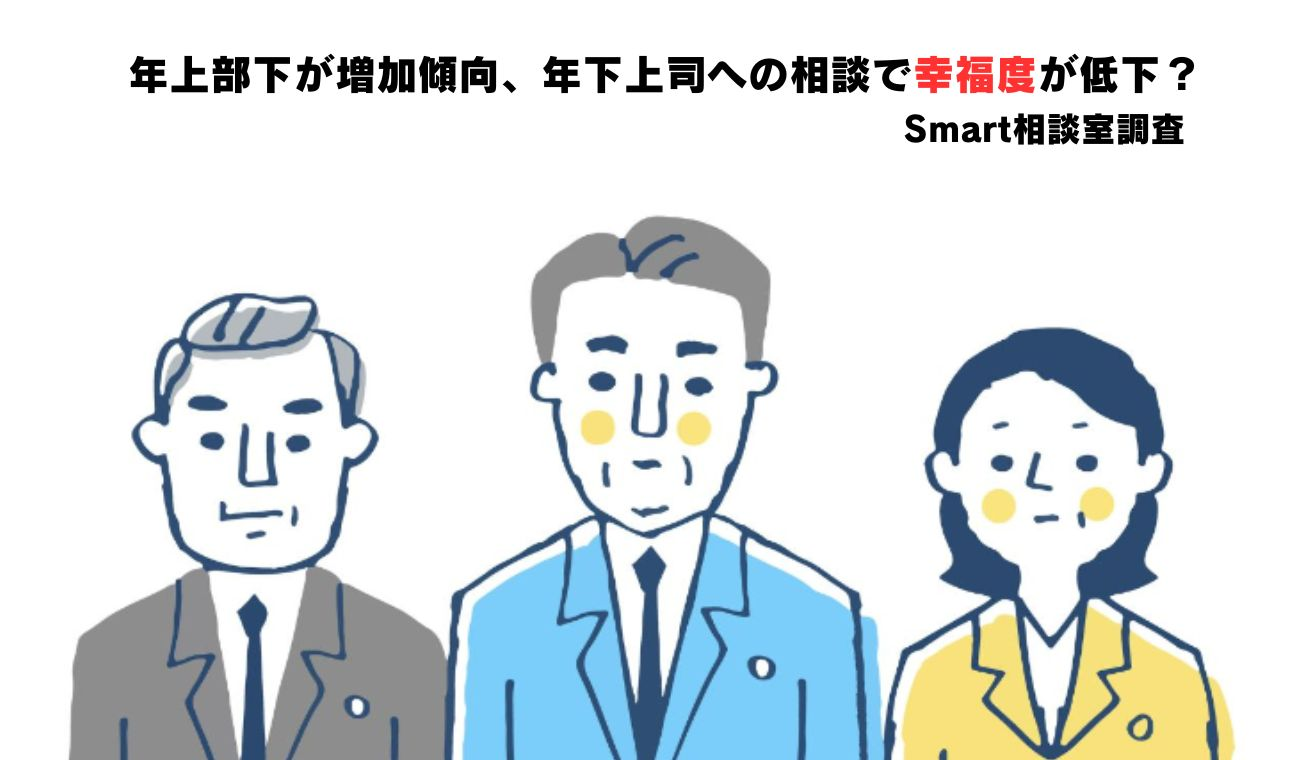
株式会社Smart相談室では、法人向けオンライン対人支援サービス「Smart相談室(スマートそうだんしつ)」を提供している。近年では年功序列から成果主義へのシフトによって、年下上司・年上部下が増加傾向にあり、年齢と立場のギャップによって、相手との付き合い方に悩みを抱えるケースもみられるという。そこで同社は、年下上司・年上部下が抱える課題やその解決方法についてのアドバイスを公開した。
直属の上司が年下は21.6% 今後も増加すると予想

同社は「日本の人事部」による「人事白書調査レポート2023(※1)」で「年功主義」が減少傾向(2022年比2.9ポイント減)にあると報告されたことに触れ、評価・報酬制度のあり方が成果主義」を軸として「能力主義」「職務主義」へと移行しつつあると解説。
さらに、2023年に「サイボウズ チームワーク総研」が実施した調査(※2)においては、30-50代会社員のうち21.6%が「直属の上司が年下」と回答しており、従業員数が2000人以上の企業ではその割合は30%近いことも明らかにされていた。
同社は、年功序列の衰退に伴って年下上司・年上部下が増えている実態に加えて、2025年4月からすべての企業で「従業員の65歳までの雇用確保」が義務化されることによる「定年延⻑」や「再雇用制度」の適用も影響し、今後さらに年下上司が増加すると予想している。
※1 出典元:評価・報酬は能力主義、成果主義、職務主義が約7割と主流。年功主義は2022年から2.9ポイント減少(日本の人事部)
※2 出典元:「年上の部下」へのマネジメント、必要なのは「敬語」よりも「傾聴」と「適切な関与」(サイボウズ チームワーク総研)
年下上司への相談は年上部下の幸福度低下に

同社は続いて、2021年の日経BPコンサルティングによる「働き方に関する意識調査(※3)」から、シニア人材の抱える課題や悩みに関する結果を抜粋。「給与が業務の内容や業務量に見合わないと感じる(41.8%)」「モチベーションが上がらない、下がった(28.4%)」との回答が多かったことを紹介した。
また、 2021年にロバート・ウォルターズ・ジャパンが実施したアンケート(※4)では、年下上司に対して「働きにくさを感じる理由」として「年齢故の経験値・知識不足を感じる(53%)」との回答が目立っている。
さらに、2023年のパーソル総合研究所による調査(※5)では、年下上司に「仕事上の悩みや不満を聞いてもらう」ことに、労働の幸福感を低下させる効果があることがわかったという。
※3 出典元:~人生100年時代、働く世代の意識ギャップ~ 再雇用世代&若い世代 現場のホンネ(日経BPコンサルティング)
※4 出典元:グローバル人材「年上部下」と「年下上司」の実態は (ロバート・ウォルターズ)
※5 出典元:働く10,000人の成⻑実態調査2023 シニア就業者の意識・行動の変化と活躍促進のヒント(パーソル総合研究所)
年下上司と年上部下の関係性を向上するポイントは?
こうした調査結果を受けて同社は今回、年下上司と年上部下の関係性を向上する方法についてアドバイスを公開した。
まず「年下上司が部下との衝突に悩んでいる場合」については「フォロワーシップカルチャーの醸成」が必要だと提言。「多様な背景を持つ人たちが共通の目標達成のために自律的に考え、行動すること」によって、組織力が高まるとして、リーダーはフォロワーの意見を受け入れた上で、最終的な意思決定を下すよう促した。
次に「年上部下が上司との考え方のギャップに悩んでいる場合」については「しなやかなマインドセット」を心がけるよう提案。これについては容易にできることではないとして、外部のコーチングなどを取り入れて「アンラーニング・捉え直し」のスキルを身につけるよう促した。
まとめ
同社は対人関係によるストレスが離職の要因となりかねないとして、年下上司と年上部下の関係性向上への取り組みが重要であることを伝えている。年齢差によって周囲への相談のハードルが高くなる可能性もあることから、第三者機関の相談窓口やコーチングの導入が有効だとの見解を示した。
同社が参照していたパーソル総合研究所の調査(※5)では「年下上司のもとで働くことに抵抗はない」とするシニアの割合が年々微増傾向にあることもわかっている。互いに尊重し合えれば、良好な関係を構築することは十分可能だろう。
今後さらに増加することが予想されている年下上司と年下部下。関係性向上のポイントを押さえて、より強い組織づくりへとつなげていただきたい。
※5 出典元:働く10,000人の成⻑実態調査2023 シニア就業者の意識・行動の変化と活躍促進のヒント(パーソル総合研究所)

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする