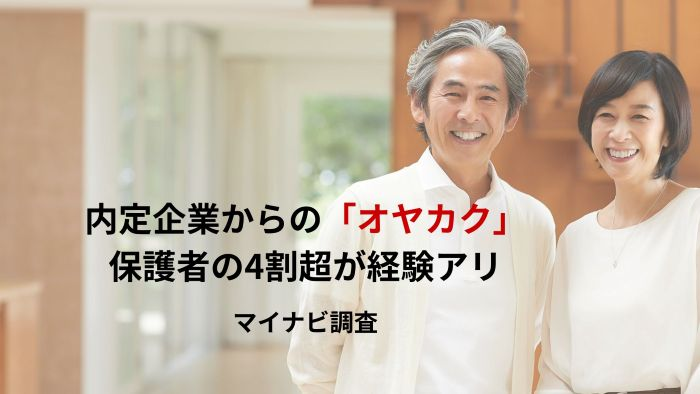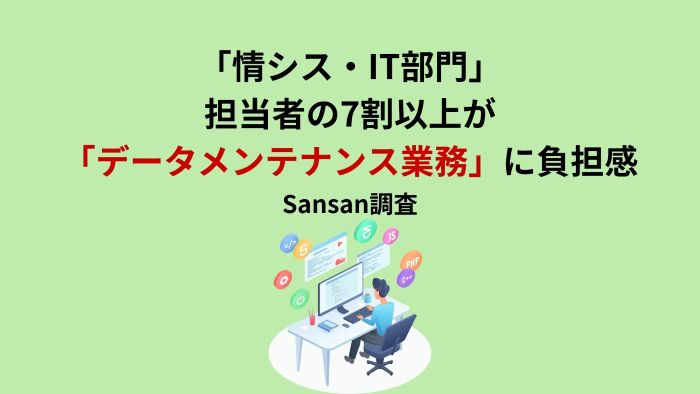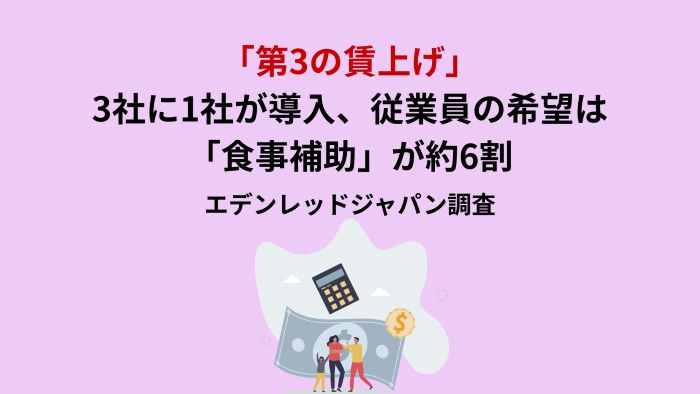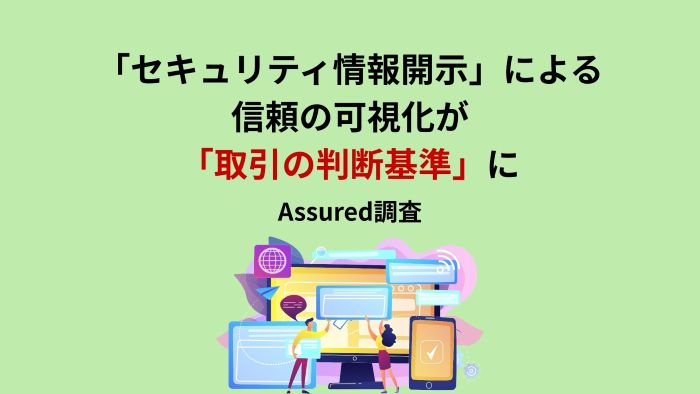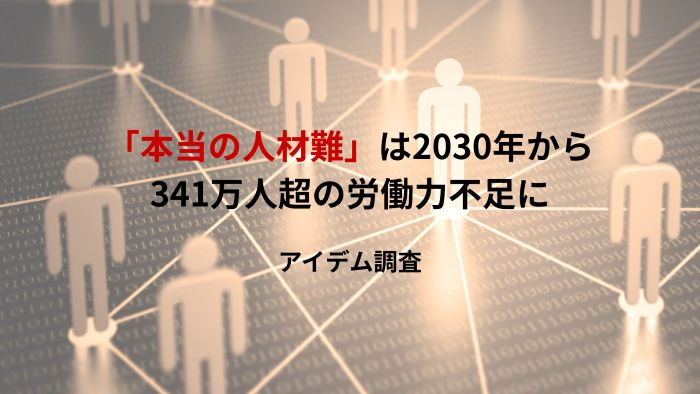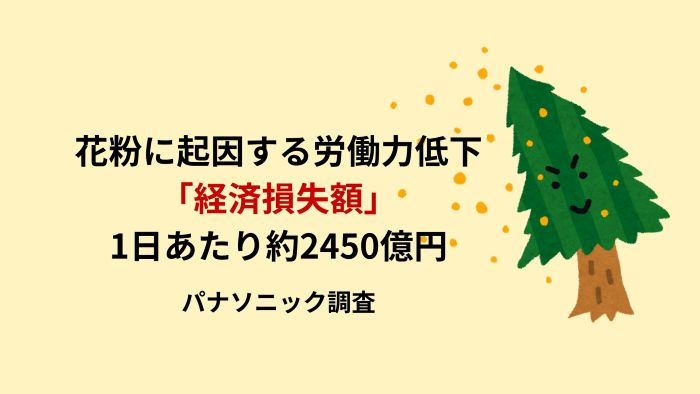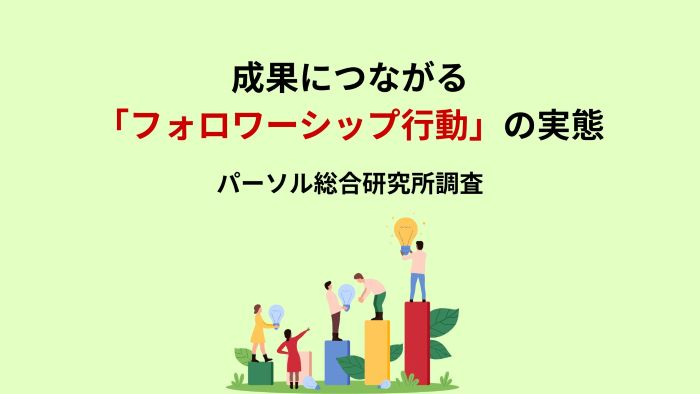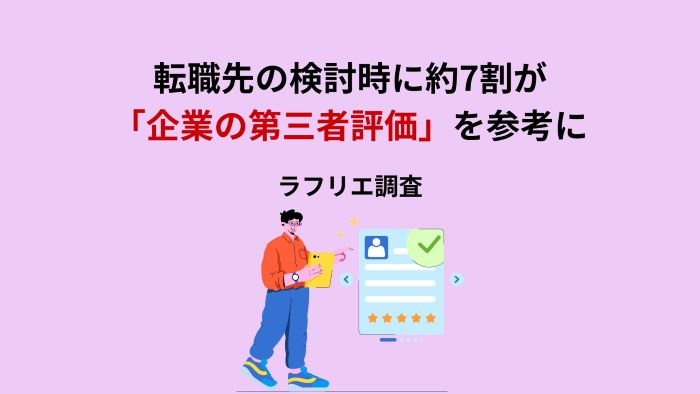歴史的賃上げ実施も7割以上が家計負担は軽減せず 賃上げ実態調査2025

福利厚生の食事補助サービス「チケットレストラン」を提供する株式会社エデンレッドジャパン、従業員の様々な生活出費を補助する「freee福利厚生 ベネフィットサービス」を提供するフリー株式会社、家事代行サービスで従業員のライフステージをサポートする株式会社ベアーズの3社が展開する「#第3の賃上げアクション」は、2025年の賃上げ機運が高まる中、経営層・人事担当者と一般企業の従業員を対象に、2024年・2025年の賃上げと「従業員の手取り額を実質的にアップする福利厚生(=第3の賃上げ)」に関する動向を調査。賃上げが従業員の暮らしにどのような影響を与えているのか、その実態を明らかにした。
調査概要
調査名称: 賃上げ実態調査2025
調査主体: #第3の賃上げアクション
調査方法: WEBアンケート方式
調査期間: 2024年12月11日~2024年12月12日
調査対象および有効回答数: ①役員含む経営者・人事担当者 400名/②経営者・役員除く一般社員 400名
出典元:#第3の賃上げアクション『賃上げ実態調査2025』
2024年の生活実態と2025年の賃上げ意向

本調査ではまず一般社員を対象に、歴史的高水準となった2024年の賃上げは家計にどのような影響を与えたのかを明らかにした。2024年に行われた賃上げにより手取りが増えた実感があるか尋ねる項目では、60.9%が手取りが増えた実感は「あまりない/ほとんどない」と回答したという。また、賃上げが家計負担の軽減につながったかどうか尋ねる項目においても71.5%が「あまりそう思わない/ほとんどそう思わない」と回答したことが報告されている。
次に本調査では、昨今の物価高・値上げの影響を受け、2024年は前年より家計の負担が増えたかと質問。80.8%が「さらに負担が増えたと感じる」と回答し、節約意識の高まりを感じる人が93.3%にも及んでいることが判明した。
続いて本調査では、経営層・人事担当者を対象に賃上げ意向について質問している。2025年の賃上げ実施予定については、59.8%が「実施予定/前向き検討中」と回答したという。また、賃上げを実施する理由としては「従業員の生活支援(59.6%)」「物価上昇の考慮(57.4%)」「人材確保・定着(50.0%)」が上位に挙げられている。
第3の賃上げへの期待は?導入企業の約8割が満足

次に本調査では「従業員の手取り額が実質的にアップする福利厚生(第3の賃上げ)」について質問。導入企業ではその満足度について、75.2%が「非常に満足/やや満足」と回答したという。特に中小企業は、89.5%と9割近くに達しており、高い評価を得ているようだ。さらに経営者・人事担当者が感じている導入効果としては「人材確保・採用時のアピール(68.8%)」が挙げられたという。
高い満足度と効果実感を得られている第3の賃上げだが、認知度については42.6%と半数以下であったことが報告された。しかし一方では、未導入の経営層・人事担当者は66.9%が「非常に興味がある/やや興味がある」と回答し、一般社員の85.3%が「非常に導入してほしい/やや導入してほしい」と回答しており、興味関心の高さもうかがえる。
まとめ
歴史的な賃上げが行われた2024年だが、生活実態の改善を感じた人は少ないようだ。企業は賃上げの実施と並行して、生活支援の取り組みを充実させていく必要があるのではないだろうか。
本調査は“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を目指す「#第3の賃上げアクション」プロジェクトによって実施されたもの。本プロジェクトについて興味を抱く人は多く、導入企業では高い満足度も示された。今後さらに認知が進めば、導入企業はますます増加していくことだろう。
家計負担の軽減を企業としていかに支援し、従業員の生活の質を向上させていくか、改めて検討する機会としていただきたい。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする