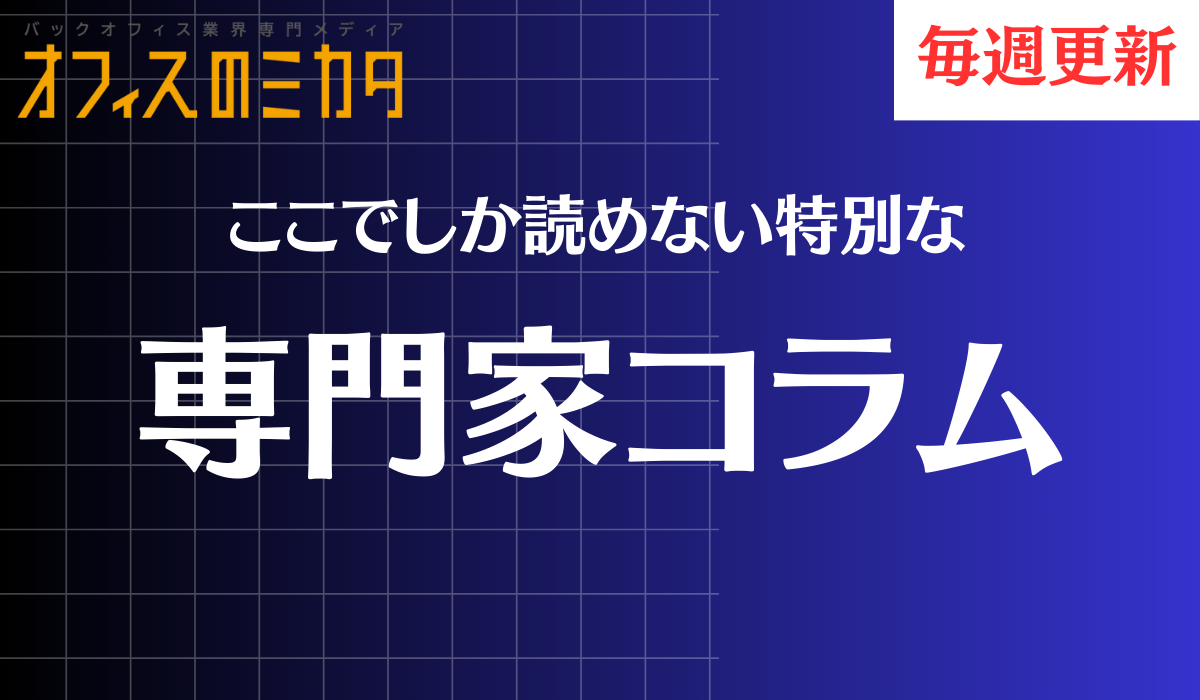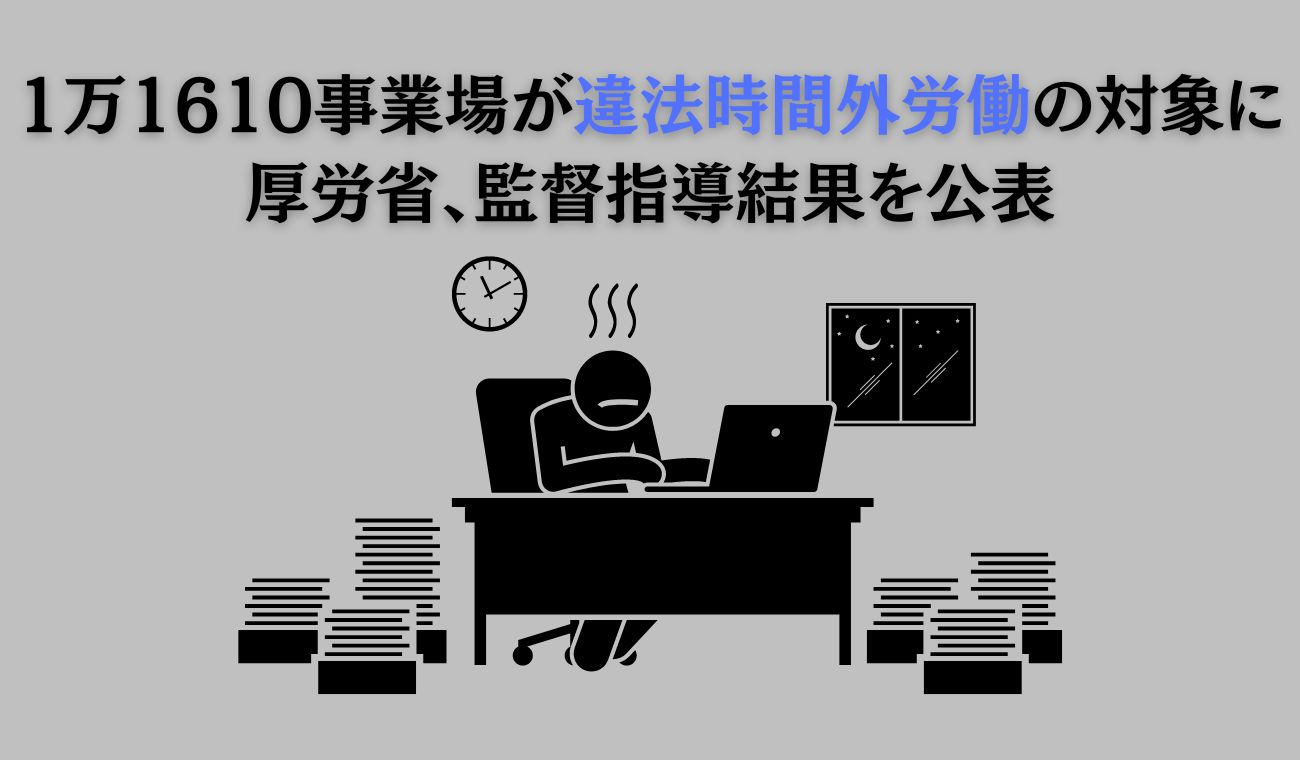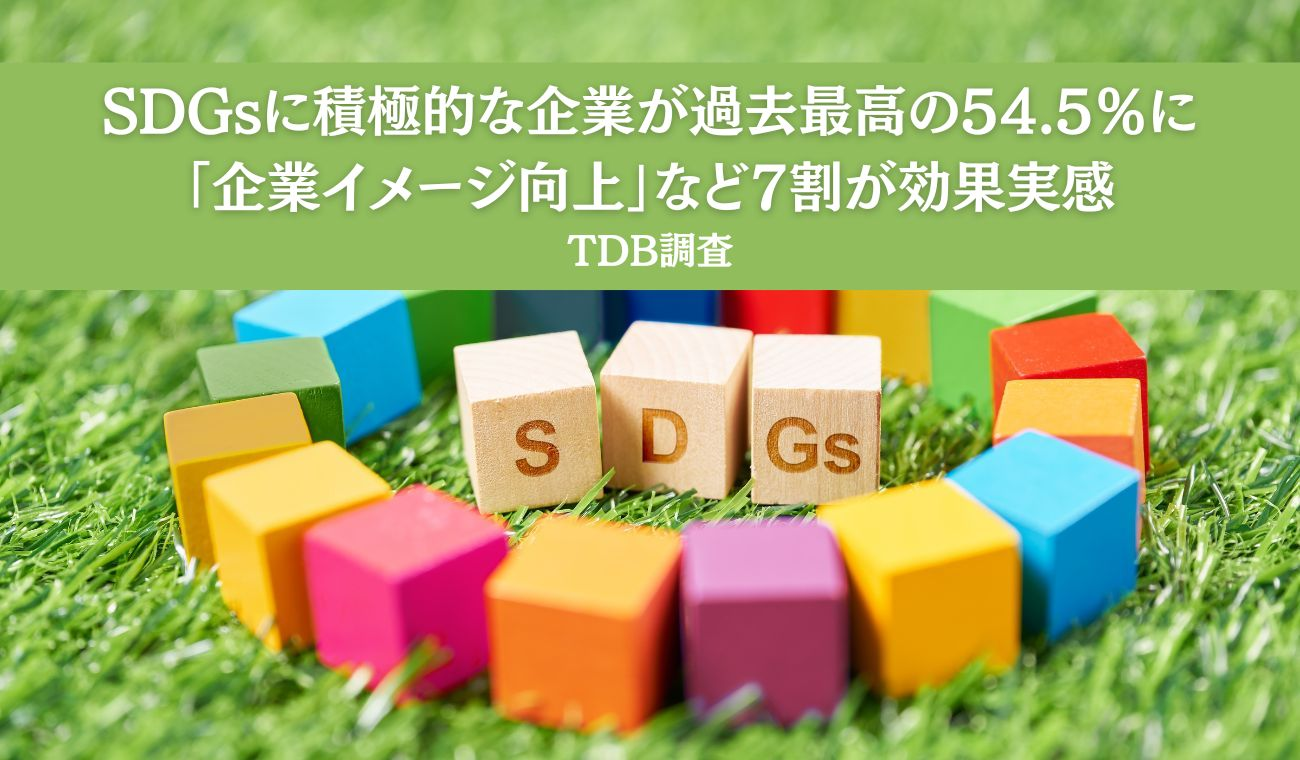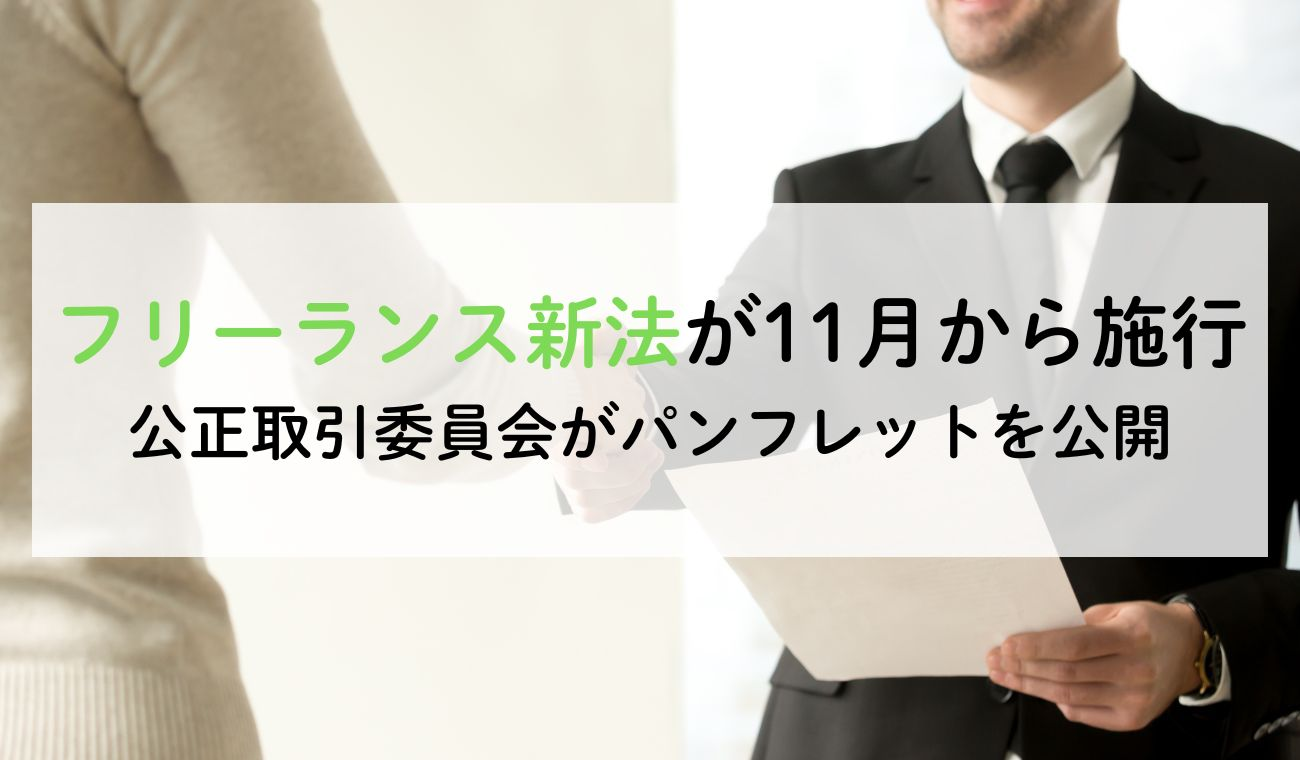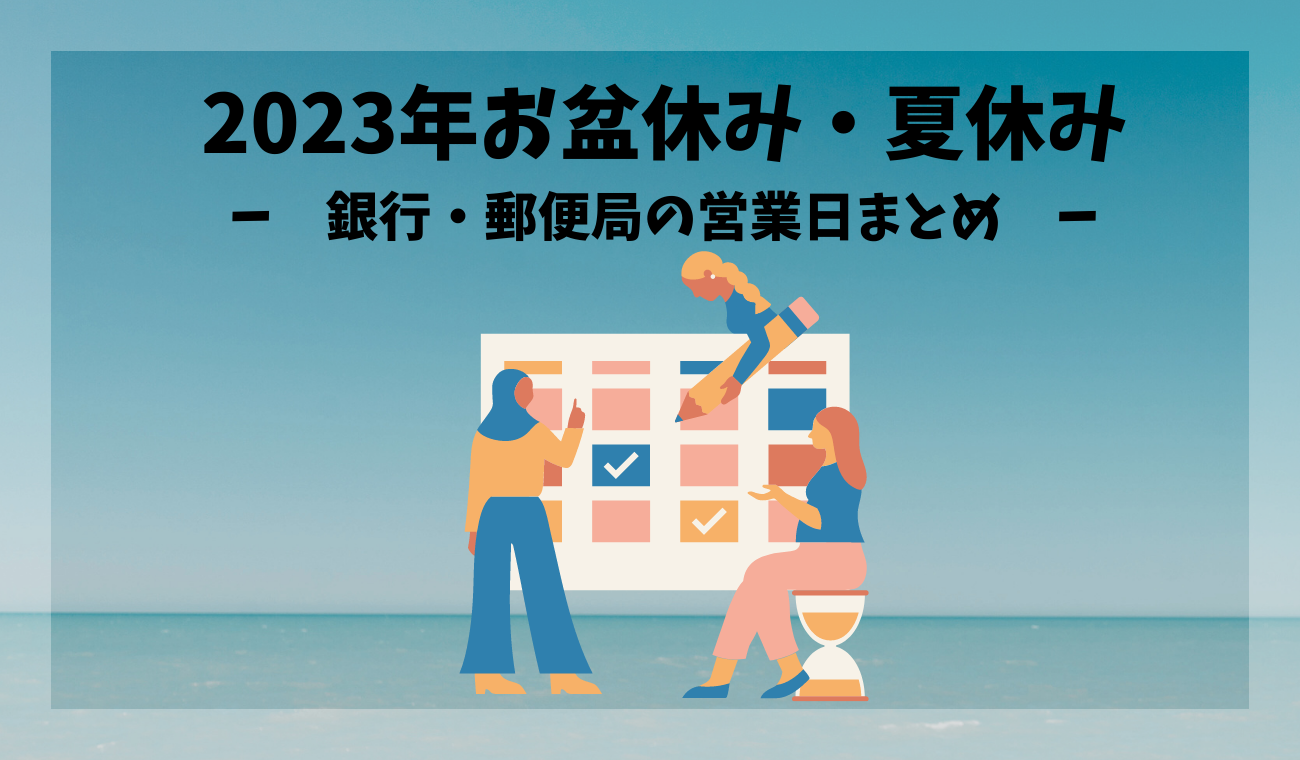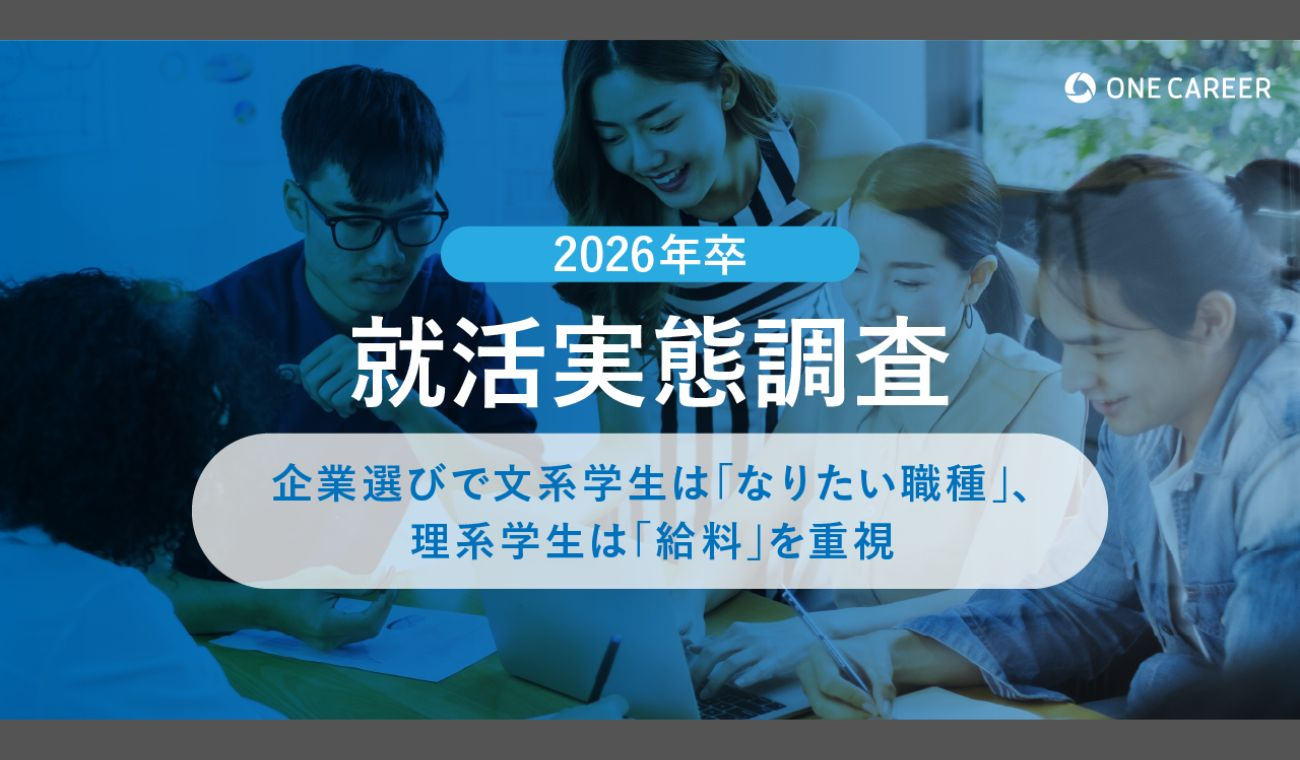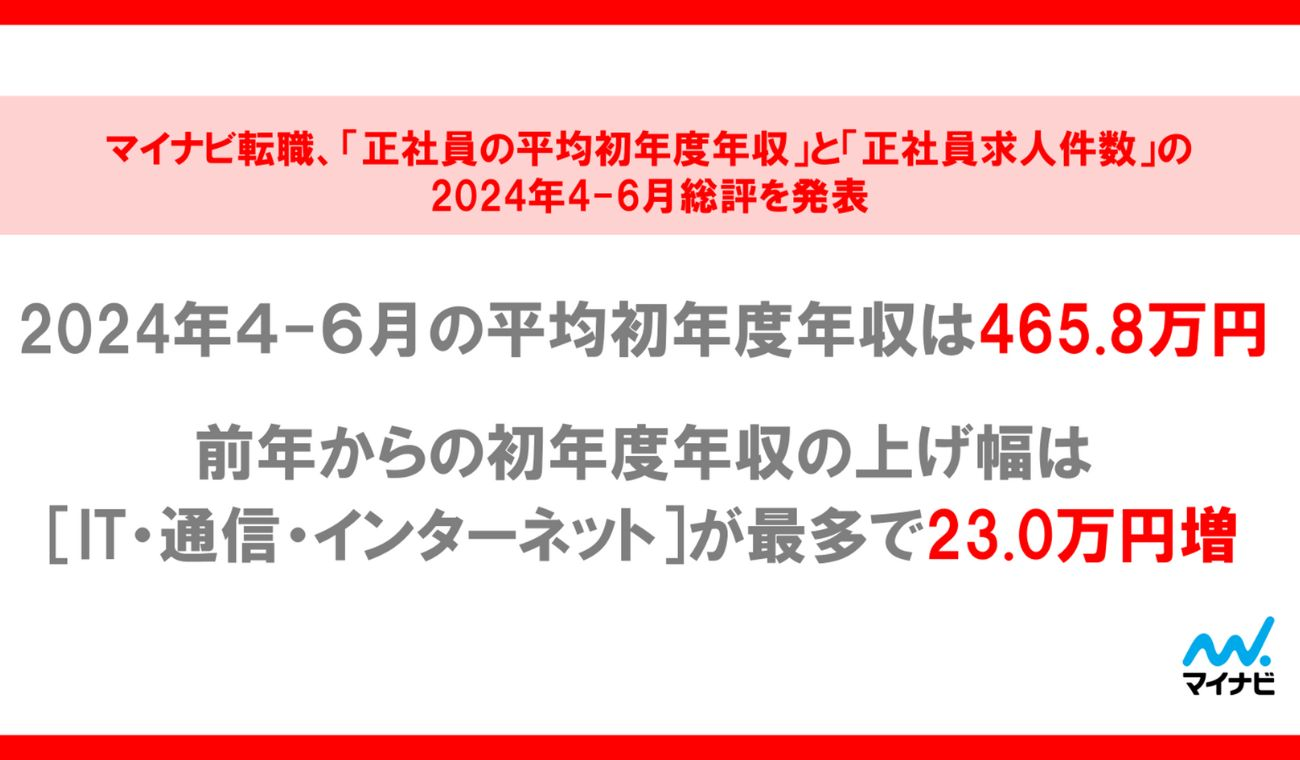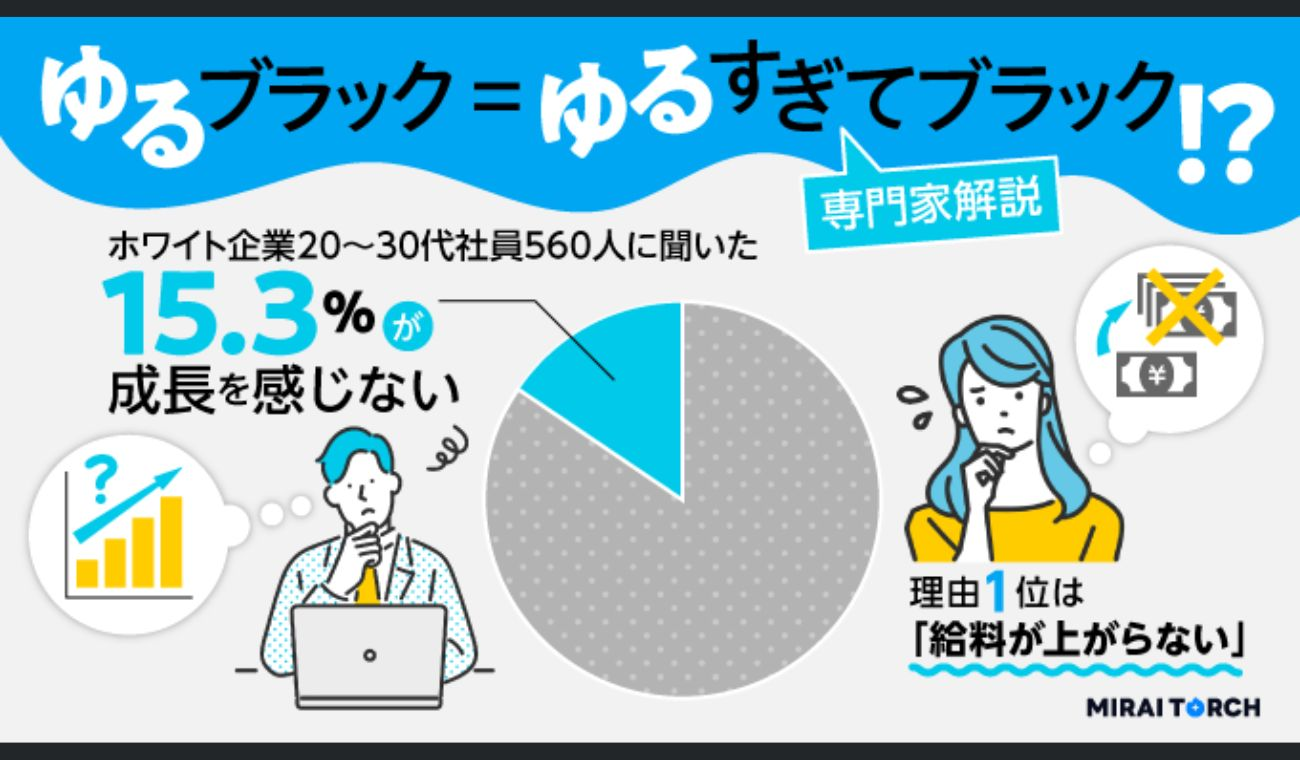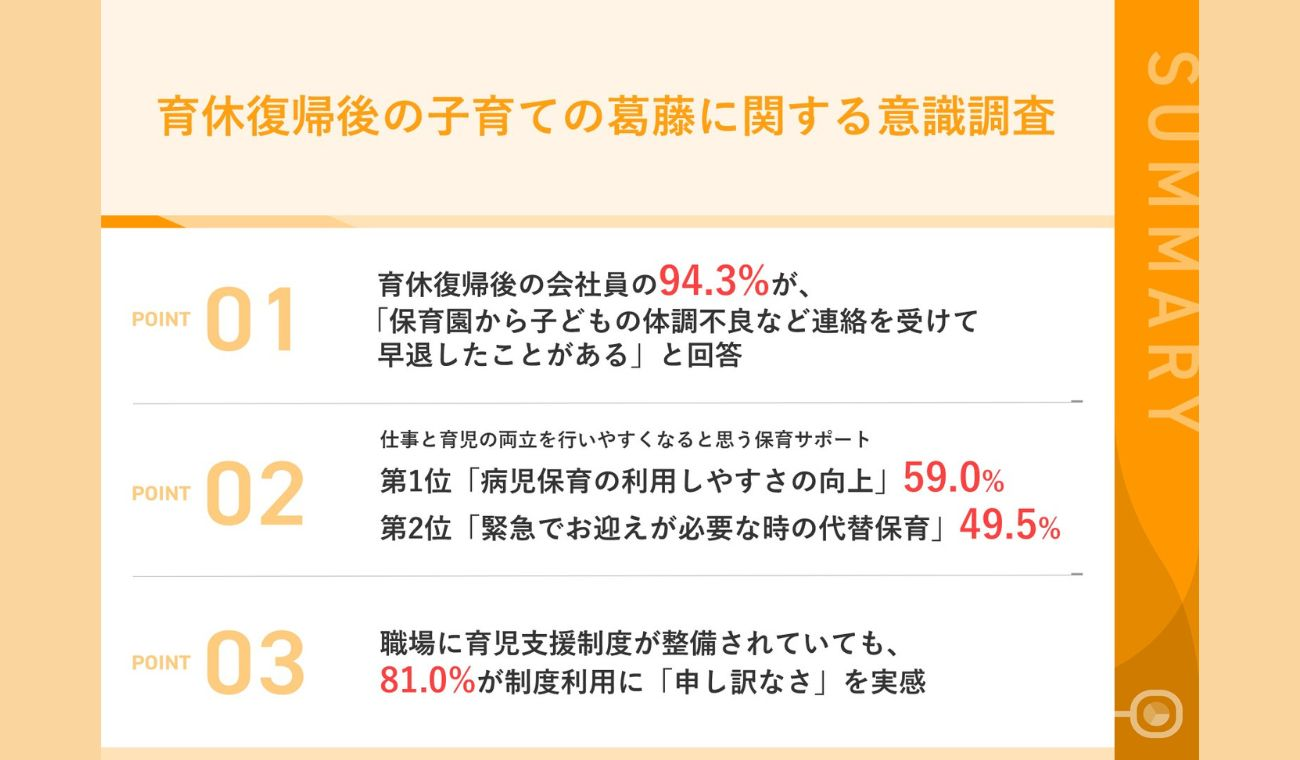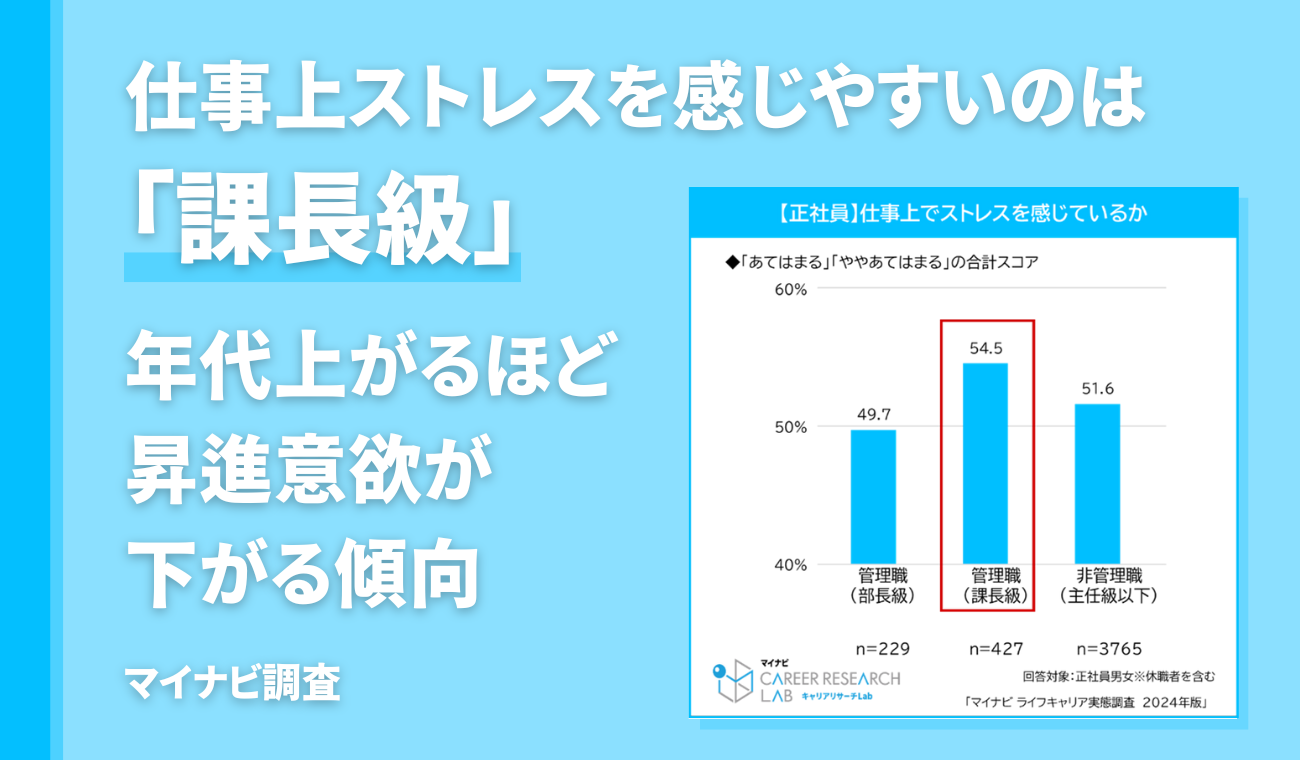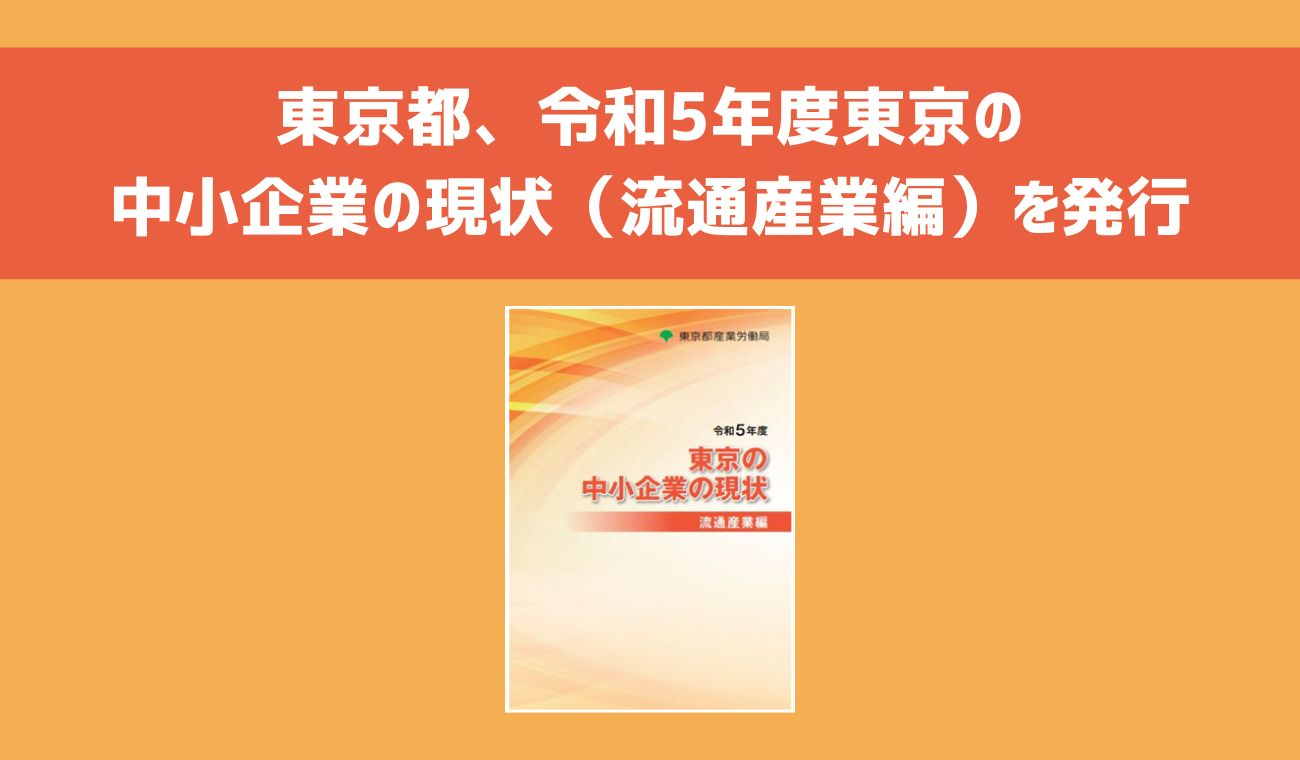郵便料金値上げによる請求業務への影響は?7割以上の企業が対策未定の実態

フリー株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔)は企業の請求業務に関わる経理・総務担当を対象に、請求業務の現状と郵便料金値上げへの対策に関するアンケート調査を実施。2024年3月7日に、総務省の情報通信行政・郵政行政審議会が、25グラム以下の定形の封書に定める郵便料金の上限額を、84円から110円に26円引き上げる方針を示したことを受けて実施されたもの。
調査概要
調査期間:2024年4月9日〜4月12日
調査方法:Webアンケート方式
調査対象:従業員数11名〜1000名の企業で請求業務に関わる経理・総務担当社員
有効回答:1000件(本調査)
割付:最も多い割合多い請求書発行形態ごとに割付を実施
紙で印刷・封入をして、郵送している(以降、「手作業での郵送」):500
クラウド請求ソフトで送付している:(以降「クラウド請求ソフト」):250
電子ファイルを、メールで取引先ごとに送っている(以降「メール」):250
出典元:freee、請求業務の現状と郵便料金値上げへの対策に関する調査を実施(フリー株式会社)
約半数が電子化に着手も発行する請求書の半分以上を紙で印刷・郵送する企業が3割超

本調査によると、最も多い請求書の送付方法は「手作業での郵送(紙で印刷・封入をして、郵送している)」が46.9%、クラウド請求書が26.3%、メールが25.6%となっており、約半数が電子化に着手していることがわかる。
しかしながら、メール、クラウド請求書経由の発行が主な企業においても、3割超は51%以上の請求書を紙で発行していることが明らかになった。
請求書の送付方法を電子送付に切り替えることへの意向については、クラウド請求書を導入している企業が最も高く、紙の請求書を電子送付に変えていきたいという意向が8割を超えるという。一方、手作業での郵送が主な企業については「どちらでもない」以下の回答が4割を超えており、請求書の電子化に消極的なことがうかがえる結果となった。
郵便料金値上げの認知度は全体で8割超 値上げの詳細を把握しない企業も

本調査では、郵便料金の値上げについての認知度について、手作業での郵送が主である企業は8割を下回ることが明らかになっている。加えてメール送付、手作業での郵送については「詳細までは知らない」という回答が5割を超え、郵便料金の値上げの内容理解までは至っていない様子がうかがえた。
また、郵便料金値上げへの対策状況はメインの発送方法ごとに異なっており、クラウド請求書が主な請求書発行方法である企業では対策中と対策予定が7割を超えるものの、手作業での郵送の場合は3割を割り込んだ。手作業での郵送の場合、対策未定と対策予定なしで7割以上にのぼるという。
電子化の推進は「取引先」の理解がキーに

本調査によると、請求書の電子化のボトルネックは総じて「取引先」に関連するものが高く、特にクラウド請求書が主な請求書発行方法である企業においては「取引先からの理解・合意」「取引先の要望ごとの対応」の割合は5割を超えることが明らかになっている。また「個別請求書フォーマットの対応」についても、クラウド請求書、メールともに負担としてあげる割合が多いという。手作業での郵送については、他の手段をメインとする層との大きな差はないものの「長年続けた習慣を変えること」の数字が高いことから、現状を維持したいとの意向が見受けられた。
まとめ
本調査により、郵便料金値上げの認知は広まっているものの、その詳細を把握していない企業も少なくなく、紙での発行をメインとする企業では7割超が対策を実施しない(未定含む)との意向を示していることが明らかになった。
電子化を推進する上での障壁として「取引先」に関連するものが多く挙げられており、同社は特に「個別フォーマットへの対応」については「請求書のフォーマット(文字の大きさ・色・項目の配置)の変更を行う際の取引先との調整コストが表れている」と指摘した。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする