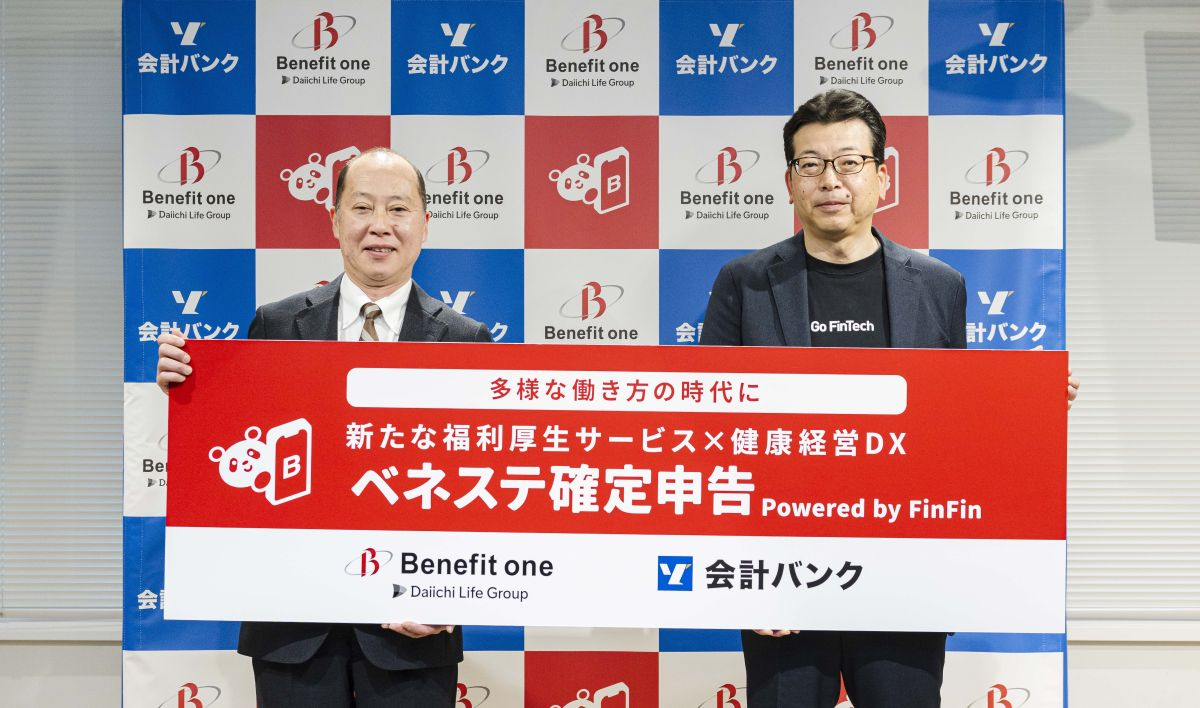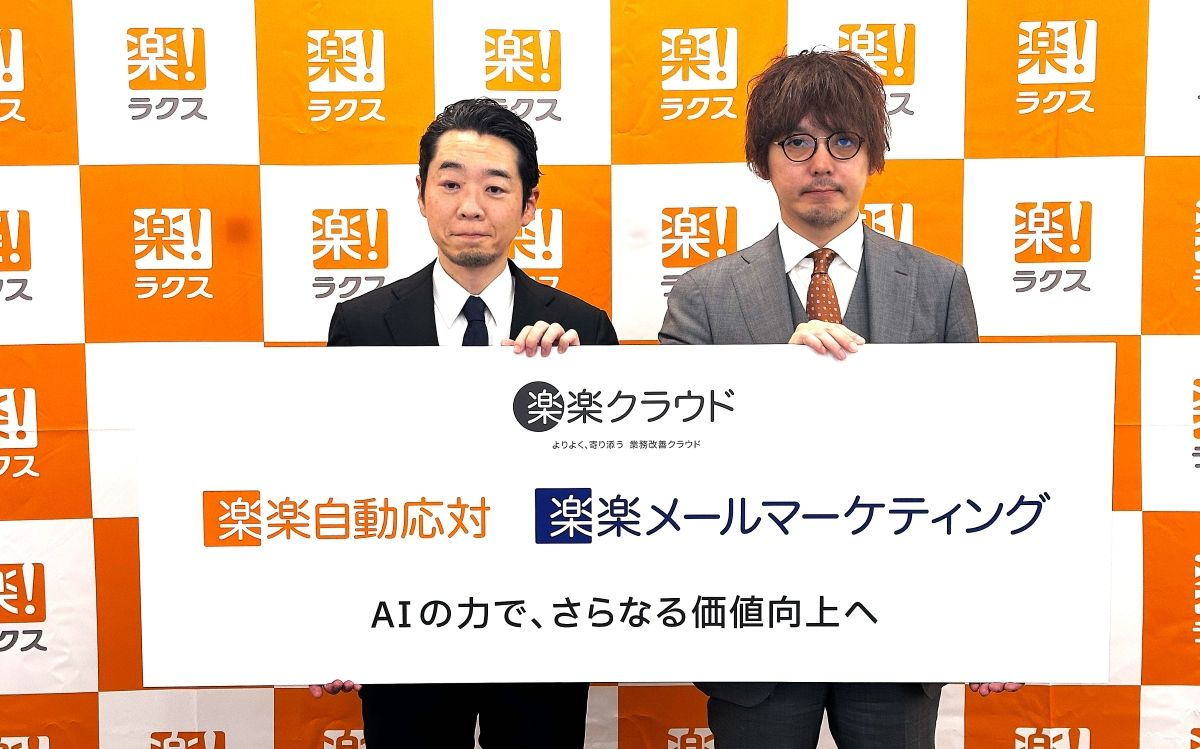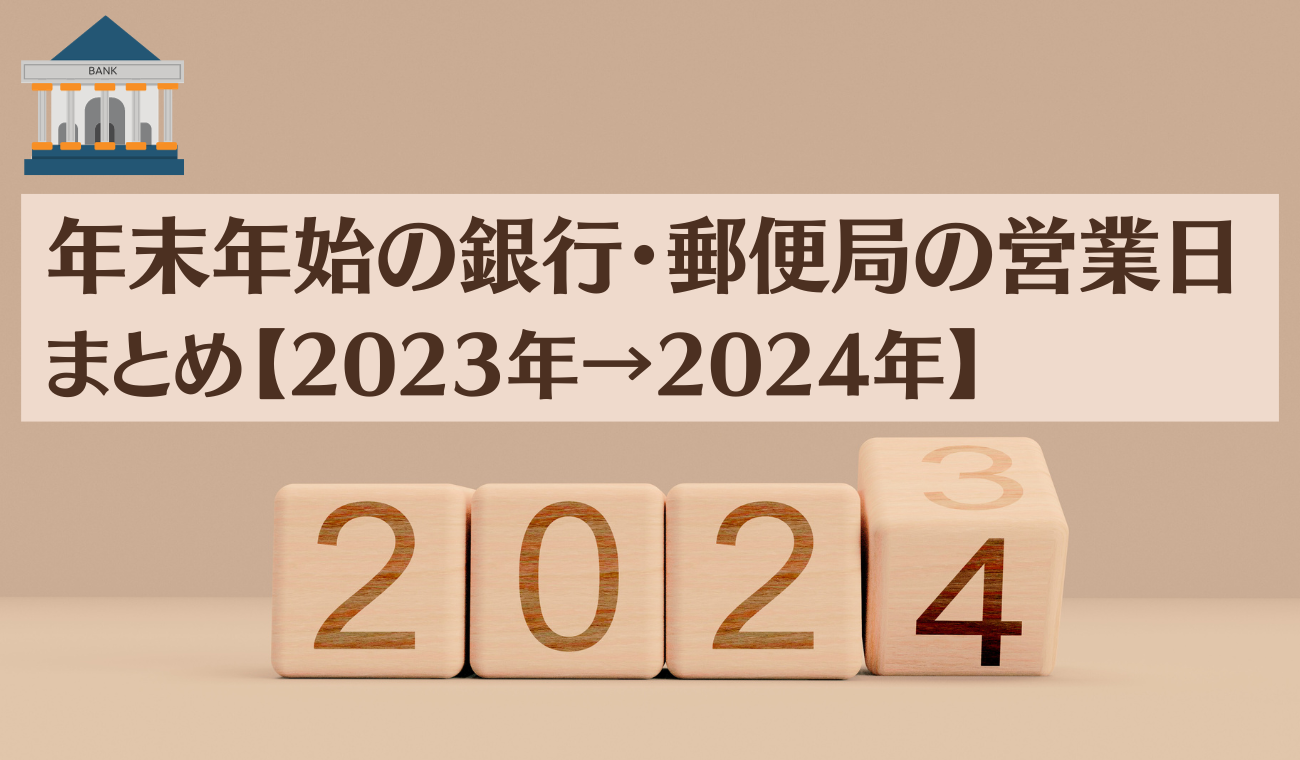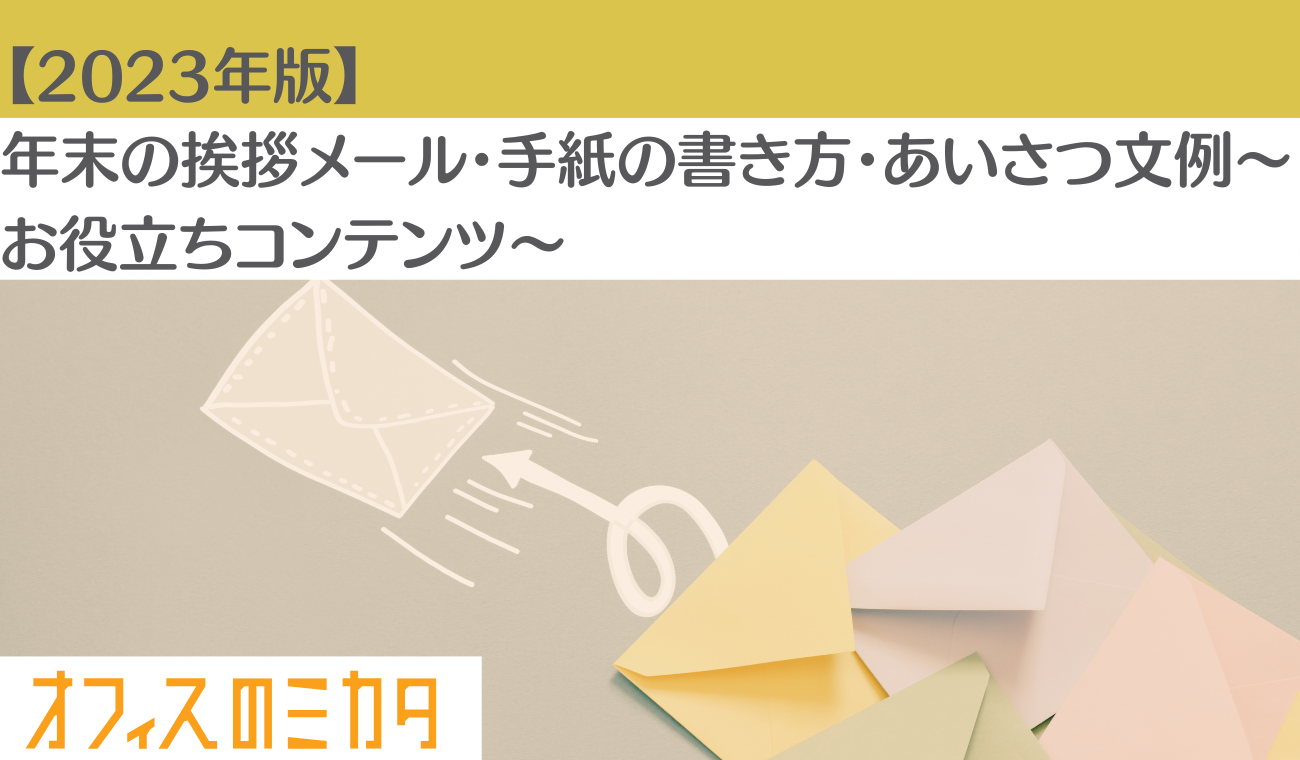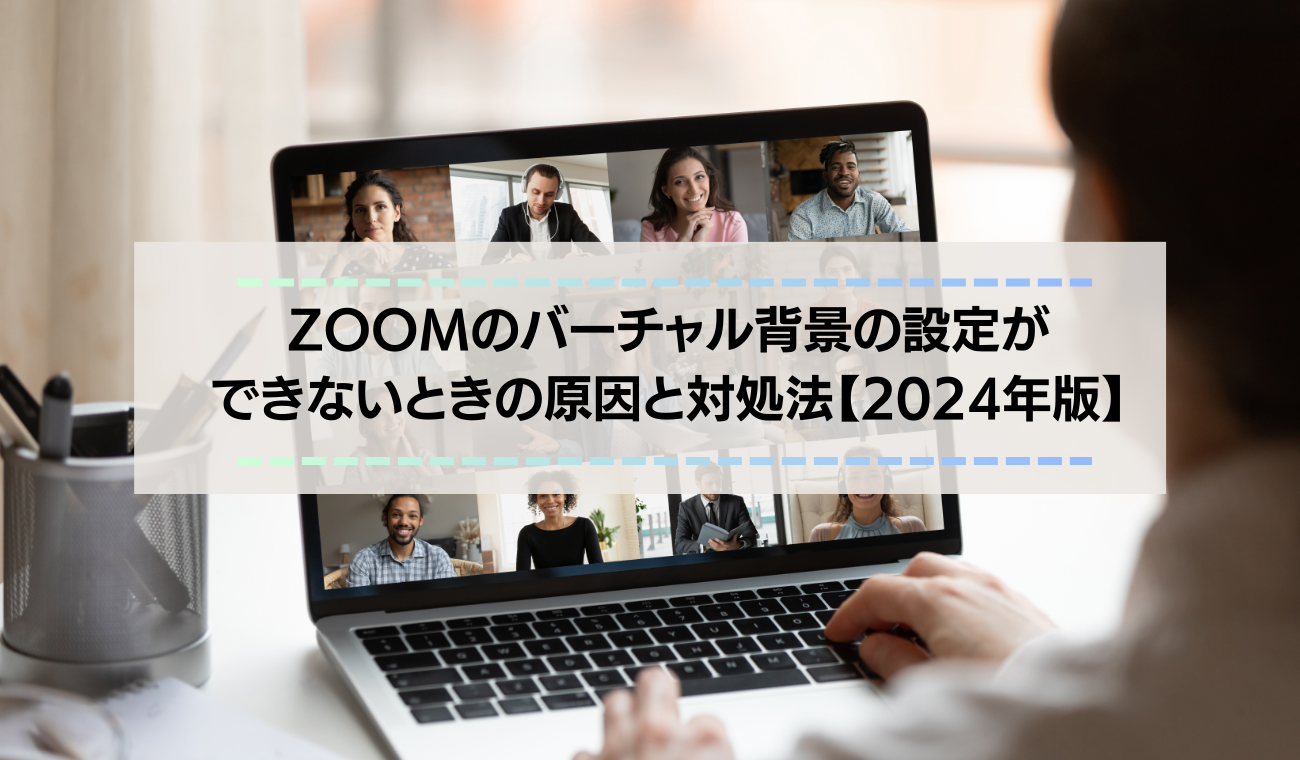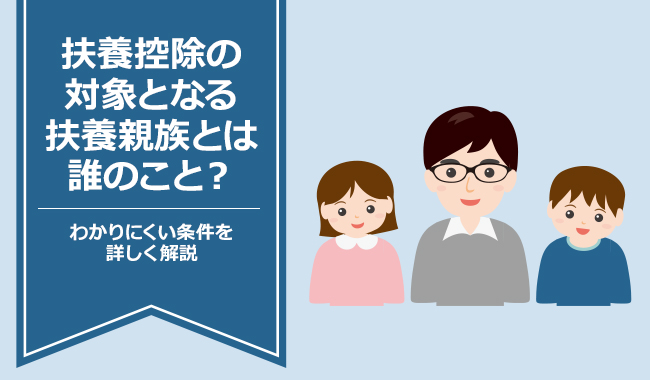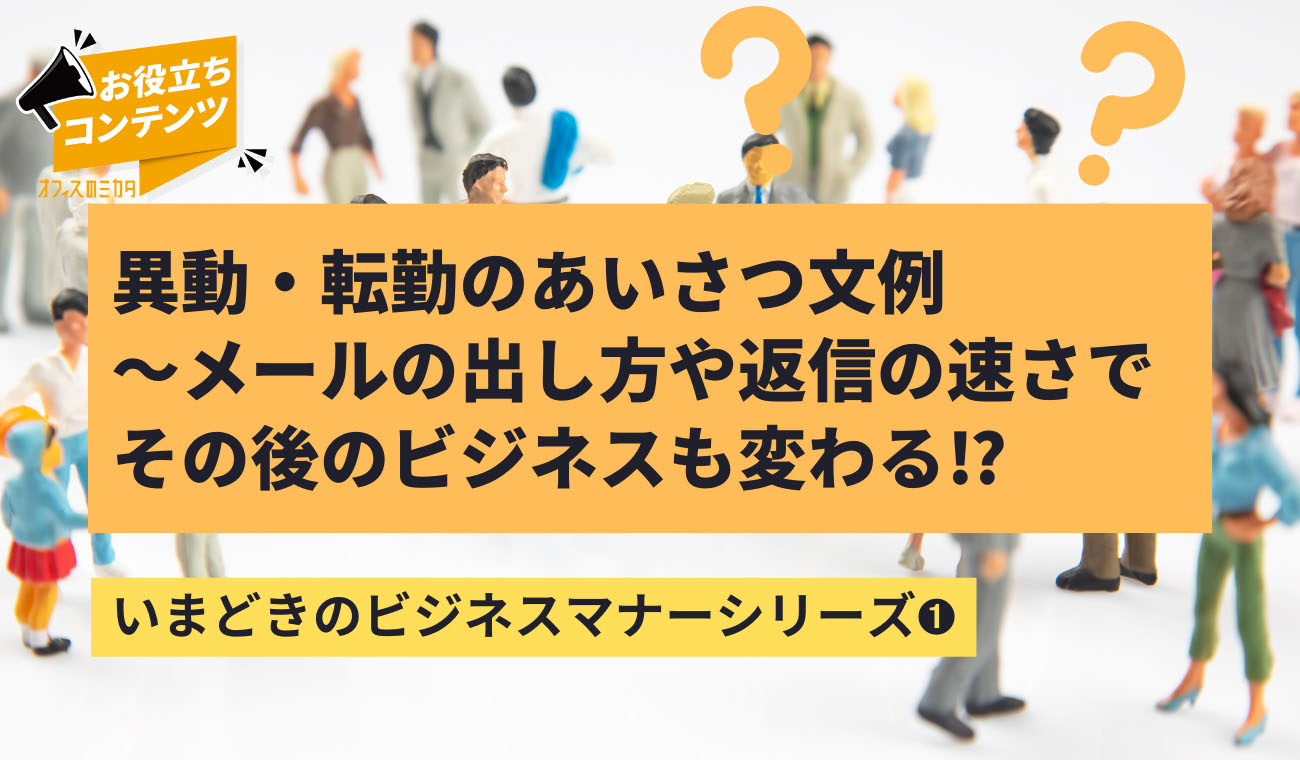【2025年版】6月のビジネスメール・手紙の挨拶文例~お役立ちコンテンツ~
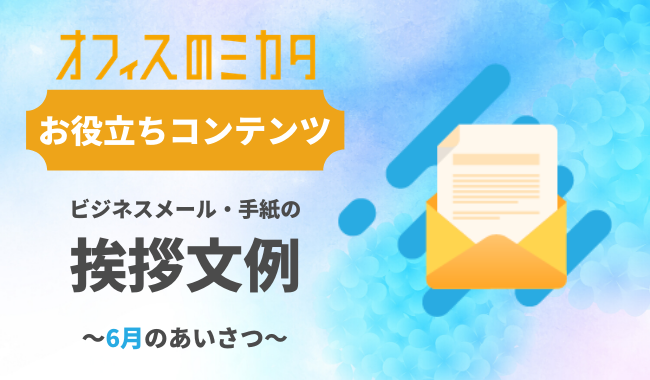
6月は梅雨の季節。真夏のような蒸し暑さを感じる日も多く、心身ともに疲れやすい時期でもあります。こうした時期にビジネスシーンで送るメールやお手紙では、相手への気遣いを込めて、少しでも気持ちが晴れやかになるようなあいさつから始めたいものです。
本記事では、夏を目前に控えた6月に送るメールや手紙にふさわしい、時候の挨拶と文末表現を、フォーマルな場面とカジュアルな場面に分けてご紹介します。相手との関係性ややり取りの場面、使用するツールなどに応じて、適切に使い分けながらご活用ください。
目次
●【メール】フォーマルな時候の挨拶と結びの言葉
●【メール】カジュアルな時候の挨拶と結びの言葉
●【手紙】フォーマルな時候の挨拶と結びの言葉
●【手紙】カジュアルな時候の挨拶と結びの言葉
● まとめ
【メール】フォーマルな時候の挨拶と結びの言葉
ビジネスシーンでは、顧客やクライアントに対して各種案内状などフォーマルな文面のメールを送る機会もありそうです。ここでは、改まった場面で使いたい時候の挨拶から文頭表現、文末表現を見ていきましょう。
時候の挨拶
フォーマルな場面では、季節を端的に表す用語を用いた「○○の候」という一節から始まる漢語調の挨拶が相応しいです。○○の候の後には、相手の繁栄を喜ぶ言葉や日頃の感謝を記すことを、セットとして覚えておくとよいでしょう。6月の季節を表す用語として、「入梅」「梅雨寒」「長雨」などの梅雨時期を表すものや、「麦秋」「小夏」などが多く使われます。メールを送る時期に合わせて使い分けましょう。
・入梅の候(みぎり)、貴社におかれましては益々ご繁栄のことと、お喜び申し上げます。
・梅雨寒の候(みぎり)、貴社益々ご隆盛の由、大慶の至りと存じます。
・麦秋の候(みぎり)、○○様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
・小夏の候(みぎり)、平素は格別にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
結びの言葉
末文は、文頭とは別の表現を使って季節柄と相手を労わる言葉や、相手のさらなる繁栄を願う言葉の他、指導や愛護を願う言葉をセットで使いましょう。相手が最後に読む文末を丁寧に結ぶことで、文章全体がまとまり、相手により丁寧な印象を与えられます。
・向暑のみぎり、貴社ますますのご発展をお祈り申し上げます。
・夏至の候、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
・梅雨寒の折、ご自愛くださいませ。
・ご多用の折、誠に恐れ入りますが、ご都合をお聞かせ願えれば幸いです。
【メール】カジュアルな時候の挨拶と結びの言葉
親しい顧客や、頻繁にやり取りがあるクライアントなどの親しい間柄では、改まった表現をすると、かえって形式ばったものに感じさせてしまうこともあります。そのような時は、相手を気遣いつつも、親密性が感じられるよう、やや砕けた表現を使うのもよいでしょう。ここでは、普段のビジネスメール等にも利用できる、カジュアルな時候の挨拶や文末表現を見ていきます。
時候の挨拶
ビジネスカジュアルや、カジュアルシーンで使う時候の挨拶は、口語調の言葉を選びましょう。6月らしい季節を表す表現に加え、相手の状況を気遣う一言を添えるとよいでしょう。
・さわやかな初夏の風が心地よい好季節となりました。○○様におかれましては、益々ご活躍のことと存じます。
・雨に濡れ、木々の緑も深みを増すこの頃、いかがお過ごしでしょうか。
・長雨の続くこのごろですが、○○様におかれましては、相変わらずご活躍のことと拝察いたします。
・梅雨とは思えない暑さが続いておりますが、お変わりありませんか。
・夏至を過ぎ、梅雨明けが待ち遠しいこの頃ですが、貴社におかれましてはますますご清栄のことと存じます。
結びの言葉
文章全体の雰囲気に合わせた丁寧かつカジュアルさもある表現を使い、相手の繁栄と活躍を祈る言葉や、健康や幸せを願う気持ちを添えて結びとしましょう。
・うっとうしい日が続いております。体調を崩されないようくれぐれもご自愛ください。
・梅雨はまだしばらく続きそうですが、皆様のご健康を心よりお祈り致します。
・梅雨明けが待ち遠しいこの頃ですが、どうぞ健やかにお過ごしください。
・青葉生い茂る初夏のみぎり、ますますのご活躍をお祈りいたします。
【手紙】フォーマルな時候の挨拶と結びの言葉
ビジネスシーンでは手紙のやり取りは減少傾向にありますが、相手が紙の文書を好む場合や、重要な内容を丁寧に伝えたい場面では、手紙が適していることもあります。ここでは、ビジネスレターにふさわしい時候の挨拶や、頭語・結語を含む基本的な文末表現を確認しておきましょう。
時候の挨拶
フォーマルな文書では、「謹啓」や「拝啓」といった頭語から書き始めるのが適切です。頭語の後には、メールと同様に漢語調の時候の挨拶を添えるとよいでしょう。一カ月の中でも季節の移ろいは大きいため、送付する時期にふさわしい表現を選ぶことが大切です。
・謹啓 初夏の候(みぎり)、貴社におかれましては益々ご隆盛のことと、お喜び申し上げます。
・謹呈 短夜の候(みぎり)、○○様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
・恭啓 向暑の候(みぎり)、平素は格別にご高配を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
・拝啓 入梅の候(みぎり)、貴社一段とご繁盛の段、大慶に存じます。
・拝呈 梅雨寒の候(みぎり)、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
結びの言葉
文末には、相手の健康や繁栄を願う言葉、あるいはご厚情に感謝する言葉などを添えるのが一般的です。さらに、季節感を取り入れることで、文章全体がより引き締まり、丁寧な印象を与える末文となります。なお、文頭に「謹啓」や「拝啓」などの頭語を用いた場合は、その結びにふさわしい結語を添えるのが基本です。頭語と結語には決まった組み合わせがありますので、正しく使い分けることが大切です。
・麦秋のみぎり、貴社ますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 謹言
・夏至の候、より一層のご活躍を祈念いたします。 謹白
・梅雨冷の折、お身体をおいといくださいませ。 敬白
・初夏の折、末筆ながら、皆様の益々のご健勝とご多幸を衷心よりご祈念致します。 敬具
・長雨が続く季節につけ、ご自愛専一になさってください。 敬白
【手紙】カジュアルな時候の挨拶と結びの言葉
メールと同様に、相手との関係によっては、手紙の文面にも親しみや柔らかさを持たせたい場面があるかもしれません。そのような場合には、丁寧さを保ちつつも、やや口語調の砕けた表現を取り入れることで、温かみのある印象を与えることができます。ここでは、そうした場面にふさわしい、手紙に添える時候の挨拶や文末表現についてご紹介します。
時候の挨拶
カジュアルシーンでは、頭語や結語を省略することも多く、冒頭では季節を感じさせる表現に続けて、相手への気遣いや相手の繁栄を喜ぶ気持ちを盛り込むとよいでしょう。6月は梅雨の季節ですが、地域によって天候の状況は異なります。相手のお住まいの地域や状況を考慮しながら、適切な言葉を選ぶことが大切です。
・今年も衣替えの季節を迎えますが、お変わりありませんか。
・雨に濡れたあじさいの花の色が一層濃くなるこの頃、○○様もお元気でお過ごしのことと拝察いたします。
・麦の穂の色づく季節を迎え、いよいよご壮健のことと存じます。
・梅雨入りを控え、不安定な天候が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
・梅雨寒の日が続いていますが、ご機嫌いかがでしょうか。
・長雨の頃ですが、相変わらずご活躍のことと存じます。
結びの言葉
結びの表現においても、メールと同様に口語調でやわらかな語り口を心がけましょう。特に梅雨どきは体調を崩しやすい時期でもあるため、相手の健康を気遣う一文を添えると、思いやりの気持ちが伝わります。また、夏に向けた前向きなメッセージを加えることで、読み手の心にも明るい印象を残すことができます。
・梅雨入り間近ですが、どうぞ健やかにお過ごしください。
・青葉が生い茂る初夏の折、貴社のさらなるご活躍をお祈り致します。
・梅雨冷えの日が続いております。どうかご自愛専一にお過ごしください。
・長雨の季節となりました。お身体には十分おいといください。
・梅雨明けが待ち遠しいこの頃です、どうぞ心穏やかにお過ごしくださいませ。
まとめ
改まったシーンで用いる漢語調のあいさつから、日常的なやり取りに適した口語調のカジュアルな表現まで、6月にふさわしい多彩な時候の挨拶をご紹介しました。
梅雨空のようにどんよりと曇った日が続くかと思えば、晴れ間には夏の訪れを感じさせるような暑さが広がる6月は、天候の変化が特に大きい時期です。こうした季節だからこそ、メールやお手紙の文面に、古くから日本人が大切にしてきた季節の移ろいを表す時候の挨拶を添えてみてはいかがでしょうか。安否を気遣う気持ちや、日頃の感謝を穏やかに伝えることで、より心の通うコミュニケーションにつながることでしょう。
<お役立ちコンテンツ「ビジネスメール・手紙の挨拶文例」>
ー4月の挨拶ー
ー5月の挨拶ー
ー7月の挨拶ー
ー8月の挨拶ー
ー9月の挨拶ー
ー10月の挨拶ー
ー11月の挨拶ー
ー12月の挨拶ー
ー1月の挨拶ー
ー2月の挨拶ー
ー3月の挨拶ー

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする