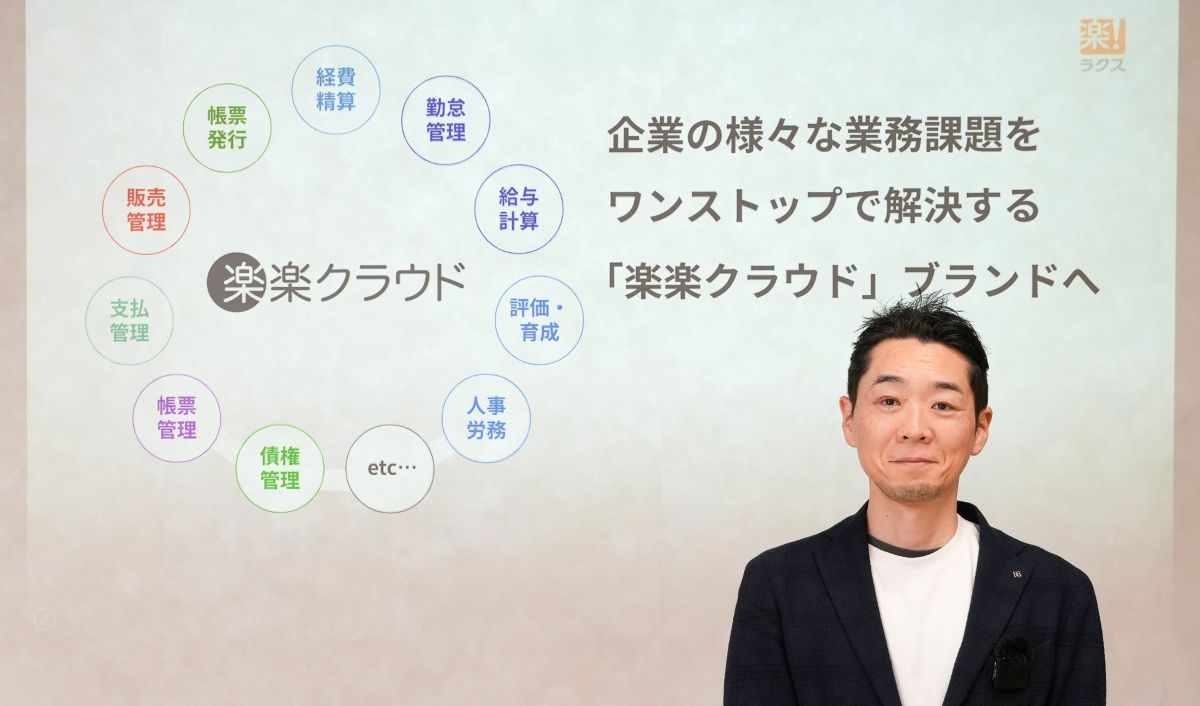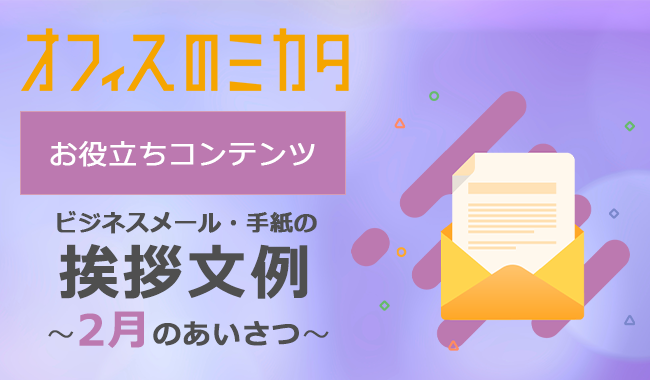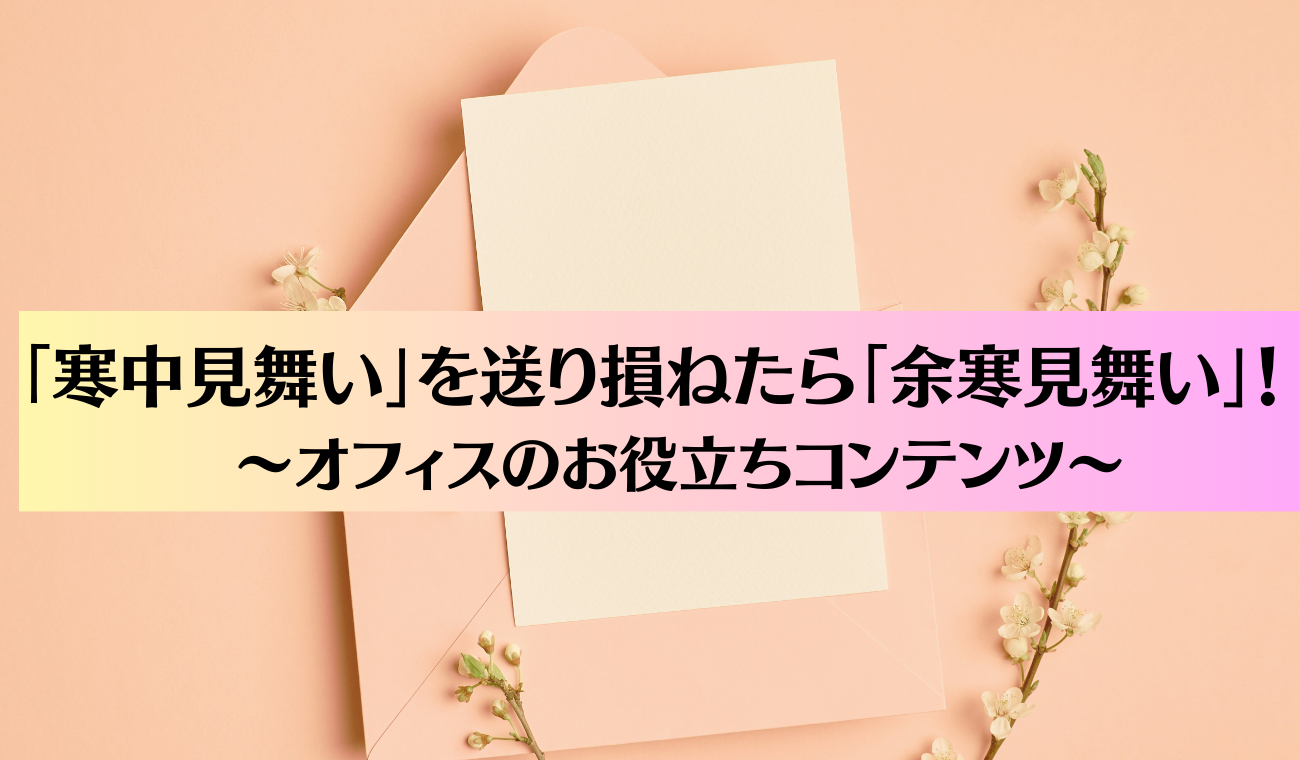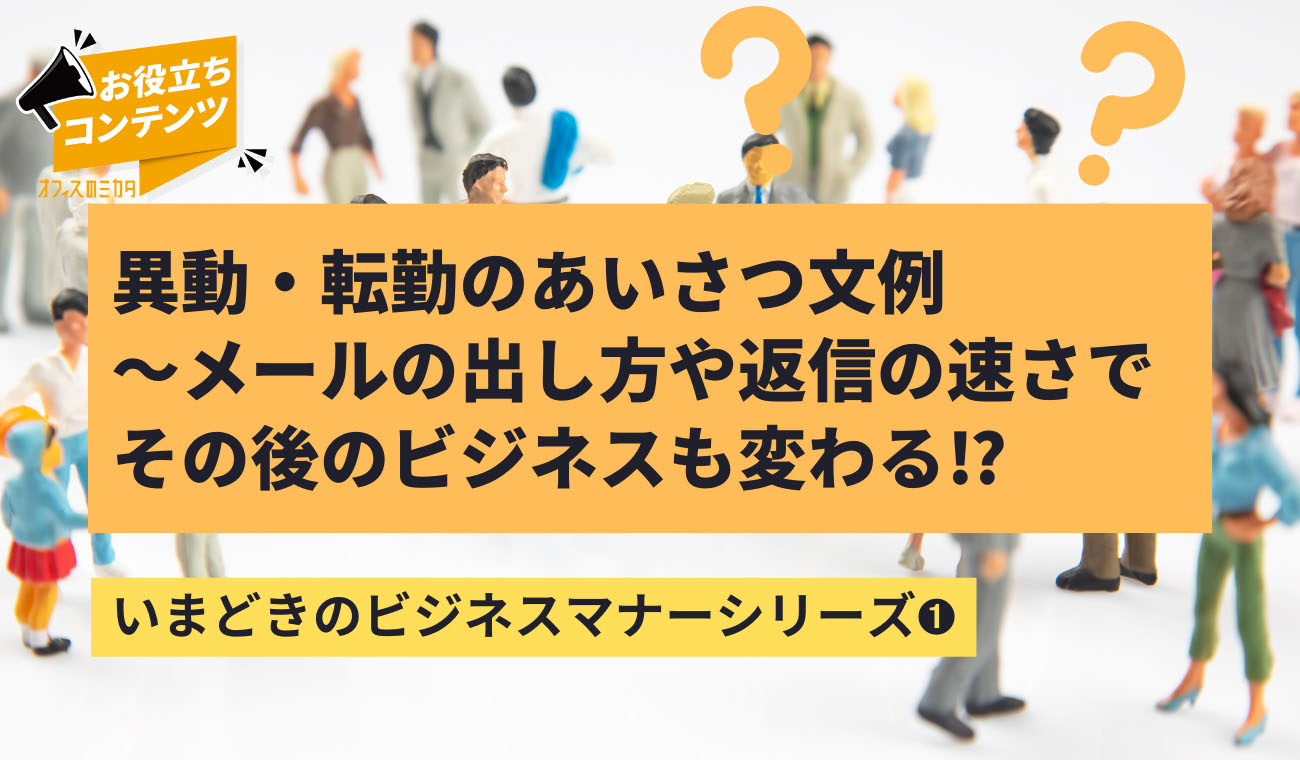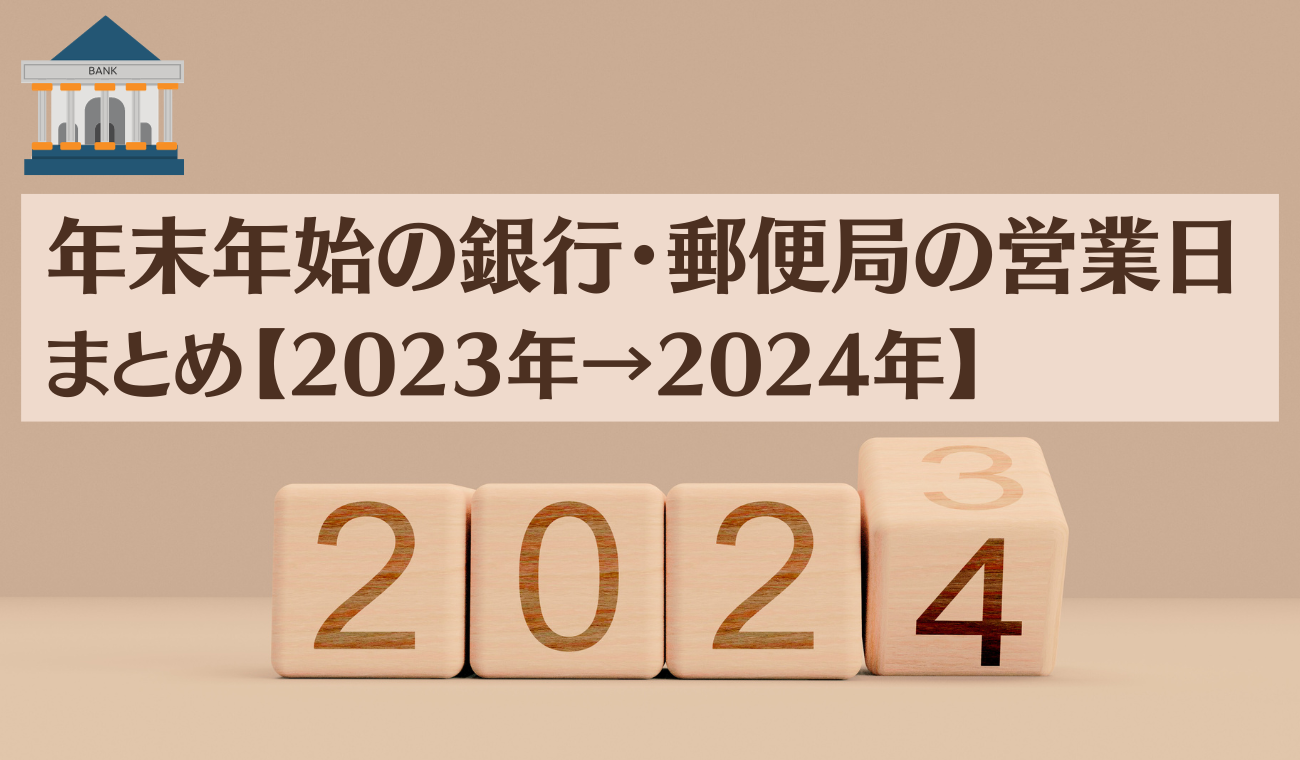社保拡大やフリーランス新法、健康保険証の廃止… 2024年後半、人事労務担当者が押さえるべき法改正とは?【freeeTOGO World 2024より】

2024年5月14日、人事労務や会社設立を支援するクラウドサービスを提供するフリー株式会社が、会計、人事、労務、情報システムなどのバックオフィスの最先端を紹介するイベント「freee TOGO World」を開催した。当日行われたセッション「労務の最前線!2024~プロが予測!年度はじめに今年のトレンドを完全把握~」から、労務人事担当者が押さえておきたい2024年後半の動きについて紹介する。
※前半はこちらから:2024年4月からの法改正、本当に対応できてる?人事労務担当者が確認したい3つの法改正【freeeTOGO World 2024より】
目次
■2024年下半期人事労務関係の注目ポイントは?
■2024年10月1日:社会保険適用拡大
■秋施行予定:フリーランス新法
■12月2日予定:健康保険証廃止、マイナ保険証への移行周知を
■法改正に向けた情報収集と対策を
2024年下半期人事労務関係の注目ポイントは?
登壇した日本社会保険労務士法人特定保険社会保険労務士 山口友佳氏(以下、山口氏)によれば、2024年下半期に人事労務担当者が押さえておきたいものは下記3つ。
①社会保険の適用拡大(2024年10月1日から)
従業員数101人以上の企業から51人の企業へ引き下げ
②フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行(2024年秋施行予定)
③健康保険証の廃止(2024年12月予定)
特に2024年秋施行予定のフリーランス・事業者間取引適正化等法に関しては、非常に大きなトレンドの一つだという。
2024年10月1日:社会保険適用拡大
まず押さえておきたいのが、2024年10月1日から適用される「短時間労働者への社会保険適用拡大」。業種問わず101人以上の企業から51人以上の企業へ引き下げられる。
短時間労働者の加入条件としては5つの条件があり、これら全てを満たすことで被保険者となる。
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月超見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上
・学生でないこと
・特定適用事業所(被保険者51人以上)または任意特定適用事業所に勤めていること
特定適用事業所とは、1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上(改正後は50人以上)となることが見込まれる企業等のこと(※1)。また任意特定適用事業所は、特定適用事業者の要件に満たない場合でも申し出により対象事業所となった事業所を指す。
社会保険適用拡大にむけて、人事労務担当者が行うことは下記3つ。
①短時間労働者の社会保険加入要件対象者を洗い出す
②対象者に、対象となることや保険料がどのくらいかを先に通知する
③加入を望まない人に対しては労働契約の変更を行う
「2024年10月の適用に向けて、新たに対象になる方への通知や保険料の概算を伝えるなどコミュニケーションをとってほしい」と山口氏。社会保険加入を望まない従業員に対しては、労働契約を変更するなど対応が必要だ。
※1 出典元:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)
秋施行予定:フリーランス新法
フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、新法)は、発注事業者(企業)との取引適正化とフリーランスの就業環境整備を目的に創設されたもの。
「新法は、競争法と労働法に関わる部分があるため、中小企業庁が管轄する部分、厚生労働省が管轄する部分と分かれているのが特徴」(山口氏)
法律の内容は、業務内容や報酬額など書面による取引条件明示の義務化や妊婦健診の時間確保など育児介護等業務両立への配慮の義務化などが挙げられる。これまでは労働法の保護を受けられなかった部分だが、新法により従業員に近いような保護が与えられるという。

フリーランスと取引のある企業の人事労務担当者が行うべきことは下記の3つ。
①自社が新法で定義する発注事業者に該当するか
②相手方が新法で定義するフリーランスに該当するか確認
③相手方が本当にフリーランスか、偽装請負や偽装フリーランスになっていないか確かめる
発注事業者(特定業務委託事業者)は、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの。フリーランス(特定受託事業者)は、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう(※2)。つまり、従業員を雇っているかいないかで区分されるため、従業員を雇用しているフリーランスは法律の対象外となる点に注意したい。
とはいえ、事例がないため2024年5月時点で従業員の定義や継続的業務委託の期間など確定していないものも多いと山口氏。制度改正に向けて情報収集を行っていく必要がある。
※2 出典元:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)の概要(新規)
12月2日予定:健康保険証廃止、マイナ保険証への移行周知を
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正により、健康保険証の発行が2024年12月2日に終了する(※3)。また発行済み保険証に関しては、マイナ保険証移行期間として最大1年間は利用可能だとしている。

マイナ保健証への移行に伴って、人事労務担当者が行うことは下記の3つ。
①健康保険証が12月2日で廃止することを従業員へ早めに通知
②今のうちからマイナ保険証へ切り替え手続きを行うよう周知
③入退社の手続きフローを見直す
中には、マイナンバーカードを取得していない/使いたくない従業員もいるだろう。そういった従業員に対しては、申請によらず対象者に資格確認書を交付するとしている(※4)。ただ詳細は関係機関と調整中とのことで、動向を確認しつつ、従業員にはマイナンバーカードがないと保険診療が受けられない訳ではないことを伝えるようにしたい。
マイナンバーカードの健康保険証利用手続きについては、デジタル庁がすでに紹介している(※5)。「人事労務担当者が自ら早めにマイナ保険証に切り替えて、周知させるのも一つの手」だと山口氏は語る。
あわせて健康保険証に関する手続きの改正も行われるため、動向については協会けんぽや健康保険組合のサイトを確認しておきたい。
※3 出典元:1.マイナ保険証の利用促進(厚生労働省)
※4 出典元:マイナンバー情報総点検本部(首相官邸)
※5 参考元:マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法(デジタル庁)
法改正に向けた情報収集と対策を
2024年の後半にかけて社会保険適用拡大、フリーランス・事業者間取引適正化等法、健康保険証の廃止に関する人事労務の担当者がやるべきことを紹介してきた。この秋に向けて人事労務担当者はより一層情報収集しつつ、従業員への早めの周知が必要となる。
なお2025年は育児介護休業法の改正、2028年10月には雇用保険法の改正などが予定されている。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする