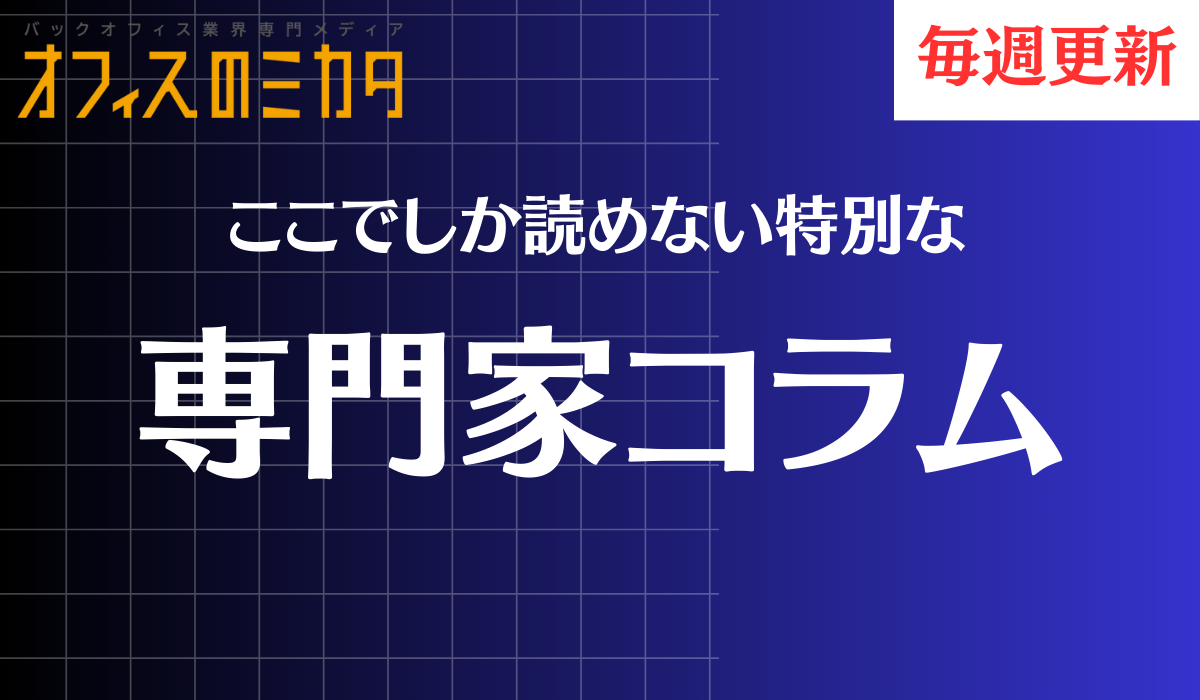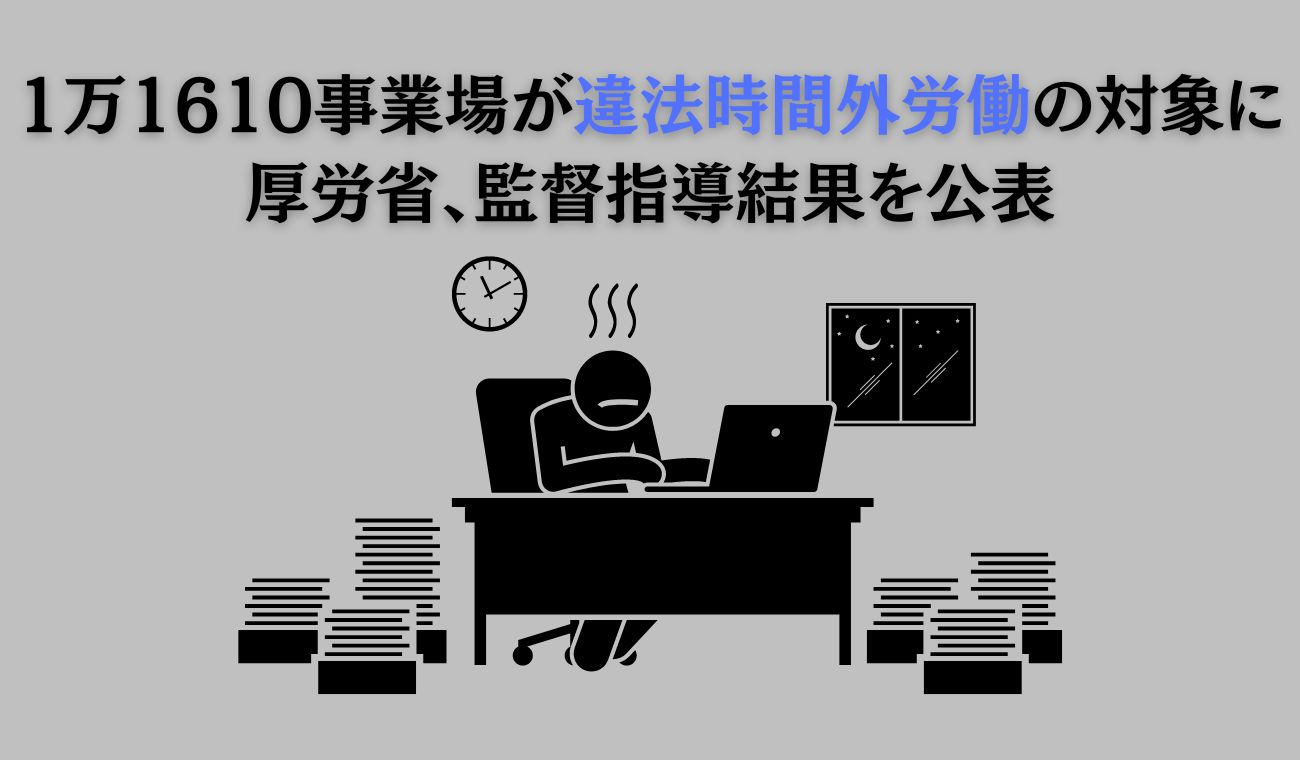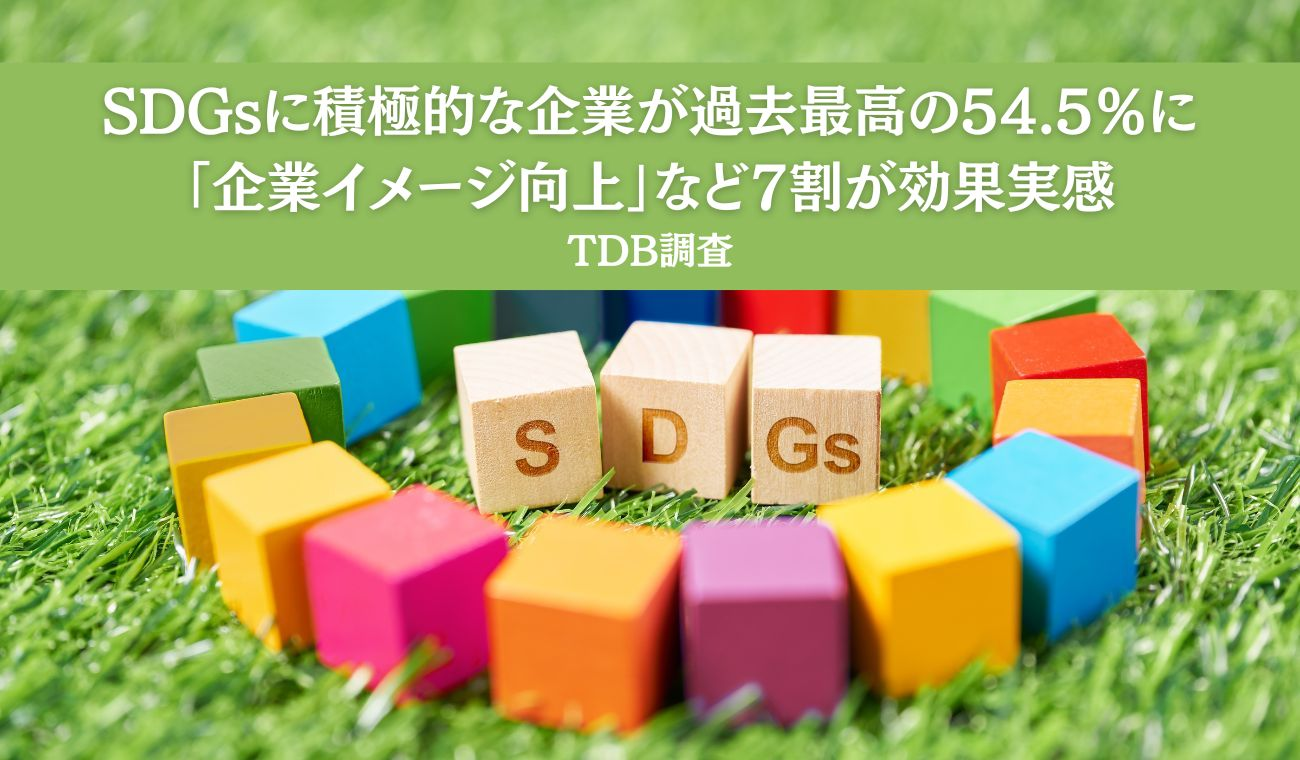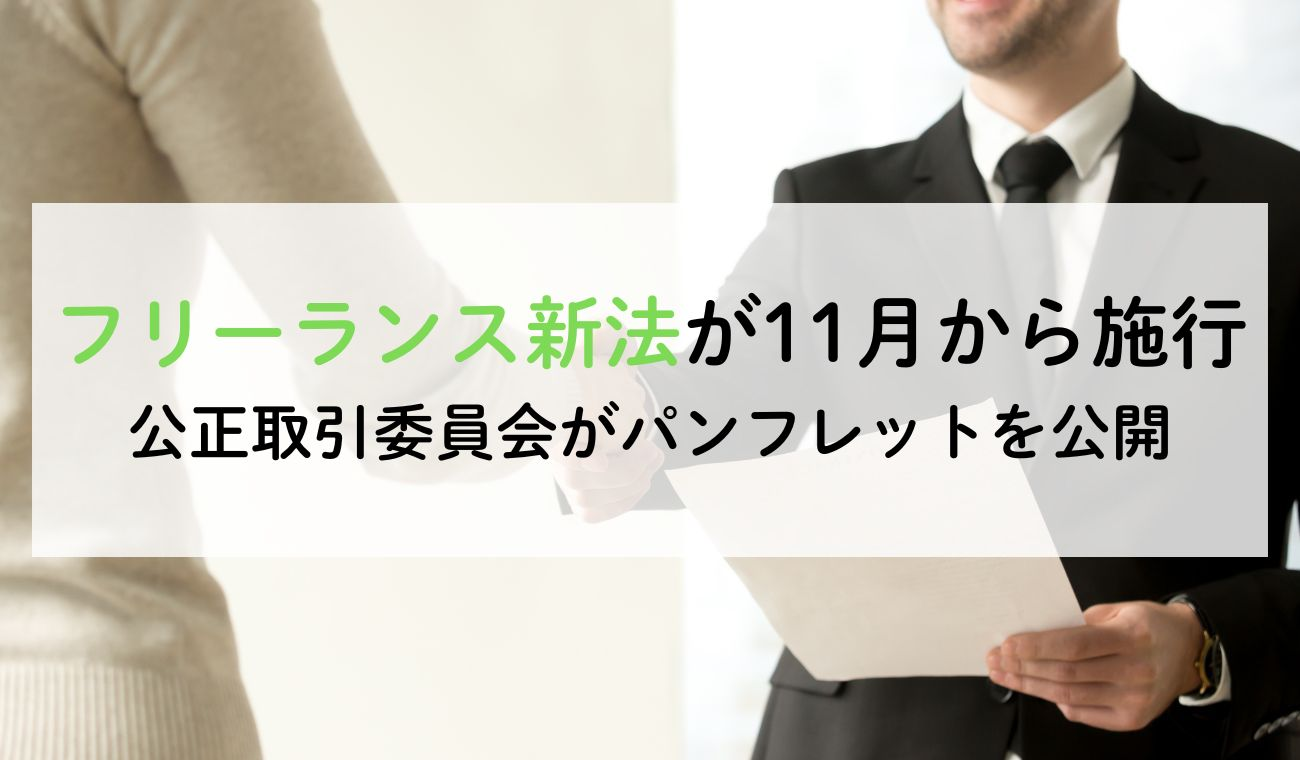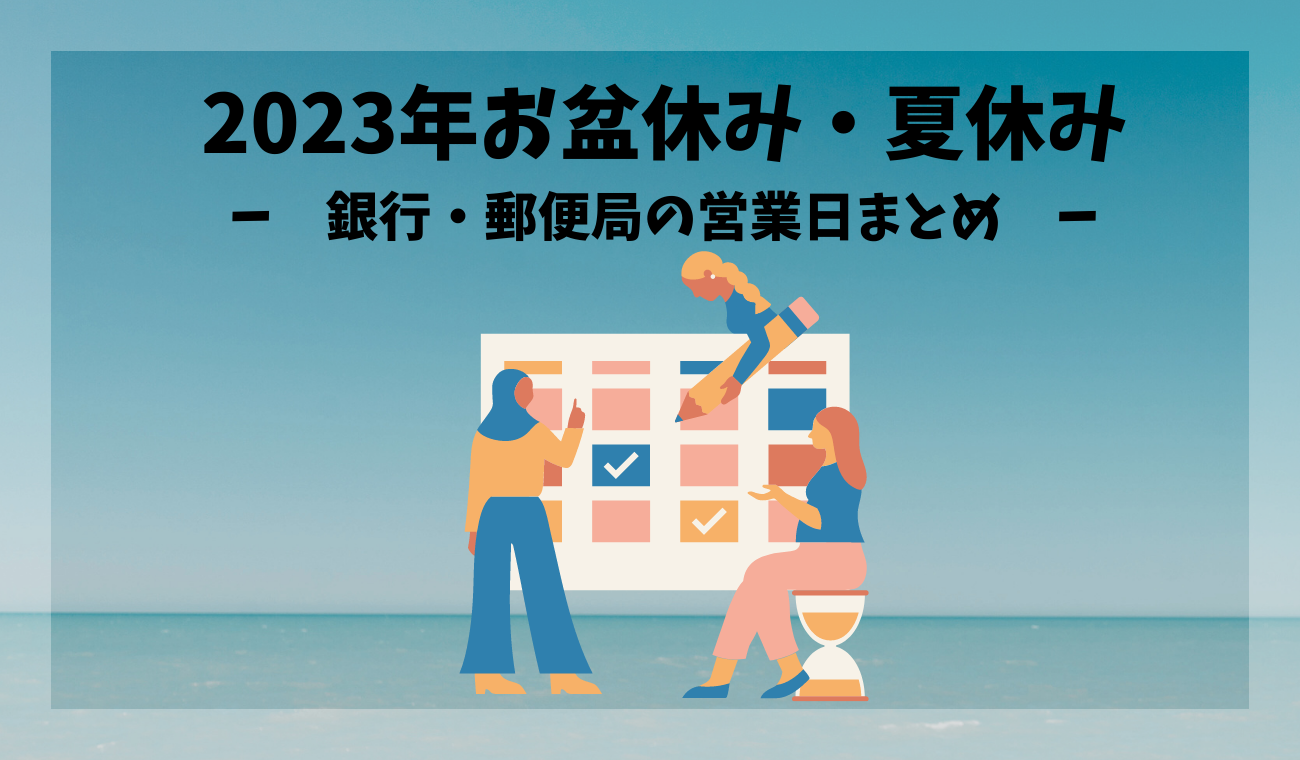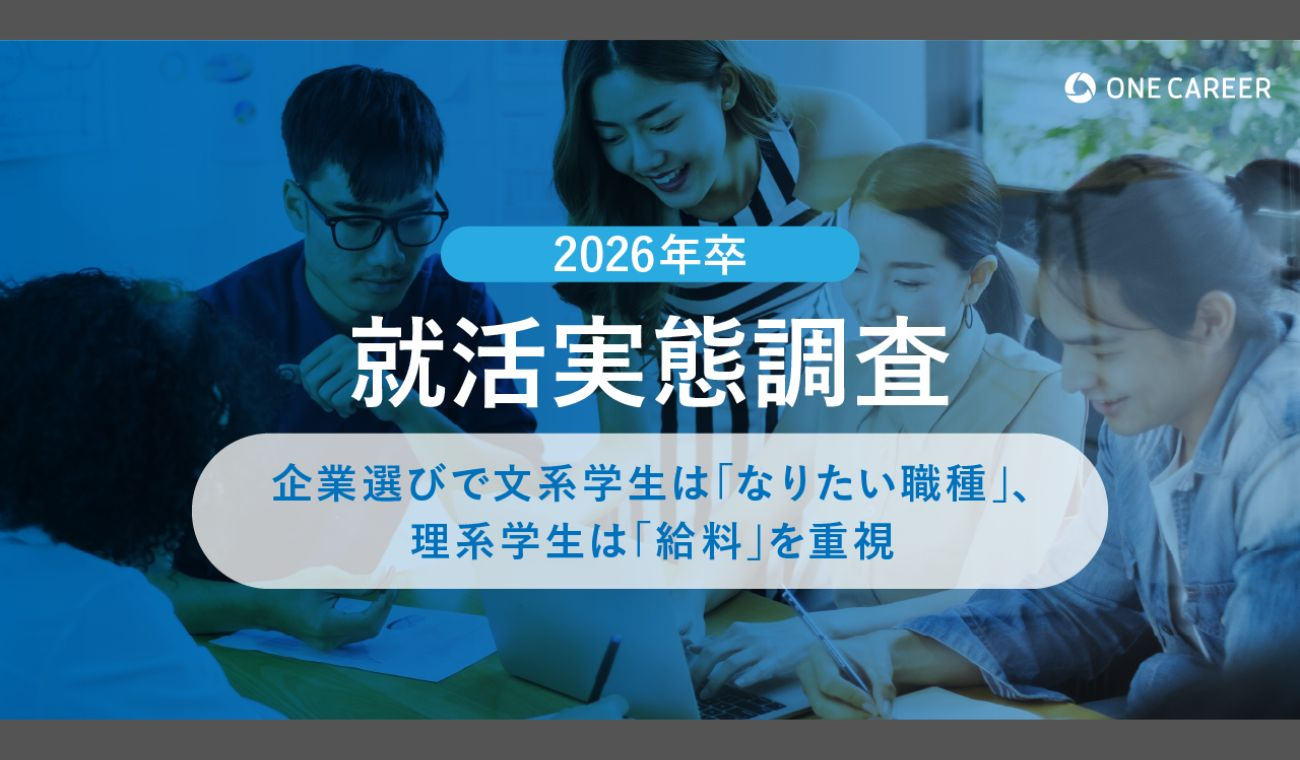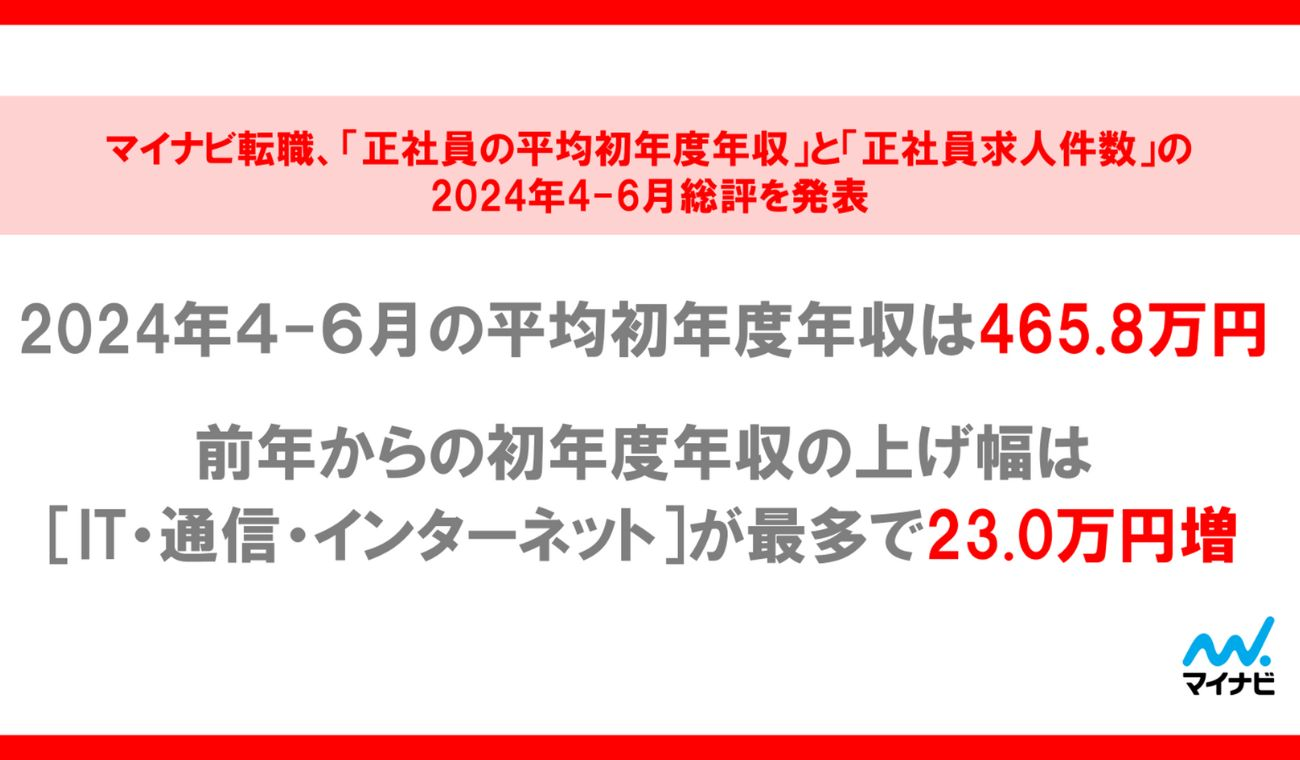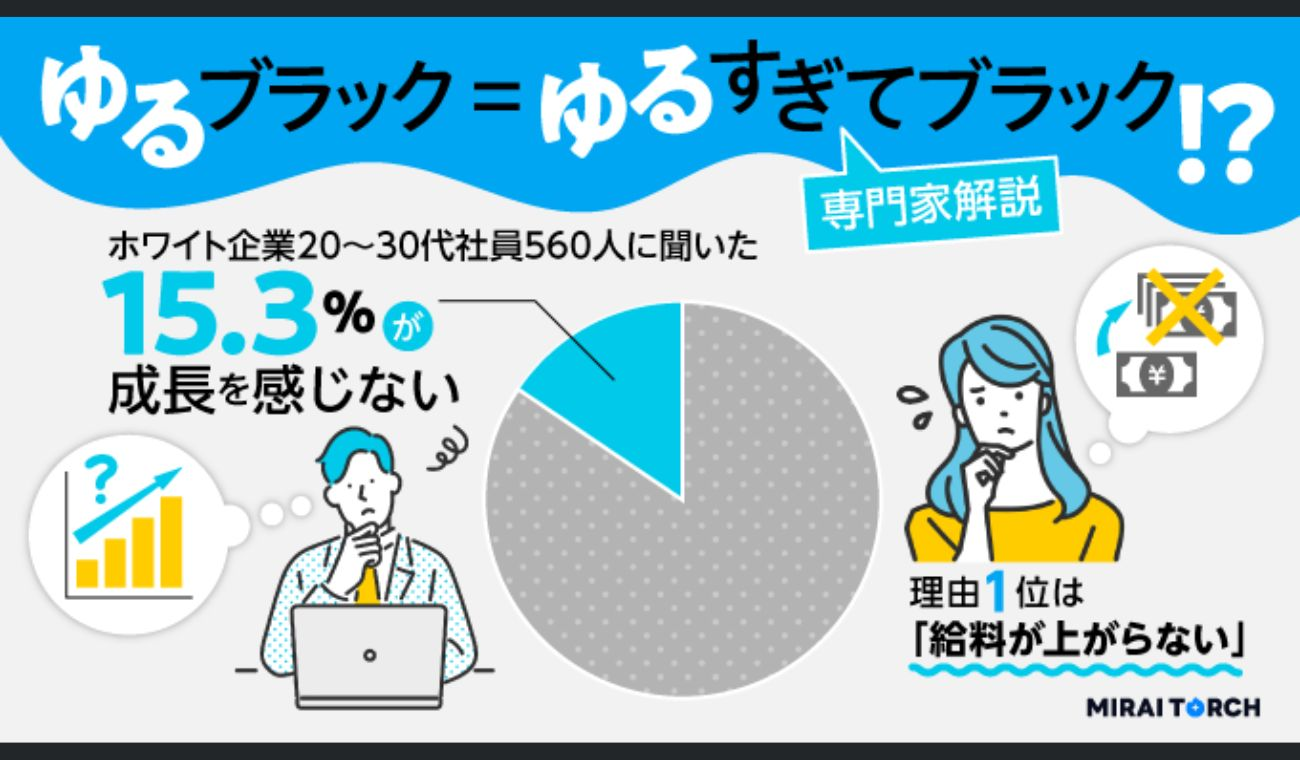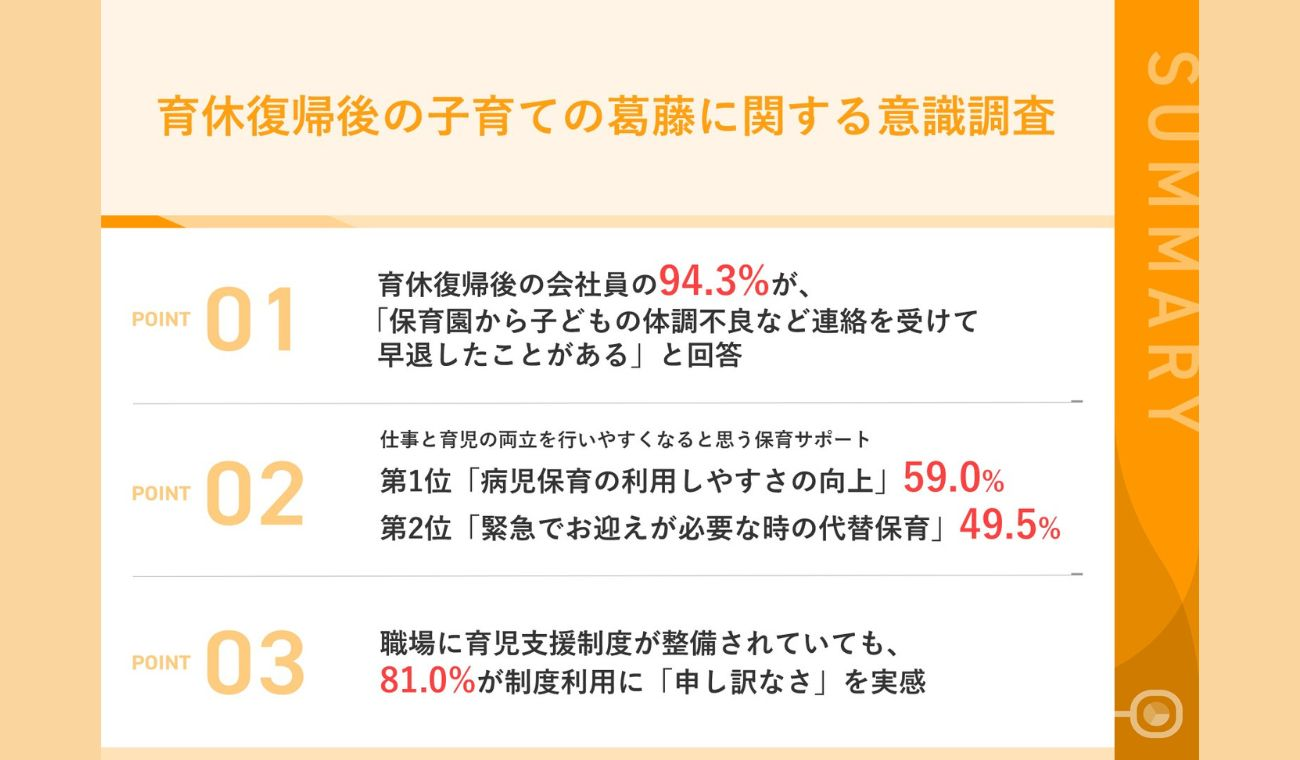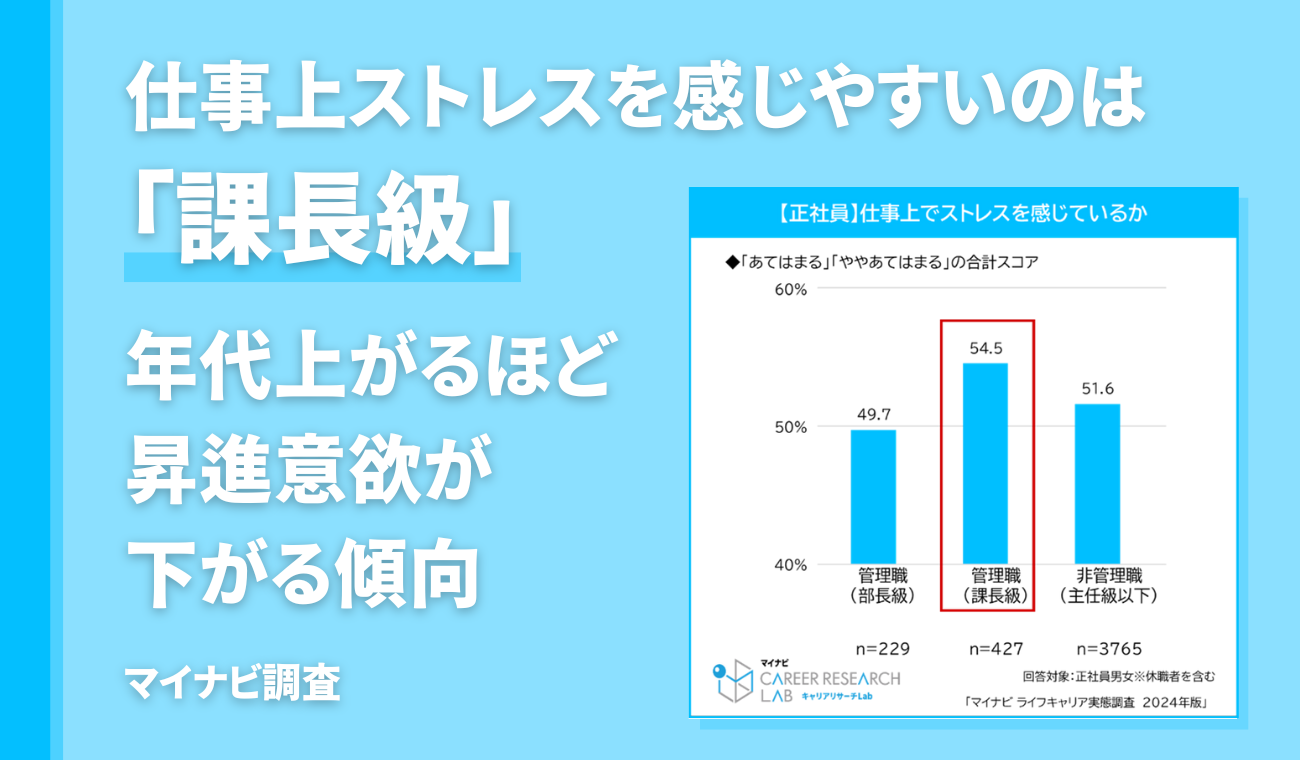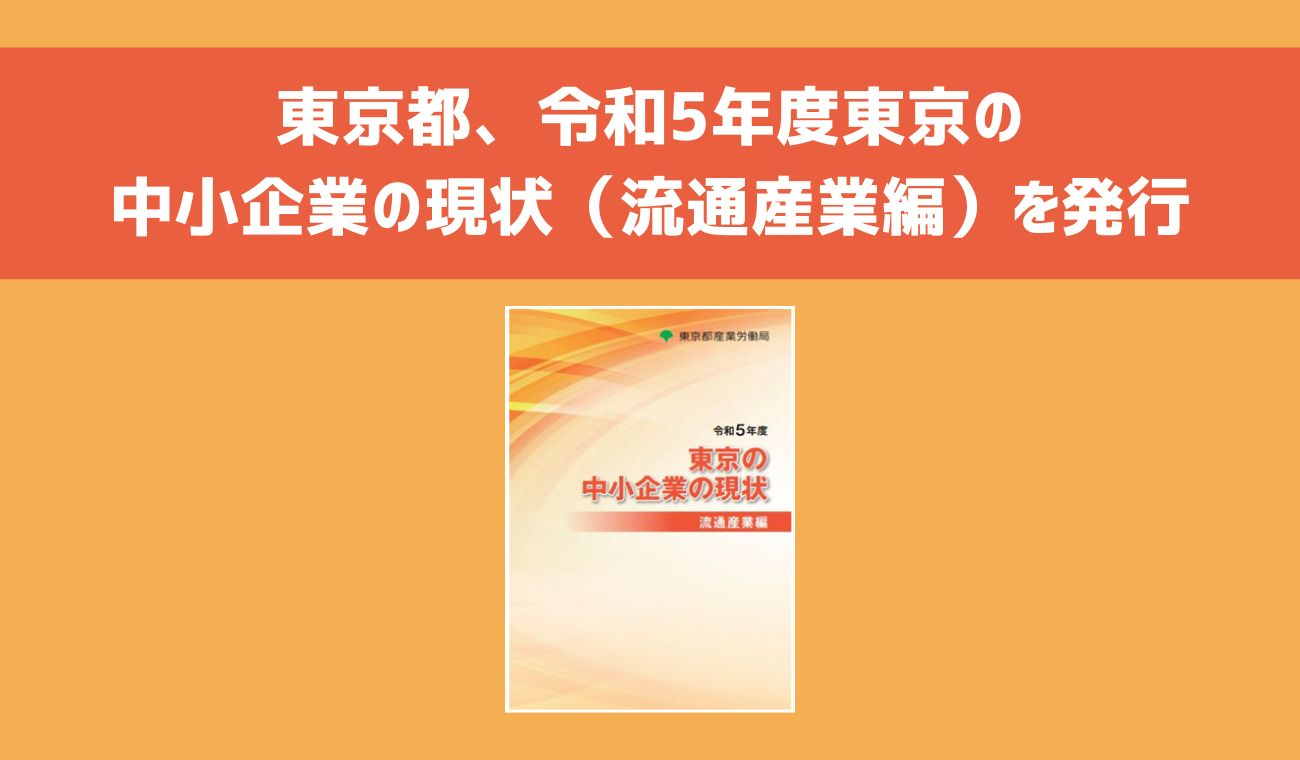部下に不満を抱える上司は約8割|部下とのコミュニケーションに感じる課題や実行した対応は?
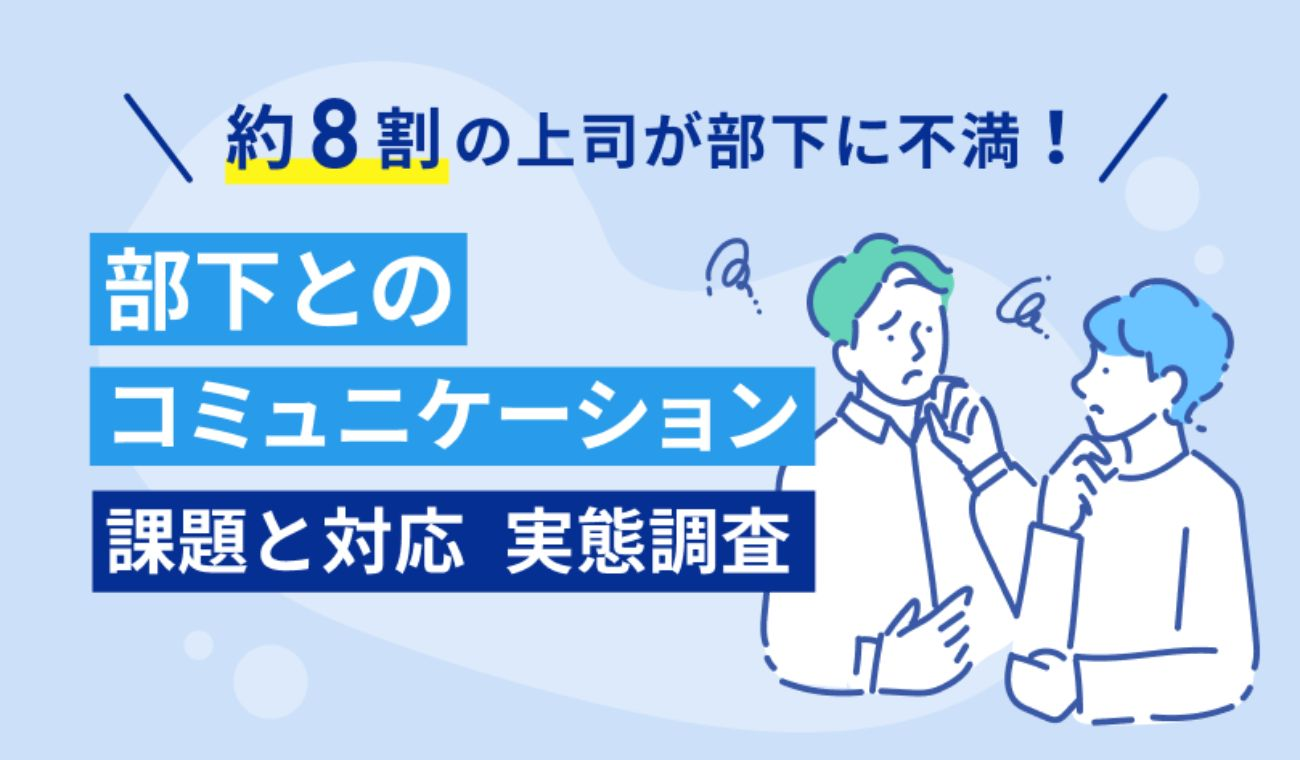
株式会社アシロ(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:中山博登)は、労働問題の相談・対応を得意とする弁護士・法律事務所を検索できるポータルサイト「ベンナビ労働問題」にて、部下を持ったことがある男女2432人に対して、部下とのコミュニケーションに関する調査を実施した。
部下を持つ上司の課題を明らかに
同社は人手不足に悩む企業が多い現代では、あらゆる組織で人材の確保と定着のために予算を割いていながらも、必ずしも成果が出ているとはいえないことを指摘。また、業務内容や待遇改善による人での確保だけではなく、人間関係や上司・部下間のコミュニケーションも、人材の定着の重要な課題だとする見解を示した。
その上で、実際に部下を持つ上司がどのようにコミュニケーションをとり、どんな課題を抱えているのかを明らかにするため、アンケート調査を実施した。
調査概要
調査対象: 20歳以上の男女2432人
性別割合: 男性(1486人)女性(946人)
調査方法: Freeasyを用いたインターネットリサーチ
調査日 : 2024年5月21日〜2024年5月22日
出典元:8割の上司が部下に不満があると判明!2,432人の上司にアンケート調査を実施(ベンナビ労働問題/株式会社アシロ)
8割が対面でコミュニケーション 約4割が課題感

本調査では「部下とのコミュニケーションでよく使用する手段はなんですか?」との質問に、80.3%が「対面」と回答している。次いで「チャットツール(Chatwork/Slack/LINEなど)」が11.5%となった。
また「部下とランチや飲み会の機会はありますか?」との質問では「よくある(週に1回以上)(9.3%)」「たまにある(月に数回)(23.2%)」「あまりない(年に数回)40.8%)」と、頻度に差はあるものの、7割以上が部下との飲み会やランチの機会を持っていることがわかった。
「部下とのコミュニケーションが円滑に行われていると感じますか?」との質問には60%以上が「感じる」と回答。その理由として、407人が「話す機会が少ない」と回答し最多となった。次いで「考え方・常識が違う(385人)」「共通の話題がない・何を話したらいいかわからない(313人)」が続いている。
約8割は部下に不満「やる気/熱意がない」「言われたことしかできない」など

続いて、本調査では部下に対する不満について質問。「部下に不満はありますか?」との質問に「まったくない」と回答したのはわずか20.1%で、79.9%は少なくとも何かしらの不満を抱えている実態が明らかになった。
具体的な不満としては「やる気/熱意がない(560人)」「言われたことしかできない(518人)」「指示をうまくくみ取れない(459人)」「信頼して仕事を任せられない(451人)」「コミュニケーション能力が足りない(421人)」などが上位に並んでいる。
「不満がある場合、どう対応しますか?」との質問では「話す機会をもうける(747人)」が最多となったが「やんわり指摘する(711人)」も同程度の人が選択しており、メンタル面への悪影響やハラスメントを懸念してか、毅然とした対応や行動に移れない様子もうかがえる。なお「はっきりと伝える」は484人であった。
部下への対応に困ったときの相談相手としては「上司・先輩(1058人)」「近い間柄の同僚(970人)」が上位で「誰にも相談していない」も538人と多く選択されていた。
続いて本調査では「部下と接する際、どんなことに気をつけていますか?」と質問。その結果「感情的にならない(1068人)」「こまめにコミュニケーションをとる(1054人)」「意見を押しつけない(963人)」「部下の話をよく聞く(830人)」などが上位に並んでいる。
まとめ
本調査では上司の多くが部下に対して何かしらの不満を抱いており、コミュニケーションをとることで対応している実態が明らかになった。一方で対応方法として一定数が「やんわり指摘する」と回答しており、部下に指摘する際にはっきり伝えられないケースも多いようだ。
2024年4月にパーソルキャリア株式会社の調査機関「Job総研」が実施した調査(※1)では、上司からのフィードバックについて「はっきり言われたい」と考える人が多いとの結果が出ている。ハラスメントなどへの注意は必要だが、業務上必要な注意や指導はパワーハラスメントに該当しない。本当に伝えなければならないことはある程度はっきり伝えてもいいのではないだろうか。
厚生労働省によるハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、ハラスメントの定義について紹介されている(※2)。改めて参考にしていただきたい。
※1 出典元:『2024年 人材育成の意識調査』を実施しました(パーソルキャリア株式会社)
※2 参考:「ハラスメント基本情報」ハラスメントの定義(あかるい職場応援団/厚生労働省)

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする