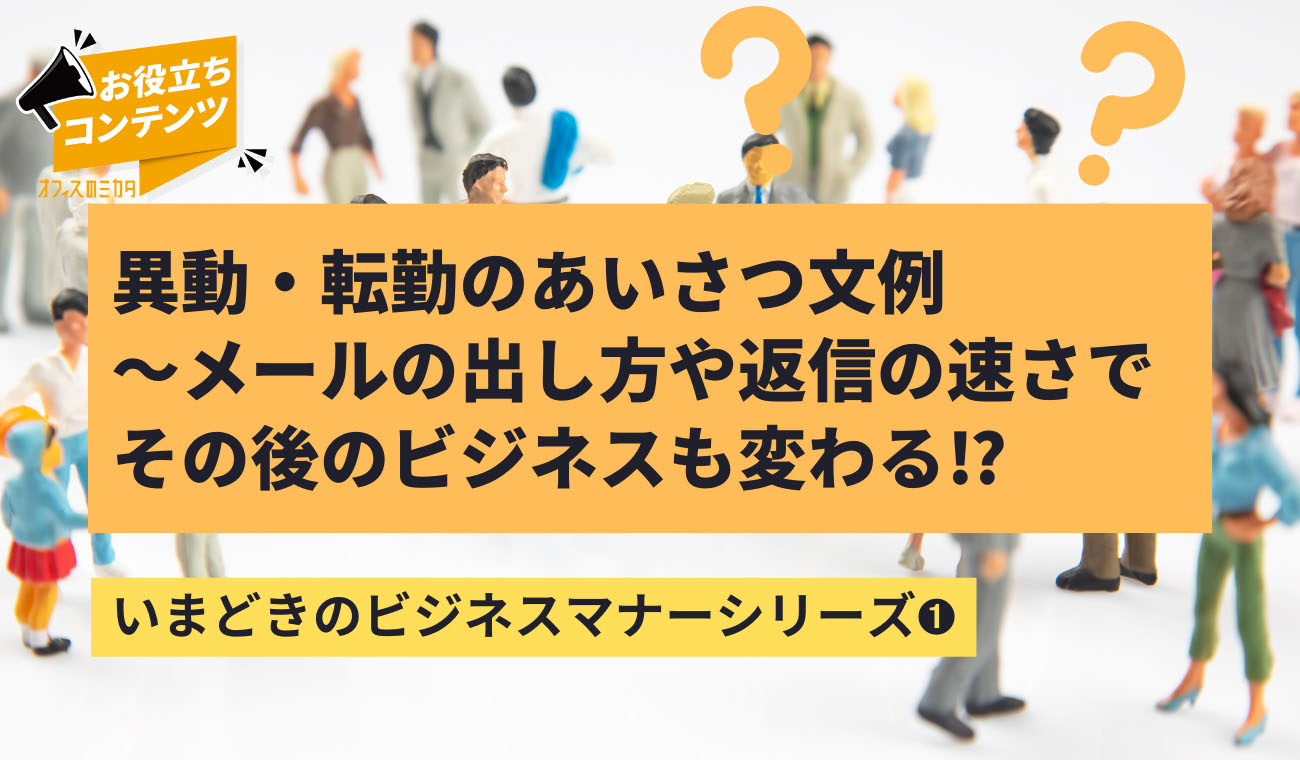中小企業は夏の賞与を支給する? 査定期間や注意点を解説~おさえておきたい!バックオフィスの基礎知識Vol.2

企業の業績指標である「賞与」は、適切な人事評価を行い従業員のモチベーションを向上させるためにも重要なものだ。賞与を支払うか否かや支給額は企業の裁量に委ねられているが、さまざまな査定方法があるため、どのように賞与額を決定すべきか頭を悩ませている担当者もいるのではないだろうか。
今回は、「おさえておきたいバックオフィスの基礎知識」の第2弾として、夏の賞与の算出方法を説明する。企業規模ごとの平均支給額や業種別の支給ランキングも紹介しているので、参考にしてほしい。
目次
●賞与の年間平均支給額
●中小企業における、夏の賞与支給額の状況
●賞与の決め方や査定期間は?
●新入社員への賞与
●賞与決定時の注意点
●まとめ
賞与の年間平均支給額
厚生労働省の資料によると、賞与は「定期または臨時に労働者の勤務成績、経営状態等に応じて支給され、その額があらかじめ確定されていないもの」と定義されている。一般的な企業の賞与はどの程度なのだろうか。まずは参考までに、民間企業における賞与の年間平均支給額や、業種別支給額ランキングを見てみよう。
【事業所規模別】賞与の年間平均支給額
国税庁が毎年実施している「民間給与実態統計調査」より、2022年の従業員(1年を通じて勤務した者)1人あたりの平均賞与額を事業所規模別に見ると、以下の通り。

(参照:国税庁「民間給与実態統計調査 -調査結果報告- 令和4年分」P18)
事業所規模別の支給額を見ると、事業所規模が大きい企業ほど支給額も多い傾向だ。後ほど詳しく説明するが、賞与算定の基礎となる給与のベースが、事業所規模が大きい企業ほど、高額であることに関係している。
【業種別】年間賞与の平均支給額
同調査を参考に、2022年の1年を通じて勤務した従業員1人あたりの平均賞与額(年額)を全事業規模で業種別にランキング化すると、以下のようになる。

(参照:国税庁「民間給与実態統計調査 -調査結果報告- 令和4年分」P20)
支給額が多いのは「金融業、保険業」や「電気・ガス・熱供給・水道業」といった社会インフラ系となっている。一方、支給額が少ないのは「不動産業・物品賃貸業」や「卸売業、小売業」などで、業種による差が大きいことがわかる。なお10位圏外だった業種では「農林水産・鉱業」が38万円、「宿泊業、飲食サービス業」が17万円となっている。
中小企業における、夏の賞与支給額の状況
前述したように、賞与額は事業所の規模によって平均額が異なる傾向がある。そのなかで、中小企業の賞与額はどのような状況なのだろうか。企業の場合、夏と冬それぞれに賞与を支給するのが一般的だろう。ここでは、中小企業における夏期賞与の平均支給額を紹介する。
中小企業における夏の賞与支給額
厚生労働省は「毎月勤労統計調査」を毎月実施し、半期ごとに従業員1人あたりの平均賞与額や前年比を公表している。この調査をもとに、2023年の夏季賞与の支給額を事業所規模別に見てみよう。

(参照:厚生労働省「毎月勤労統計調査 -令和5年9月分結果速報等」)≪特別集計≫令和5年夏季賞与(一人平均)
事業所規模が大きいほど支給額が高く、前述の年間賞与の平均支給額と同様の傾向となっている。また、いずれも前年比で2~3%以上のプラスに推移していることがわかる。
今年の夏期賞与の傾向は?
2024年6月に帝国データバンクが行ったアンケートによると、企業の39.5%が1人あたりの平均支給額を前年よりも「増加する」と回答した。「変わらない」としたのは34.2%。一方で、「賞与はない」と答えた企業は10.3%となった。
ただし規模別にみると、中小企業で賞与を「増加する」と答えた企業は38.2%、小規模企業では29.2%。大企業の47.2%を下回る結果になっている。
また、同アンケートによれば平均支給額の増減幅は、平均で+2.0%という結果になった。中小企業は+1.7%、大企業は+4.1%で、ここにも規模格差が見られる。
参考記事: 夏のボーナス、前年より「増加」が約4割~ 支給額は平均2.0%増、規模間格差が顕著~(TDB Economic Online)
賞与の決め方や査定期間は?
従業員への賞与支給額を決定するには、「賞与総額(賞与原資)」をもとに「支給月数」を定めたうえで「個別賞与」を決定するのがスタンダードな方法だ。それぞれの算出方法と、賞与の査定期間や新入社員に対する賞与の支給状況を見ていこう。
賞与総額(賞与原資)と支給月数の算出方法
「賞与総額(賞与原資)」とは、業績指標をもとに決定する、企業が賞与として支給できる総額のこと。業績指標は以下のように段階的に分かれており、どの段階を基準とするかは企業によって異なる。ただし、賞与は「利益配分」という性格が強いため、「営業利益」または「経常利益」をベースとするのが一般的だ。
・売上高
・売上総利益(売上高-売上原価)
・営業利益(売上総利益-販売管理費および一般管理費)
・経常利益(営業利益+営業外収益-営業外費用)
・税引前当期利益(経常利益+特別利益-特別損失)
・税引後当期利益(税引前当期利益-法人税など)
賞与総額(賞与原資)および従業員への賞与支給月数を決定するには、一律で支給月数を定めておく「給与連動型」と、業績に応じてその都度支給月数を決定する「業績連動型」の主に2つの方法がある。
多くの企業では「業績連動型」を採用し、「業績指標をもとに算出した利益比率」と「それに連動した平均支給月数(基本給比)」を定めている。例として、売上高に対する経常利益の比率に連動させた支給月数の例を紹介する。

個別賞与の算出方法
個々の従業員の賞与(額面)は、次の式で算出するのが一般的だ。
個別賞与額=基準額(基本給+役職手当等)×支給月数×評価係数
「基準額」とは、基本給に役職手当等の手当を加えたもので、どの手当を含むかは企業により異なる。「評価係数」とは評価基準をもとに係数を決めておくもので、「人事評価がSの場合の係数は1.2、Aは1.1、Bは1.0」とするなど、企業ごとに段階や係数を定める。
この方法以外にも、人事評価結果に等級別係数をかけた評価ポイントを用いて原資を配分する方法などもある。業績や「平等性」「スキル」「貢献度」などの重視したい項目によって算出方法が変わる。
賞与の査定期間
前述のとおり、企業には賞与の支給義務がないため、賞与の査定期間や支給時期についても各企業が独自に定めることができる。夏と冬の2回に賞与を支給する企業の場合、それぞれの査定期間を「10月から3月までの半年間」「4月から9月までの半年間」というように、一定期間を設ける場合が多い。
例として、夏の賞与を6月に支給する場合の査定期間は、「前年度の10月から3月までの期間」などとなる。このとき、査定期間と支給月の間に、評価を行うための期間をきちんと設けるのが大事だ。
新入社員への賞与
新入社員への賞与の有無や支給額は、企業業績や査定期間に在籍しているかがポイントとなる。例えば、夏の賞与支給日が7月で査定期間が前年度の10月から3月だとすると、4月に入社する新入社員は査定期間に在籍していないため、賞与は支給されないことになる。ただし、「寸志」として数万円を支給している企業が多いようだ。
なお、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」によると、2023年における大学卒の「年間賞与その他特別給与額」は、年齢・勤続年数ごとに以下のようになっている。入社後数カ月から1年の試用期間は査定期間に含まない、もしくは支給月数が少なくなる場合もあるため、新入社員が本格的に賞与を受け取れるのは入社1年目の冬、もしくは2年目からと言えるだろう。

(参照:「賃金構造基本統計調査 -令和5年」雇用形態別第2表 雇用形態、年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額)
賞与決定時の注意点
最後に、賞与を決定する際に気をつけるべきポイントを解説する。
就業規則への記載
賞与などの「臨時の賃金に関する事項」は就業規則の「相対的必要記載事項」に該当する。労働条件をめぐるトラブルを避けるためにも、就業規則に支給基準や支給時期、支給対象者、業績によっては支給しないことがある旨などを記載しておこう。記載文については、厚生労働省が公開しているモデル就業規則を参考にするとよいだろう。
なお、記載している査定方法を変えるなど現行の就業規則を変更する場合は、過半数組合または従業員の過半数代表者からの意見書を添付のうえ所轄の労働基準監督署に届け出る必要があることにも注意しよう。
参照:厚生労働省「就業規則を作成しましょう」
参照:厚生労働省「モデル就業規則について」
控除する項目に注意する
従業員への実際の賞与支給額は、先ほどの計算で求めた個別賞与額より1,000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」から、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)と源泉所得税を差し引いた金額となる。月々の給与支払時とは異なり、住民税は差し引く必要がないことに注意しよう。
まとめ
賞与支給額の算出方法は、企業によってさまざまだ。近年の新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化やテレワークの推進によって、評価制度や賞与制度の改正を検討することもあるかもしれない。今回紹介した内容を参考にしながら、企業と従業員が互いに納得できる仕組みを模索してみてはいかがだろうか。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする