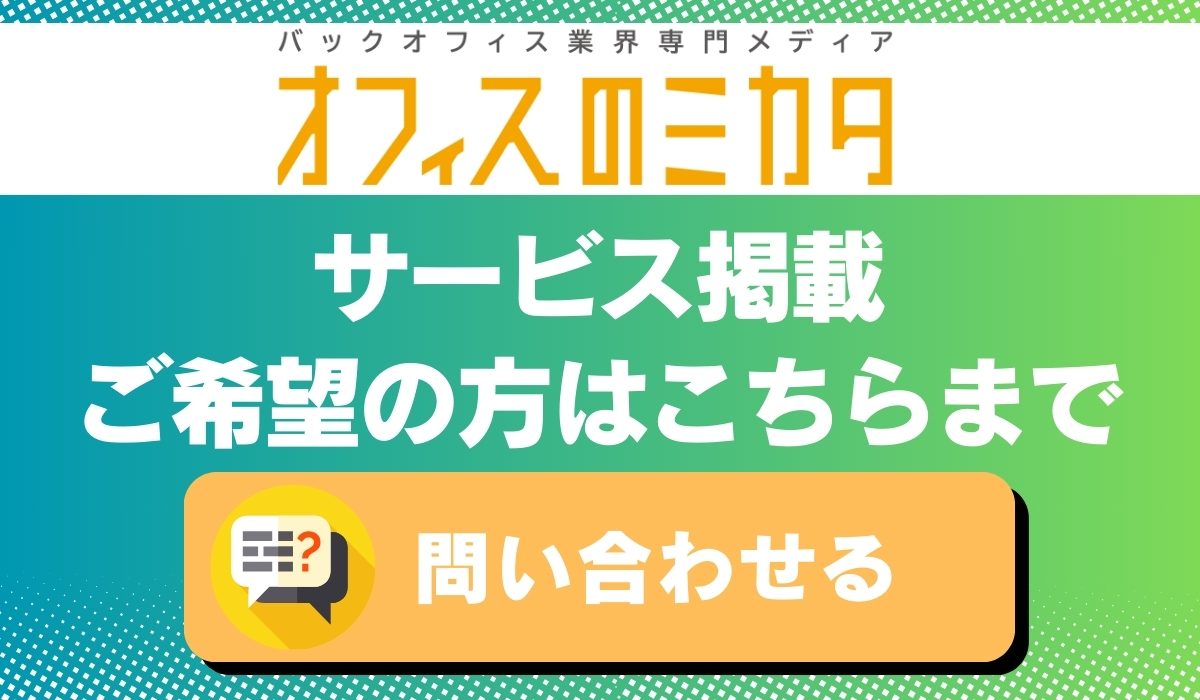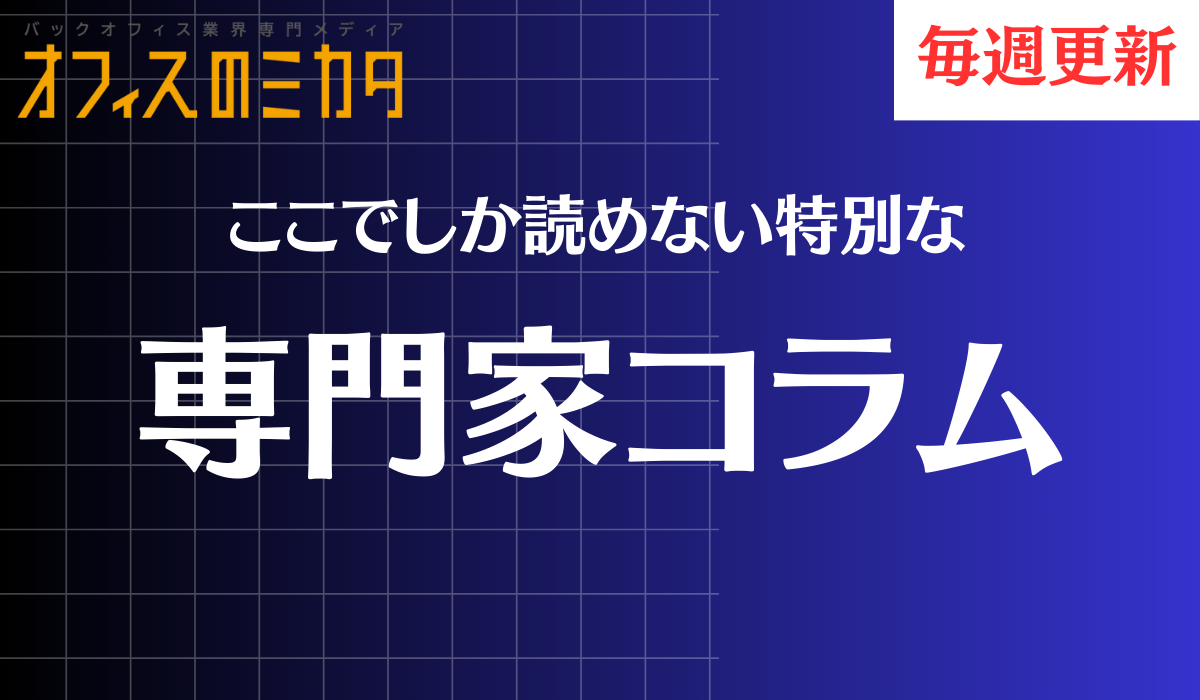原爆投下・終戦から75年。悲劇を後世に伝えることの困難に抗う

原爆投下から、そして終戦から、今年で75年。惨禍の歴史は、年々風化してきている。特に戦中・戦後世代が少なくなり、戦後生まれが後期高齢者となる現今においては、体験の「当事者語り」が聞けることはまれである。私の母方の祖父は長崎で原爆に遭い、被爆した。父方の祖父は人間魚雷回天(海の特攻)の乗組員だった。終戦がもう少し遅れていたら、父方の祖父は海に消えていただろう。母方の祖父も、原爆炸裂の瞬間、建物の中の別の場所にいたら、即死していたかもしれない。そうなれば当然、私はこの世に生まれてこなかった。
被爆3世の私に、いま何ができるか。風化にどう抗うか。今回は長崎での祖父の被爆史から書き起こし、思いをつづった。
長崎で原爆に遭う。被爆した祖父の証言の生々しさ
1945年8月9日午前11時02分、原爆が炸裂。その時、長崎県の香焼島から撮影された一枚の写真が残っている。同島から爆心地までの距離はおよそ10km。その写真をご覧いただければ、キノコ雲の巨大さに圧倒されるだろう。
試みに、直線距離で10 kmのところから撮影された東京タワーを見てほしい。

高さ333mの電波塔が、とても小さく見える。
一方、ほぼ同距離から撮影された原爆キノコ雲は以下である。「ニューラルネットワークによる自動色づけと手動補正」でモノクロをカラー写真化し、紹介している工学者・渡邉英徳氏から画像をお借りした。

規模が実感されるだろうか。
最終的にキノコ雲は、原爆投下機が飛んだ高度9,000 mを超え、14,000 mにまで達したという(※1)。
この雲の下に私の祖父がいた。工員として建物の中で働いていた祖父は、先輩から仕事を教わっていた。突如、窓にカッと閃光が走った瞬間、祖父は耳と目を手指で覆い、机の下にもぐったという。その瞬間のことは、それ以上記憶に残らなかった。
気づいた時には、机も、隣りにいた先輩も、周囲にいた他の工員も建物もすべて吹き飛び、わが身一つだけが焦土に残ったという。
祖父はただただ、爆心地から遠くへと走り始めた。周囲にはたくさん遺体。前を走る人たちは満身創痍だ。お腹の肉がごっそり欠け、臓腑をたらしている人。腕がおかしな形に曲がっている人。上半身の皮膚がほとんどはがれ、腰のあたりに垂れ下がっている人。
臨時救護所に着くと、祖父は看護する側に回った。重症者がうめき、次々と息絶えるそこは、まさに地獄だった。
その後、祖父は実家へ。驚いたのは、自分(祖父)の葬儀が終わっていたことである。「新型爆弾」の報を聞き、爆心地近くにいた祖父が幾日も帰還しなかったため、親族が「もう生きてはいまい」と弔ったというのだ。
私たちは、長崎を実戦被弾の最後の被爆地にしなければならない。どこの国であれ地域であれ、被爆が再び引き起こされることは明確な「悪」であり、悪魔の所業である。核兵器もまた、明確な悪であるとハッキリ断っておく。
さまざまな運動には「風化モデル」がある
戦争の悲劇を伝え残したい――。あまたの戦争経験者や関係者がそう思い、行動してきた。そして、その次の世代、また次の次の世代(そのまた次の――)が、思いを受け継ごうとさまざまに取り組んできた。私自身もそうだ。
しかし、「歴史」や「出来事に対する情念」「史跡」は、必ず風化する。ある程度はやむを得ない。それは多くの人が実感し、歴史も証明している。
たとえば東日本大震災について風化を感じている人は多い。被災地への目配せや復興の手入れも減少・弱化し、当事者その他の記憶も変容してきている。9年半の時を経て、記憶が薄れ人々から忘れ去られていく「忘却」が起きているのだ。そこに、ある種の「風化モデル」が働いている。
「売り家と唐様で書く三代目」という句をご存じだろうか。世代間での「しごとの引き継ぎ」が失敗に結びつくさまを皮肉った川柳である。一代目が残した財産を、初代の苦労を知る二代目が大きくしようとするも、三代目がその辛苦を知らないために財産を食いつぶすという話だ。初代が建てた屋敷が売りに出されてしまうので「売り家」とある。江戸時代に流行した言葉で、しごとの継承が三代目で切れることの多さがうかがえる。
社会学者・見田宗介氏は、この三代が克服すべきものとして、「欲望の粘着力」「システムの硬直性」「価値観の遅滞」をあげている(※2)。ビジネスを運動体と捉えた時に、できあがった運動に乗っかって「ほしいまま」に振る舞いたい、あぐらをかきたいという欲望への執着が「欲望の粘着力」だ。また、運動を駆動するシステムの官僚化・組織内文化の形骸化等が「システムの硬直性」にあたる。最後の「価値観の遅滞」は、世間の価値観を後追いするようになり、やがて時代についていけなくなる傾向をさす。これは、ビジネスという運動の衰退モデルである。
このモデルは、たとえば宗教運動にもあてはまる。宗教のライフサイクルに関するさまざまな研究成果(※3、4)は、宗教運動が継続していけば必ず、少なくとも「儀式等の軽視」「目的の置換(教団組織維持が目的となるなど)」に直面し、目的を見失うがゆえの「何のための運動か」という問い返しや、形骸化、硬直化を経験することを示している。それが、ただでさえ自然減する運動の担い手の熱量を押し下げる。驚くべきことに、この現象は政治活動等にも見られる、諸運動の普遍的な傾向といえる。
これが運動の「風化」だ。
戦争の悲惨さを伝える運動もまた、これと無縁ではない。
悲惨な歴史をストーリーで伝えることの必要性と危険性

「欲望の粘着力」に抗うには、でき上がった運動体で満足しないメンタリティが必要だ。
「システムの硬直性」に抗うには、新しいプロジェクト等を適宜生み出しつつ、それに合わせて組織機構を動かすことが必要だ。
「価値観の遅滞」に抗うには、時代の様相をつかみ運動の方向性を調整することが必要だ。異なるジャンルの運動との協同も、この点で模索されるべきだ。
今ここでこれらを詳細に吟味することはできないが、しかし、これらの前提となる「今すべきこと」が明確にあるので、それを書き記したい。
「あの惨禍を後世に伝える」という時に、私たちは「こういう悲惨な出来事があってね」と事実を物語化する。被爆者の証言、原爆ドーム等の遺物、当時の写真や映像、文書、そして建物の全壊率や死者数などのデータが素材になるが、それぞれが被爆の総体を表わすわけではないので、私たちはそこにストーリーテリングを施す。当然、後世へ伝えるためだ。
その際に大事なのは、ストーリーに回収する手前の「なまの声」、当事者との「なまの語らい・接触」を可能な限り残し、後々の世代が参照しやすいようにすることである。当事者が少なくなっている今となっては、これは時間との勝負になる。情報が残れば残るほど、そこから編めるストーリーも多角的になる(と、ここでは言い切る)。
今回この記事の冒頭で私の祖父の被爆体験をつづったが、そのストーリーには、国会図書館や長崎市図書館の資料館分室に所蔵されている祖父の証言や、私が祖父から直接聞いた話、他の親族が祖父から伝え聞いた話をまとめ、反映した。重層的にストーリー化した。改めてのこのたびのヒアリングで、私が知らなかった情報、証言集にも載っていなかった情報も得られた。情報は、あればあるほど良い。
ただし、注意も必要だ。実は、ストーリーテリングには危うさもある。物語化は得てして、出来事の中から印象深く重要とみなされるものだけを選び、筋が通るよう配列するという作業になりやすい。その過程で、物語の一貫性にとって障害になるものが排除されてしまうことがままある。
それを防ぐ意味でも「なまの情報」は多彩であった方がいい。それらが豊富にあれば、想像を膨らませて辻褄を合わせる無理やりさは減る。想像で埋め合わせる部分の多いストーリーは、ともすると妄想や作り話、極端なデフォルメの温床となる。特に、当事者が不在になり、「死人に口なし」状態になっていけば、デフォルメに対し「それは違う」と強度をもって違和感を述べられる人がいないため、想像の膨張に抑制がきかなくなり、それこそ「お涙ちょうだい」ストーリーに単純化され、曲解すらされてしまう(ただし、「お涙ちょうだい」ストーリーが優良コンテンツになるケースもあるため、ここは難しいところなのだが……)。
そうさせないために、「なまの声」、当事者との「なまの語らい・接触」を可能な限り残したい。
継承運動の要点。「これは、自分に関わることだ」と思わせる仕掛け
その上で、私が被爆の歴史保存に関わり、また多くの仲間と語らってきて実感しているのは、聞き手に「これは、自分に関わることだ」と思ってもらうこと、そして何か行動したくなるよう促すコンテンツを提供することの大切さである。コンテンツづくりに必須の要素は大きく3つあげられる。
①なまの情報、一次情報を可能な限り残す
②一次情報から、多様な知見、多彩な物語をつむぎ残していく
③受け手・聞き手が“私にとっての被爆”という物語を主体的に編める環境を提供する
①については前節で触れたが、再確認しよう。一次情報とは、たとえば「原爆ドーム」や「被爆時刻のまま針が止まった時計」といった遺物、被爆者の証言、当時の映像、写真、原爆投下をめぐる各種アーカイブ、死者数などのデータ、そして行政から一般人までさまざまな人が残した文書を指す。
これらを用いて、②の具現化、具体的には、警鐘碑・記念碑、資料館などでの展示、映画、小説、漫画、アート、教育コンテンツ、オーラルヒストリー研究といった多彩な形で展開を続けることが大切だ。
③は、草の根の啓発活動、教育、慰霊の祭や催し、マスメディアや政治行政などへの働きかけ、被爆時と「今」をつなぐ復興史、被爆者のその後の生きざまの描出などの形で行われている。特に、核軍縮や核兵器廃絶を目指すのに、ロビー活動や政治家の啓蒙、また被爆史を深く知るアクティビスト等の輩出は不可欠である。その際に、「これは、自分に関わることだ」と捉えてもらえる仕組みを用意することが大事になってくる。
かつて『世界がもし100人の村だったら』(※5)が一世を風靡したことを思い出す。同書が人々の心をとらえたのは、地球的な問題の巨大な数字を身近な数値に置き換えて表現したことによる。これは上記仕組みの好例だ。
本稿冒頭、東京タワーとキノコ雲を対比的に掲載したのも、「自分事」として読者に受け取ってもらえればとの意図による。「いま現在の東京に原爆が落ちたら……」と思わず想像してしまう仕掛けとして、わずかでも活きただろうか。
恐らく、工学者・渡邉英徳氏による「記憶の解凍」プロジェクト、戦時写真のカラー化も、近似した意図を持つものだと思う。近年、後世への悲劇の伝達は、たとえばダークツーリズム(※6)や当時の惨状・証言者の語りのVR(※7)による可視化、アーカイブのデジタル化とデータへのアクセスを容易にする環境整備、わかりやすいインターフェースなどが模索され、これらの取り組みも「種」が植わり、「芽」が出始めている。
被爆者の言葉を、そうでない人に理解できるかたちに翻訳する「通訳」に

悲劇の風化は止められない。だが、無抵抗ではいけない。あたかも正義に正解がないからといって正義に無関心でいることがナンセンスであるように、風化への抗いも、風化が止められないからといって何もしないのはナンセンスである。私たち個々人は微力で、歴史に翻弄される一個体かもしれない。しかし、地道に延々と抵抗していくこと自体が「新たな啓蒙」の第一歩であるという現実は変わらない。
ある被爆者の言葉が私の胸を打つ。
「(他の多くの被爆者の体験を聞いて)被爆っていうものが、原爆っていうものが、どんなにひどいものかを、だんだん知るようになって。知らなかったっていう部分が、私でもいっぱいあるわけですよね。そうするとね、あのお、まあ別の表現で言えば、被爆者として深まっていくっていうか。より被爆者になっていくって言ったらいいんでしょうか」(※8)
被爆した人が、当初から被爆意識を持っていたわけではない。被爆意識は、時間をかけてつくられた。被爆者は、多くの情報や証言に触れ、被爆者としてのアイデンティティを確立していった。その経験があるからだろう。上記の被爆者はこうも語っている。
継承することとは?――「とにかく自分の体験と重ね合わせるという、重ね合わせながら、その話を、被爆者の話をきっかけにしながら、その人の痛みであったり、苦しみであったりしたものを、イメージするというのかしら。イメージしながら、そういうものを、その人の体験を、まあ追体験するという。そういう営みっていうか、作業というか」(※9)、それが継承を意味すると思う、と。
被爆者の痛みや苦しみに共感し、追体験するようにして、自身の人生の中に「被爆」を位置づけ、自らのアイデンティティの支えにしていくこと、それが継承になるという。それは、被爆経験がなくても可能かもしれない。「被爆者と同じ怒りは持ち得る」と、反核運動で著名な故・鎌田定夫氏は語っている。彼には、被爆経験がない。そんな彼が、若い世代への継承について、「自分たちの日常体験のなかに翻訳できなければ、昔のことを昔のこととして語るだけでは、伝わらないんですね」。大事なのは「自分の原点で翻訳すること」「立場を入れ替えて共感し、共有すること」(※10)と指摘した。
自身のライフストーリーの中に被爆を位置づけ、忘れ得ぬこととして心に刻み、被爆者の言葉を、被爆していない人たち・世代に理解できるかたちに翻訳する、いわば「通訳」の役割を担える人材を育てることが大切なのだ。また、それが「可能である」ことを、鎌田氏は教えてくれる。
私も、これに共鳴しつつ、これからも問題にコミットしていく。
皆さんは、どう考えるだろうか。
[脚注]
(※1)サイト「長崎市 平和・原爆」より
https://nagasakipeace.jp/index.html
(※2)見田宗介ほか『二千年紀の社会と思想』太田出版、2012年
(※3)森岡清美『新宗教運動の展開過程─教団ライフサイクル論の視点から』創文社、1989年
(※4)西山茂「運動展開のパターン」、井上順孝ほか編『新宗教事典』所収、弘文堂、1990年
(※5)池田香代子『世界がもし100人の村だったら』ダグラス・ラミス対訳、マガジンハウス、2001年
(※6)災害被災跡地、戦争跡地など、人類の死や悲しみを対象にした観光のこと
(※7)バーチャル・リアリティ。現物・実物ではないが、五感を含む感覚を刺激することで、あたかも現物・実物に接触しているかのような環境をつくり出す技術およびその体系
(※8)高山真「原爆の記憶を継承する」、桜井厚ほか編『過去を忘れない――語り継ぐ経験の社会学』せりか書房、2008年、( )は引用者
(※9)前掲書
(※10)中村尚樹『「被爆二世」を生きる』中公新書ラクレ、2010年、趣意

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする