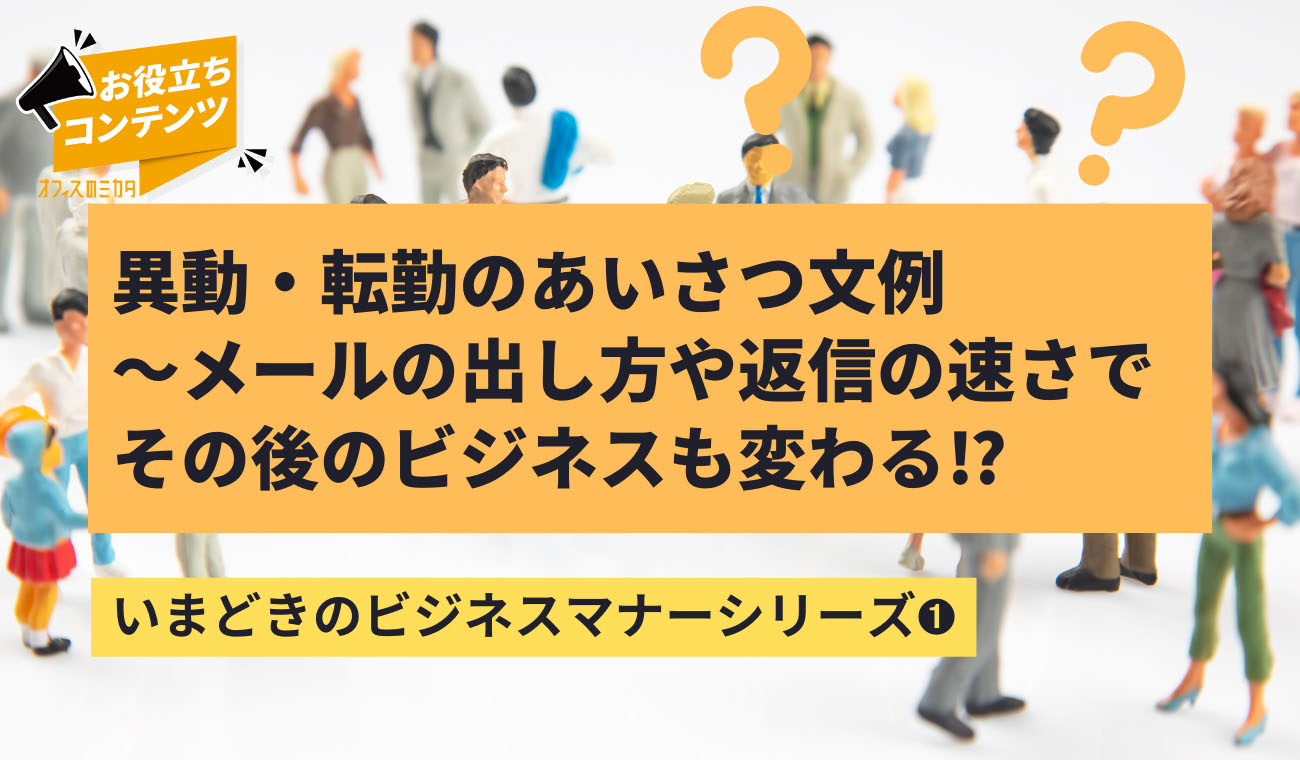DXは成長のための変革 デジタル庁の組織開発担当者に聞くDX推進のポイント

DXの必要性が叫ばれて、2025年問題も迫る中、DXに課題を抱える企業も多い。そんな状況で行政のDXを推進すべく、2021年9月にデジタル庁が発足した。DXの急先鋒ともいえるデジタル庁で人事・組織開発を担当する唐澤俊輔氏に、変革を伴いDXを推進する企業のあるべき姿について伺った。
いま求められる顧客のための変革

経済産業省は、2018年にデジタルトランスフォーメーション(以下:DX)の実現と推進に向けた『DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート〜ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開〜』を発表した。この「DXレポート」には、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの創出や、商品、サービス、業務プロセスなどの変革による競争の優位性を確立するための課題や指針が示されている。これを皮切りに、日本の各企業でDXに向けた動きが活発になった。そして、2020年には新型コロナウイルスによるパンデミックが発生。感染拡大の防止策として、各社でペーパーレス化やオンライン会議などが余儀なくされ、デジタルツールの導入が急速に進んでいる。
しかし、デジタルツールを導入するだけではDXとはいえない。実際、デジタルトランスフォーメーションという言葉の「トランスフォーメーション(変革)」の部分、つまり「商品やサービス、ビジネスモデル、業務プロセスの変革」の要素が、日本では忘れられがちだ、と唐澤氏は指摘する。現状では、単なる「デジタル化」や「IT化」にとどまってしまっているというのだ。
「なんのために変革する必要があるのかというと、それはお客様のためです。官公庁であれば国民であり、企業であれば顧客。お客様への提供価値をしっかり上げていくことが大切です」(唐澤氏)
デジタルをツールとして活用しつつ、それによって社内の業務プロセスやバリューチェーンなどを抜本的に見直して、アップデートする。こうした業務全体の構造改革による提供価値の向上が、DXでは求められている。
社会を大きく変革するデジタル領域
そもそも、なぜデジタル化が重要なのか。デジタルツールの活用はイノベーションを起こし、新しいビジネスの形で社会を変容させ、生産性を大幅に上げていく可能性があるからだ。
「例えば、航空会社でいえばチケットレスやオンラインでの購入、チェックインの自動化といったデジタル化が進んでいます。しかし、オンライン通話アプリの登場によって、出張が激減し、航空機の利用は大幅に減ってしまいました。今の社会では、ここでいうオンライン通話アプリのようなイノベーションが求められているのです」(唐澤氏)
デジタル化によって、こうした社会の変容が起こる。日本は世界の中でもデジタル化が遅れてしまっているのが現状だ。しかし、デジタル化を進めるとともに、さらにこのような変革をさまざまな環境で起こしていくことが強く求められているのだ。
ところが、日本企業のデジタル活用は、効率化ばかりに目が向きがち、と唐澤氏は話す。例えば、ペーパーレス化によって紙の使用が減れば、コストを下げられて効率的だ。しかし、ペーパーレスそのものが顧客への提供価値につながるか、といった視点は置き去りになっていないか。現状、日本では各企業でデジタルそのものへの投資はなされている。しかし、効率化ばかりに注力し、顧客への価値を生み出す視点が不足し、デジタルツールの導入が新たなサービスの創出にまでつながっていないケースが多いという。
「DXで求められるのは、抜本的にプロセスを見直すことであり、その先の顧客への提供価値の向上、売り上げの増加、そして再投資、という一連のサイクルです。デジタルツールの活用は、あくまでもそのための手段です」(唐澤氏)
今の日本では、社会全体が変容するような、大きなアウトプットを生み出せていない。既存のビジネスでは、イノベーションを生み出すことが難しい。効率化にとどまらず、新たなサービス開発の下でイノベーションを起こしていくことが、生産性を向上させ、日本企業の競争力を高めていくために必要なのだ。
適切なプロセスへの移行が成長につながる

業務プロセスの見直しも重要な視点だ。多くの日本企業では、既存の業務プロセスに合わせて、システムを作っていくことが一般的なスタイルである。しかし、それでは、既存のプロセス自体が、そのままオンライン化されてしまう。そのため、開発に時間や投資がかかるにも関わらず、業務プロセス自体の改革にはつながらない。
ソフトウェアにおけるSaaSの導入という面でも、日本と海外の違いは明らかだ。海外では、ブラウザ上で動作するアプリケーションをベンダー企業が提供するSaaSモデルによってビジネスプロセスが改善されるとなれば、自社でソフトをインストールして管理する従来の形からSaaSに変えていくことも一般的だ。一方、日本では既存のプロセスと合わないために導入を見送るケースが多い。そして、結局はそのために既存のレガシーなシステムを背負ったまま、成長が遅れてしまっている。
人口の問題も重要な課題だ。労働力としての人口が減ることもさることながら、消費する人口が減ることの打撃も大きい。高度経済成長期には、現状維持でも人口が増えることによって、自然と成長につながっていた。しかし、人口が減り続ける現代においては、現状維持ではマイナスとなる。人口減によるマイナス以上のプラスを創出するためには、生産性を高めながら、成長に寄与することが求められる。唐澤氏が強調するように、DXの本質は、ビジネスプロセス全体を抜本的に見直し、デジタルをベースにした適切なプロセスへ変えていくことにあるのだ。
DXの鍵はトップのコミットとプロジェクトベースの組織
民間からの兼業人材である唐澤氏は、これまで、各社で人材育成や組織開発に取り組んできた。その知見から、DXを推進するための組織づくりのポイントもお話しいただいた。
DXを進めていく上で最も重要なのは、トップのコミットメントだと唐澤氏は言う。DX担当を決めて任せきりということでは、DXを推進することはなかなか難しい。ビジネスプロセスを変える段階時に、現場部門から既存のプロセスと違うからできないと言われてしまうからだ。現場部門はこれまでの経験が身に付いているから、既存のプロセスの変更には抵抗がある。それは構造上仕方がない。そこを理解しながら推し進めることができるのは、トップだけだというのだ。デジタル庁も、当時の菅総理大臣のもと、トップの強いコミットメントにより設置された。
「次に求められるのは、横断的に取り組むための組織づくりです」と唐澤氏。従来の業務プロセスごとに縦割りになっている組織構造から、横断的に取り組む体制づくりへの変革が重要となる。DXの推進という観点でも、顧客価値の向上のためにも、「どの段階でどのようにデジタルを活用していくか」という議論が不可欠だ。そのためには、いろんな部門の人材が入ったチームの組成が求められる。そのようにしてプロセス全体を横断するプロジェクトにしながら、新たに組織を構築していくのだ。
デジタル庁でも、プロジェクトベースの組織づくりに取り組んでいる。例えばワクチン接種証明アプリの制作時に、プロジェクトを立ち上げてチームに専門人材を登用した。エンジニアやデザイナーといった民間の専門人材と、役人が協働できるように、さまざまな部門の人材でチームを組成していく。プロジェクトごとにそのようなチームをつくって機動的に回している。
さらに、組織の改変に伴う、人事制度など組織基盤の見直しも忘れてはいけない。プロジェクトベースの組織では、それぞれのメンバーが複数のプロジェクトを兼務する。その中で、誰が全体を把握し上司として面倒を見て評価するのか、という視点で仕組みをつくり直しているところだ。
多彩な人材が活きるイノベーティブな仕組みづくり

DX推進の突破口として、まず取り組むべきだと唐澤氏が言うのは、専門人材の採用だ。デジタル庁でも、まずリードリクルーターを採用して民間人材の採用に向けた準備を行った。専門人材が入ってくることで、最初はかみ合わない部分などが当然起こりうるが、徐々に化学反応が起き始めるという。専門人材をきちんと採用することで、専門的な知見からアドバイスすることが可能になり、周囲の人材は専門人材と一緒に実践しながら学べるので育成にもつながる。
こうした専門人材は給与水準が異なる場合があるため、人事制度や報酬制度も、それに沿った形になっている必要がある。最近は、年齢や勤続年数に関わらず担っている役割に応じて給与が決まる、いわゆるジョブ型の雇用形態に移行している企業も増え始めている。ジョブ型雇用の場合、管理職の下の高度専門人材は、役割が違うから給与が逆転していてもいい。そのように、管理職でなくともきちんと報酬を出して登用し、成果が出せる報酬体系を整備することが求められる。さらに、専門人材は、従来の縦割り組織のルールの下では、パフォーマンスが活かせないことも多い。そのため、自律的でそれぞれのパフォーマンスを高めることのできる環境を整えることも欠かせない。こうした人事制度や職場環境全体の見直しが必要になってくると、唐澤氏は話す。
イノベーションを起こさせるには、多様性を受け入れることも必要不可欠だという。
「従来の日本企業は、凝集性が高い。その会社らしい人材が育っていくことで、阿吽の呼吸で、説明なく動けることがメリットでした。しかし、イノベーションを起こすためには、社内の人材の思想が、似通って近いものになりすぎると難しい側面があります。一方、多様な人材が入ってくると、前提が違いすぎて議論がかみ合わず、平行線で進まないこともあります。そのため、個々の判断で迷ったときに、判断軸になるものを設定することが必要となるのです」(唐澤氏)
そこで重要なのが、「ミッション・ビジョン・バリュー」だという。デジタル庁には、官民合わせて約600人が集められた。民間出身人材としても、大企業からベンチャーまでさまざまな業種から登用された。役人も同様に、各省庁から出向してきている。そのため、人によって背景も経験もバラバラ。だから、目的を可視化することで、それぞれの目線を揃え議論できる環境を整えるのだ。デジタル庁でも発足前から3カ月かけて、ミッション・ビジョン・バリューの策定に取り組んだ。
さらに必要なのが、情報共有の仕組みづくりだ。このような組織でプロジェクトができて動き出すと、中間管理職は自分のプロジェクトに加えて部下のプロジェクトも把握する必要が出てくる。いままでのやり方では到底やりきれないので、ビジネスチャットのような可視化された環境でオープンに会話し、最新の状態を常に共有できる仕組みを整えることが欠かせないという。
行政のDXと人材育成のハブとなるデジタル庁

日本のDXの急先鋒に立つデジタル庁。今後も各省庁と連携し、行政そのもののDXを図っていく予定だ。スタートアップでありサービスを提供する行政であるとして、「Goverment as a Service、Goverment as a Startup」というビジョンを掲げている。行政を国民や企業に対するサービスの提供者とし、スタートアップらしく大胆に新しいことに取り組んでいく。
また2021年12月には「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が策定された。その中で「デジタル人材の育成」を柱として掲げている。「デジタル庁自身が、デジタル人材の能力を最大限生かし、引き出せる組織になるとともに、多様な経験を積むことが可能な場になること」を目指しているのだ。こうした狙いから、デジタル庁では、リボルビングドアを組織づくりのコンセプトとしている。リボルビングドアは回転ドアという意味で、民間企業と官公庁との間で、流動的に人材が行き来する仕組みだ。民間企業出身者は、官公庁や伝統的日本型組織の仕組みを学び、行政の職員は、民間企業の持つ先端技術や仕事の進め方を取り入れることができるというメリットがある。それぞれの人材が、デジタル庁で2・3年経験を積んで成果を上げ、知見を残し、デジタル人材として元の組織に帰っていく。それにより、どういったプロセスでデジタル化を進めればいいか、官民それぞれのDXを進めるための人材を輩出していく、そのハブとしての機能をデジタル庁が担う形だ。
デジタル庁600人の育成と行政のDX化。それだけではなく、国民1億2千万人を、誰一人取り残すことなく、デジタル化を推進する。これがデジタル庁の担う重要な役割だ。変革を伴うDXをそれぞれの企業で推し進めながら、日本のDXの行く末とともに、それを牽引していく今後のデジタル庁の動きにも注目したい。

 ツイート
ツイート


 シェアする
シェアする