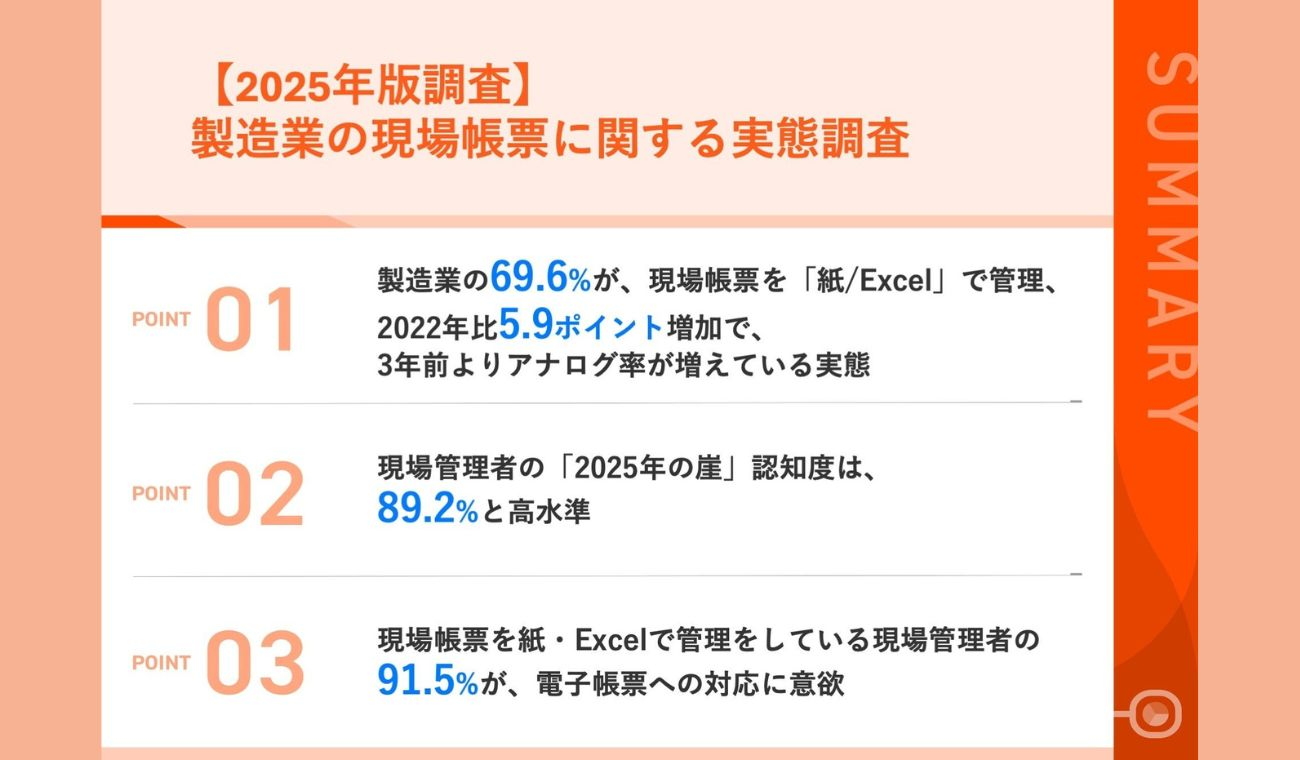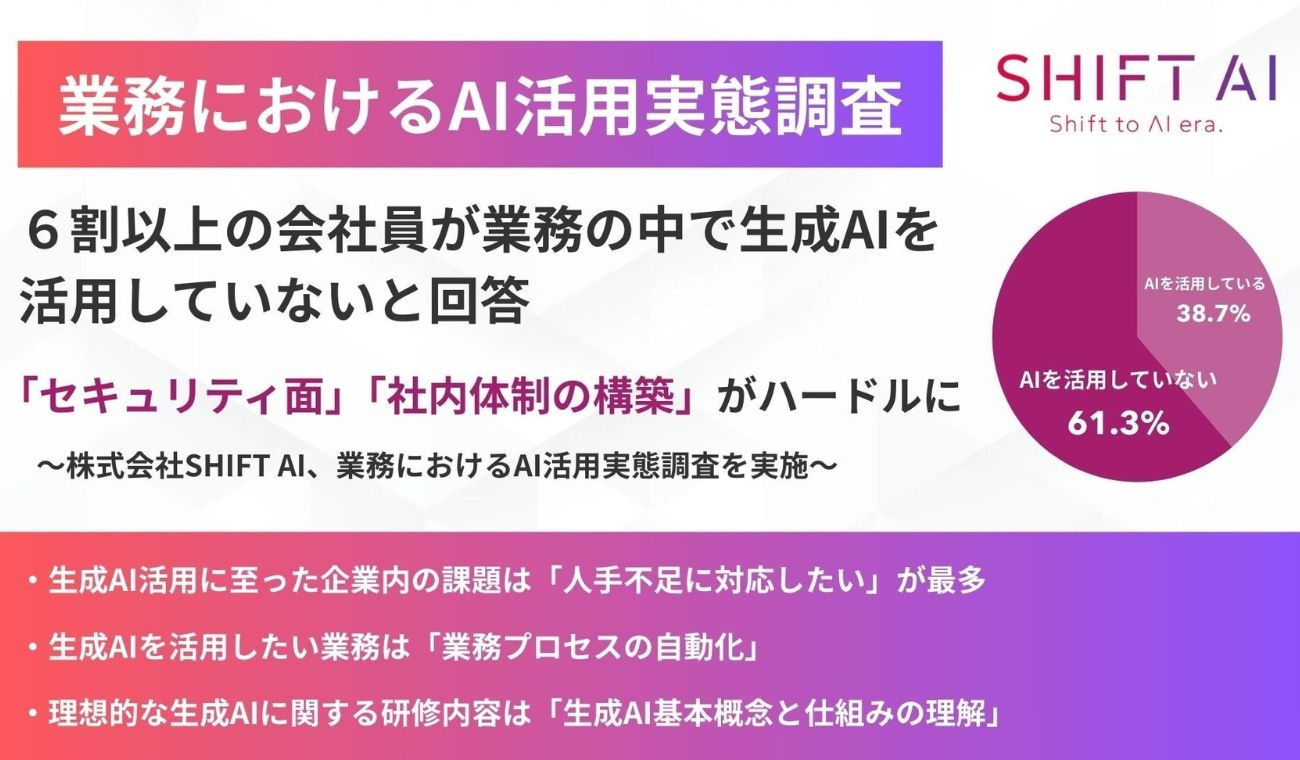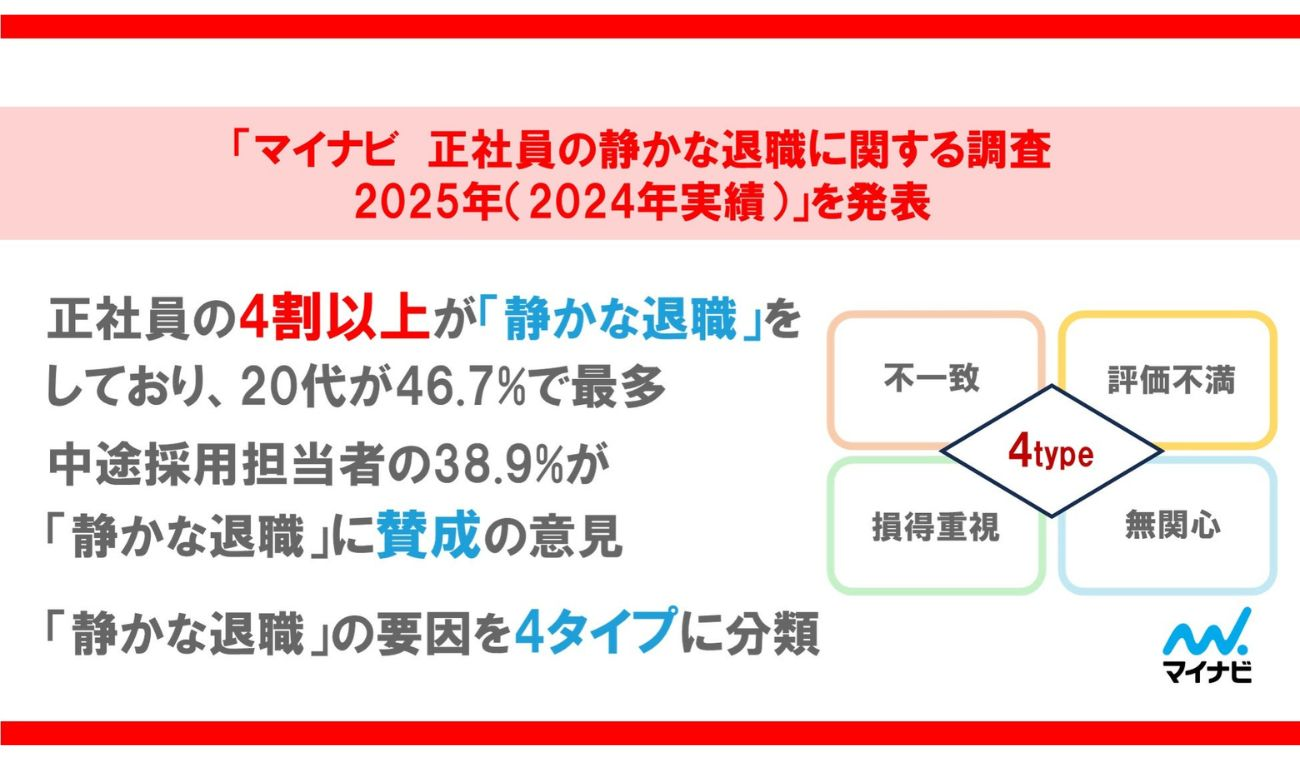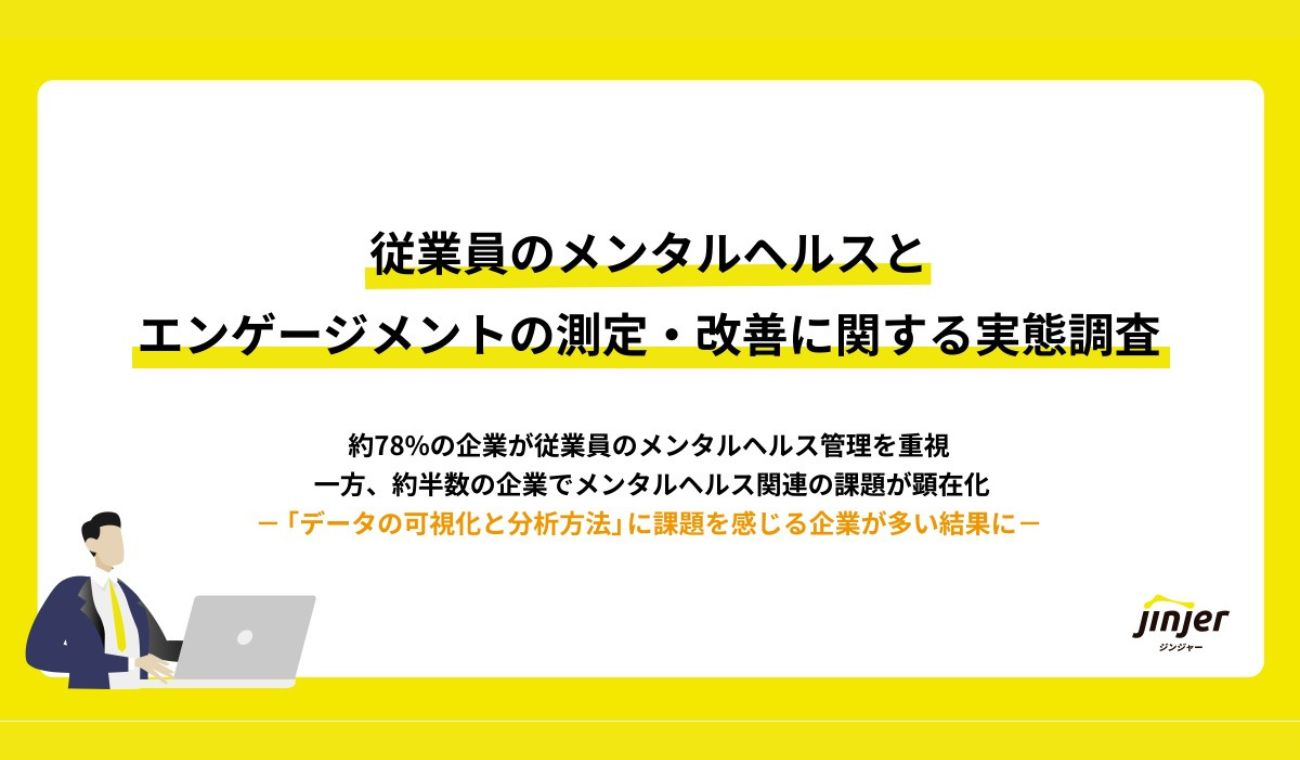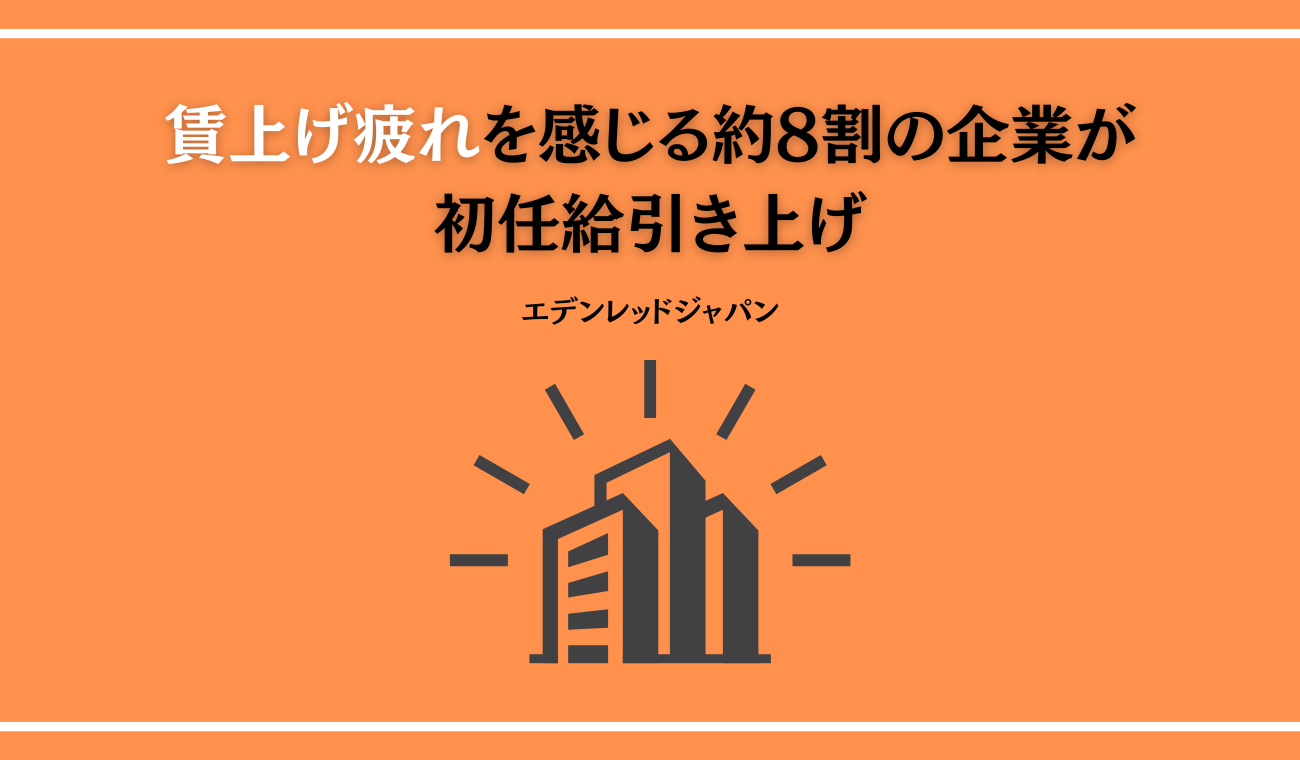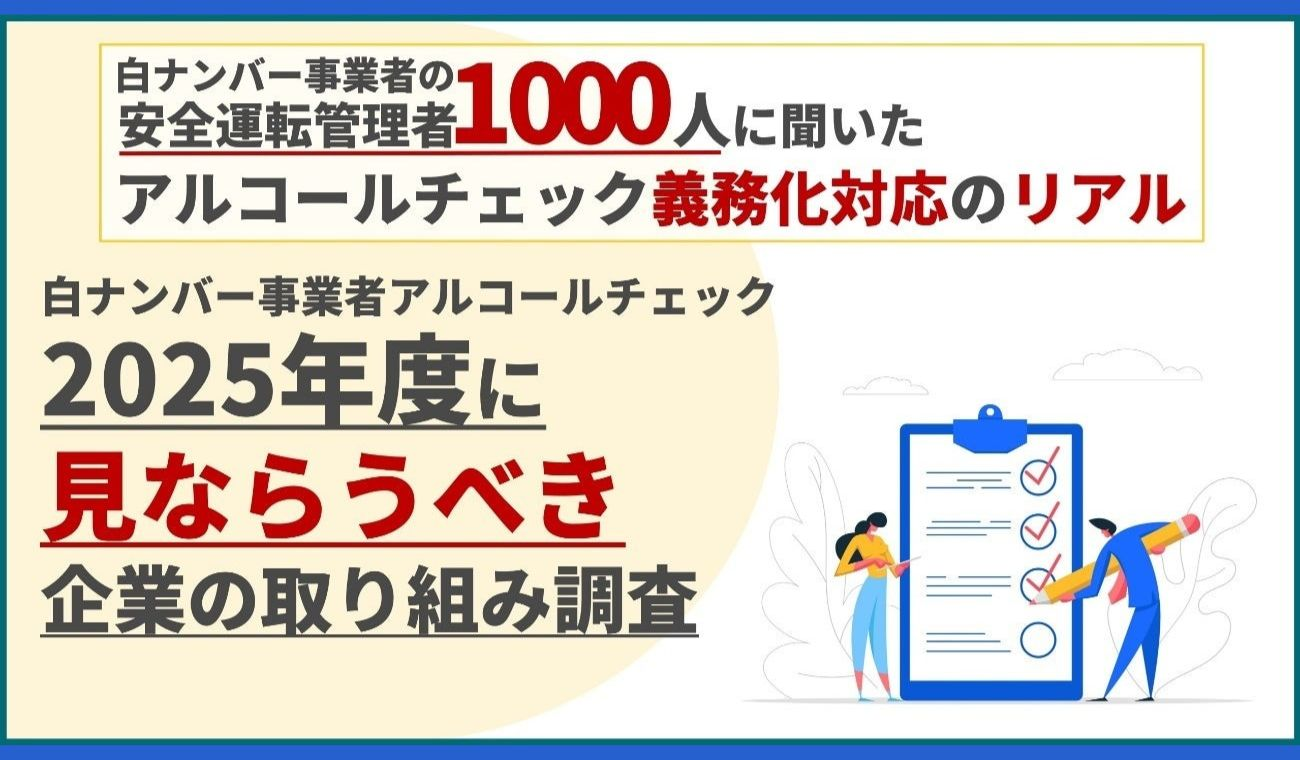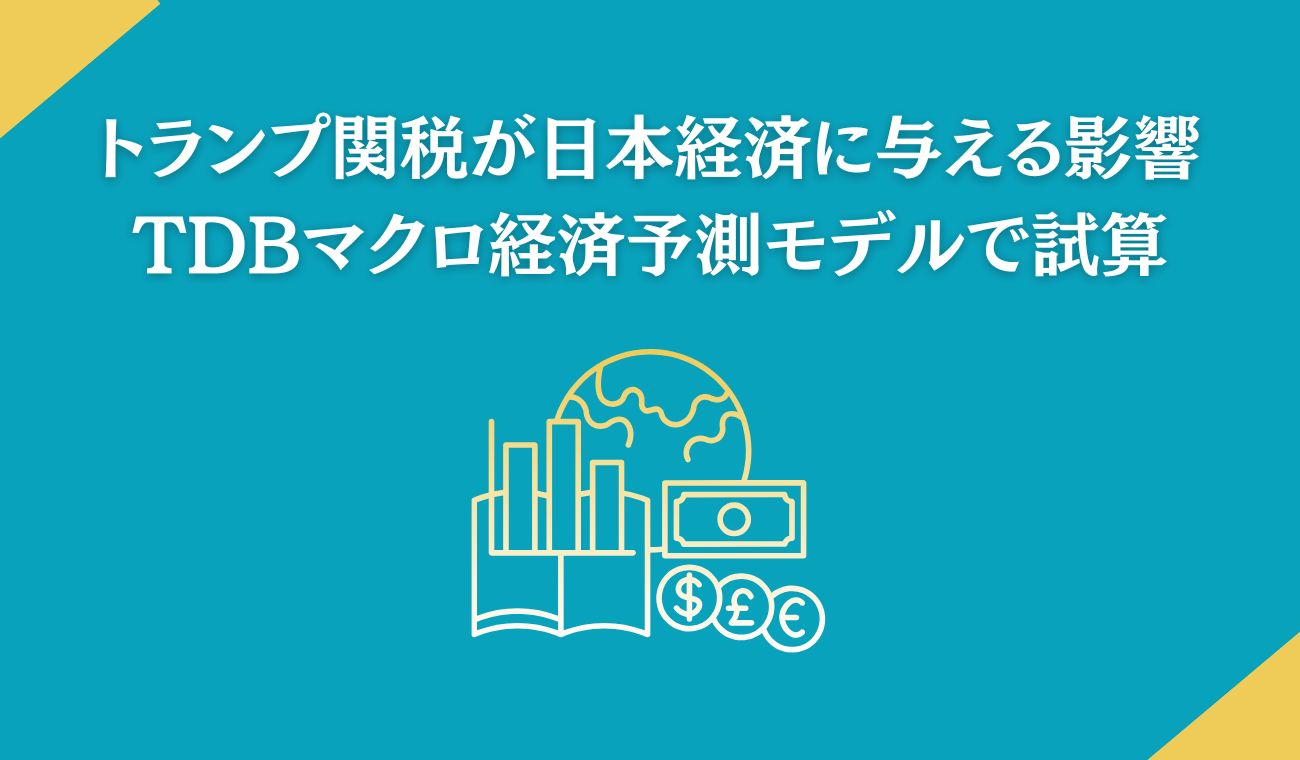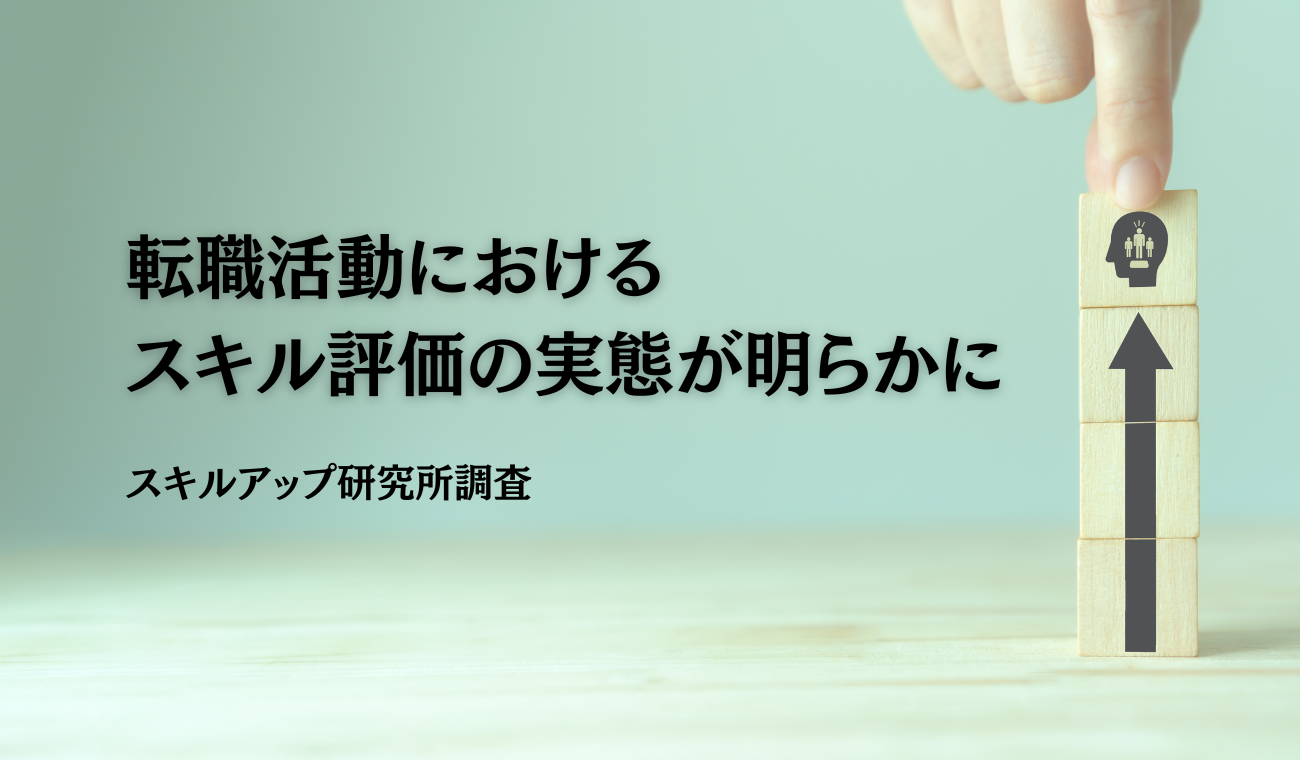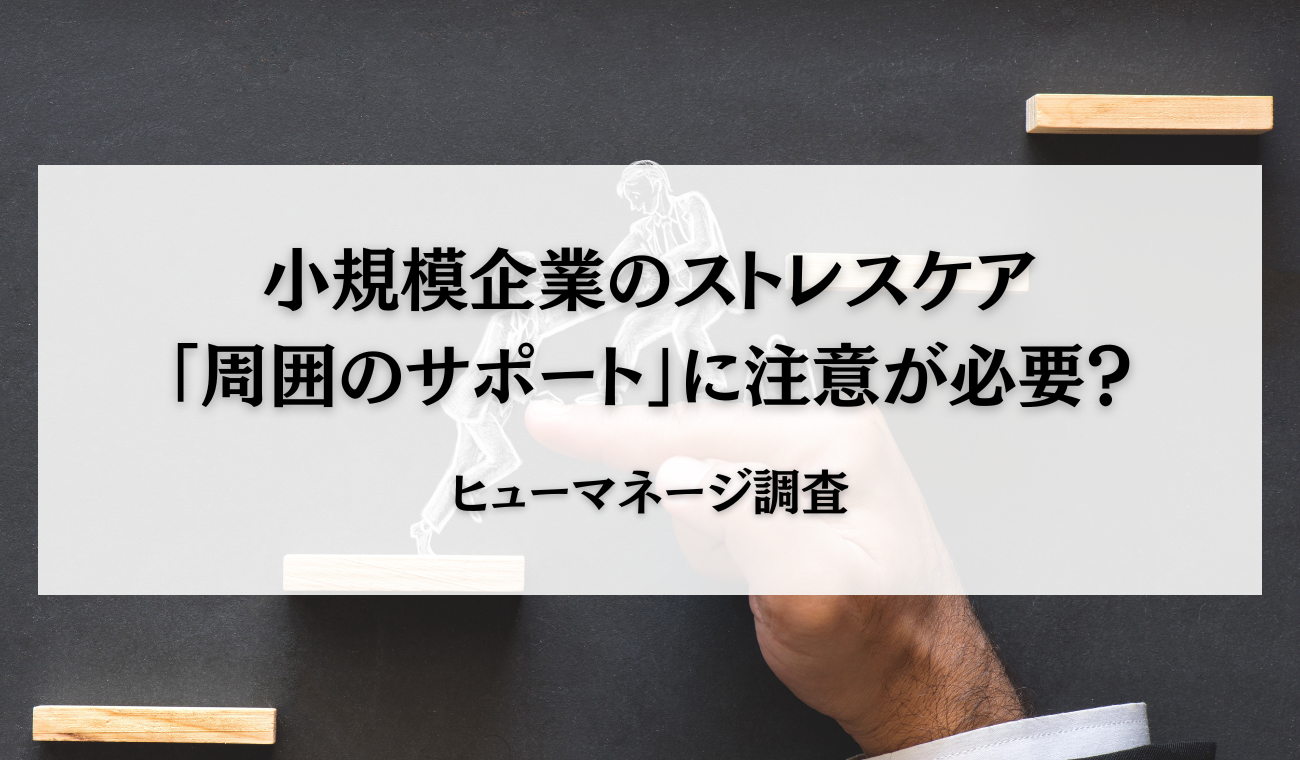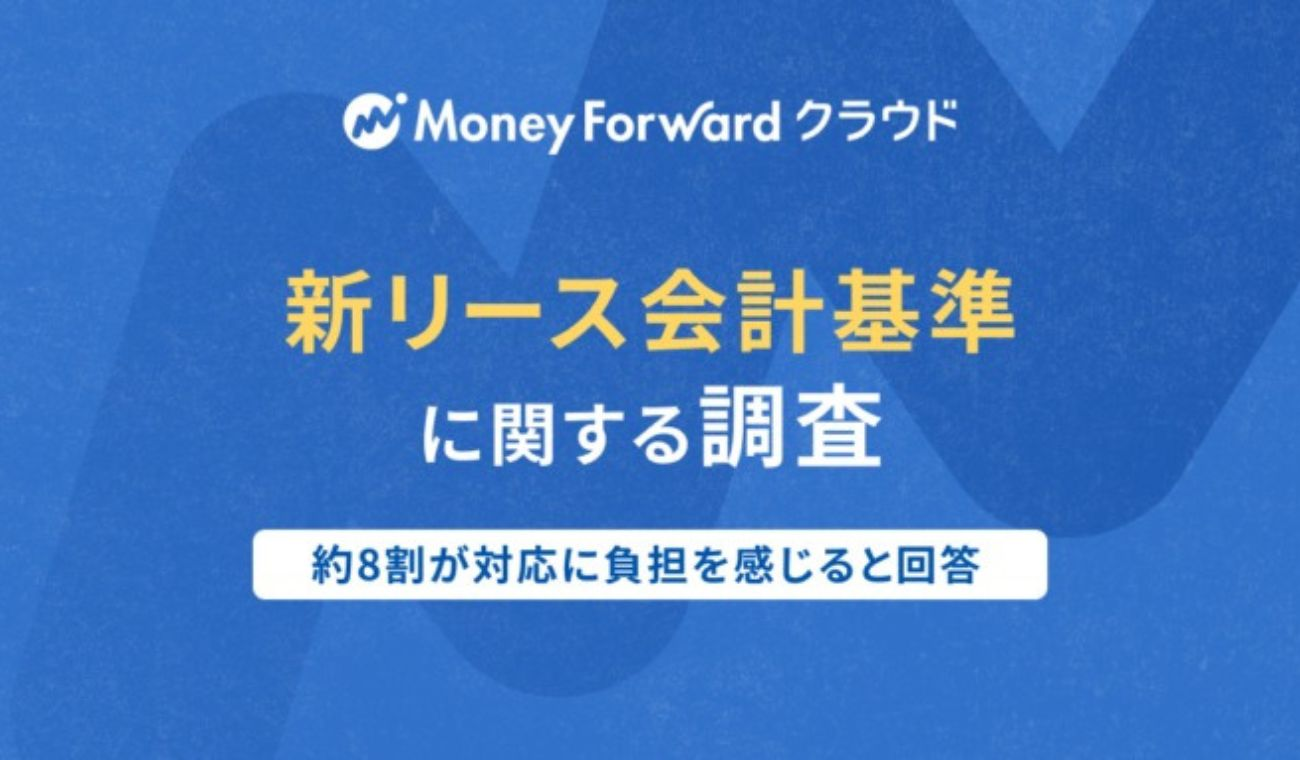働く女性への健康支援には発展の余地あり グッドアンドカンパニー調査

株式会社グッドアンドカンパニーは、自社プロジェクト「W society(ダブリュー ソサイエティ)」が、⼀般社団法⼈ ⽇本経済団体連合会 ダイバーシティ推進委員会が実施した「⼥性の健康」に関する調査に協力したことを発表。同プロジェクト参画企業であるオルガノン株式会社の協力を得て調査を設計し、企業における、⼥性の健康⽀援制度の導⼊率や活⽤実態、経営層と現場の認識のギャップ、さらに⼥性の健康⽀援が企業の成⻑や組織⾵⼟に与える影響について明らかにした。ここでは調査結果から一部を抜粋して紹介する。
調査概要
調査実施主体:⼀般社団法⼈ ⽇本経済団体連合会 ダイバーシティ推進委員会
調査⼿法:インターネット調査
調査対象:経団連ダイバーシティ推進委員会、同企画部会所属企業
実施時期:2024年12⽉13⽇〜2024年12⽉26⽇
回答件数:96件
出典元:「女性と健康」に関する調査結果(⼀般社団法⼈ ⽇本経済団体連合会 ダイバーシティ推進委員会)
女性への健康支援を実施する企業は9割超も低い利用率が判明

本調査ではまずはじめに、企業がサポート可能だと考える女性の健康課題について質問。その結果、上位には「月経にまつわる不調(83.3%)」「子宮筋腫、子宮がん、乳がんなど女性特有のがん(59.4%)」「更年期に関連して生じる不調(53.1%)」が挙げられている。
続いて本調査では、女性の健康支援の実施状況について質問しており、95.8%の企業が「実施している」と回答したことが明らかに。一方で、女性へのサポート状況についての進捗状況を尋ねる項目では「進歩的である」と回答した企業はわずか25.0%だったという。なお、62.5%が「一般的である」と回答している。
また、女性の健康支援の実際の利用状況については、多くの企業が「利用率10%未満」または「利用実態を確認したことがない・分からない」と回答。十分に活用されていない現状が明らかになった。
経営層の3割超は「支援が浸透している」と評価も、現場の実感と乖離

続いて本調査では、女性の健康支援に対する経営層および一般従業員層の理解度について質問。経営層では32.3%が「総じて浸透している」と回答したものの、一般従業員層では41.7%が「一部に浸透しているが、大半は浸透していない」と回答したことが明らかになった。
同社はこうした経営層と現場のギャップを埋めるための手段として、社内アンケートの活用を挙げている。しかしながら本調査では、社内アンケート結果の共有範囲について尋ねる項目で「従業員へのアンケート/ヒアリングを実施していない、または状況を把握できていない」との回答が36.5%にのぼっており、実態把握の不足が課題だと指摘した。
女性の健康制度導入が進まない理由と導入による影響

次に本調査では、女性の健康支援に関する制度の未導入・未実施の理由について質問。「制度設計が困難なため(20.8%)」「社員からの要望がないため(14.6%)」「リソース不足のため(12.5%)」などが上位に挙げられたという。
また、女性の健康支援がもたらす影響については「社員の生産性向上につながる(52.1%)」「女性社員定着率の向上につながる(22.9%)」といった声が多いことも判明。女性の健康支援が経営への直接的なメリットがあると認識されているようだ。
さらに本調査では、女性の健康問題に関する取り組みの位置づけについて質問しており「DEI/女性活躍の取組みとして位置付けており、経営全体としてのゴールは設定していない(76.0%)」との回答がトップに挙げられている。「経営戦略の上位に位置付けており、具体的な経営目標を設定している」との回答はわずか11.5%にとどまったという。
まとめ
本調査ではほとんどの企業が女性に対する健康支援に取り組んでいることが判明した。一方で、進歩的な取り組みや現場への浸透については不十分な実態も明らかになっている。女性の健康支援が経営に直接的なメリットをもたらすと認識されながらも、制度の利用率は低いとの調査結果も出ており、より使いやすい制度としていくことの重要性が示唆された。
「従業員へのアンケート/ヒアリング」について、本調査では多くが実施していない(把握できていない)と回答している。実態の把握と制度の改善において、実際に利用する従業員の声を聞くことは欠かせないはずだ。今後より良い制度としていくためにも、ぜひ実施を検討していただきたい。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする