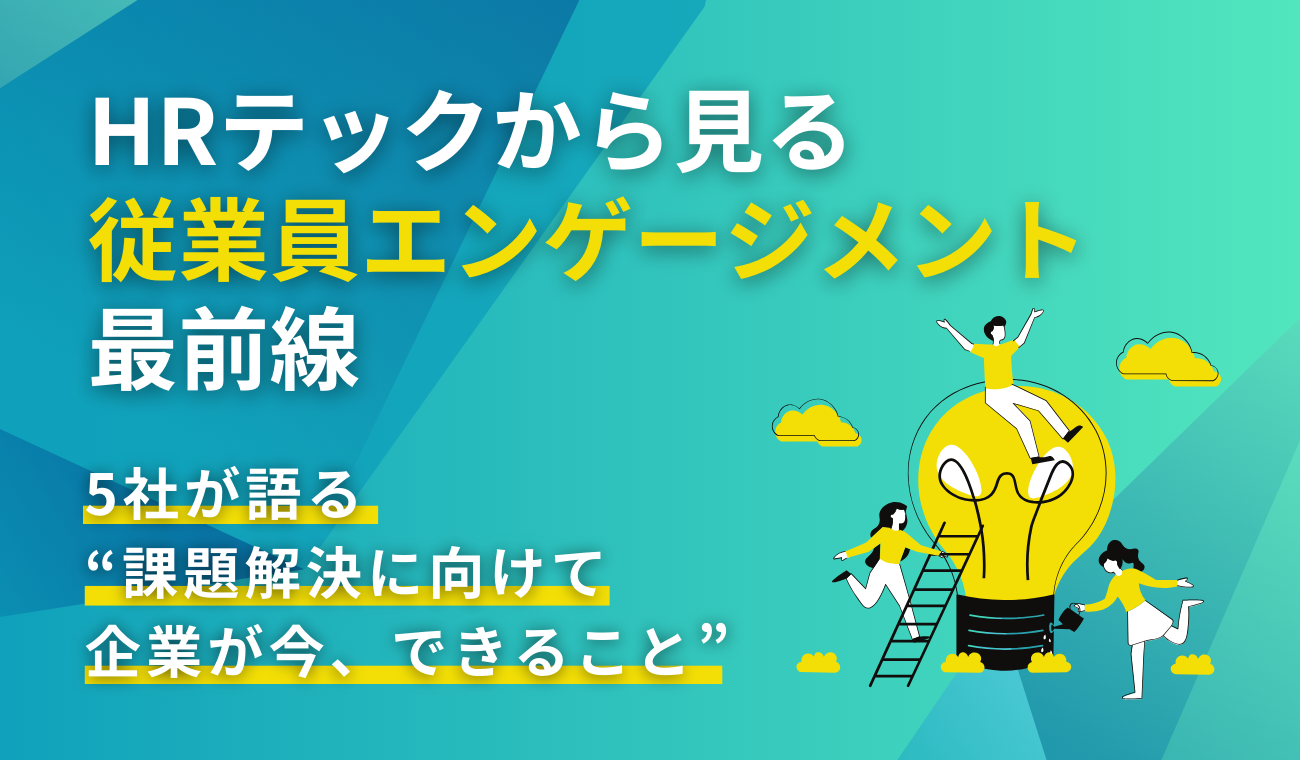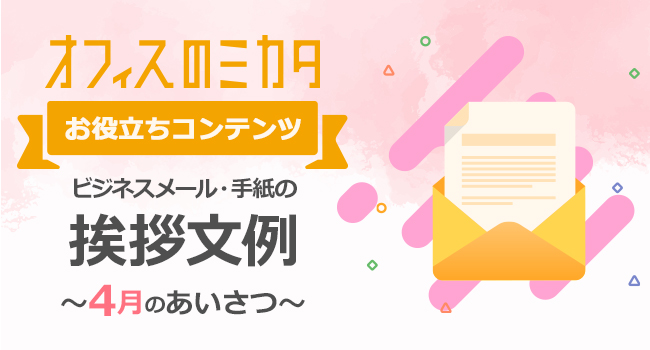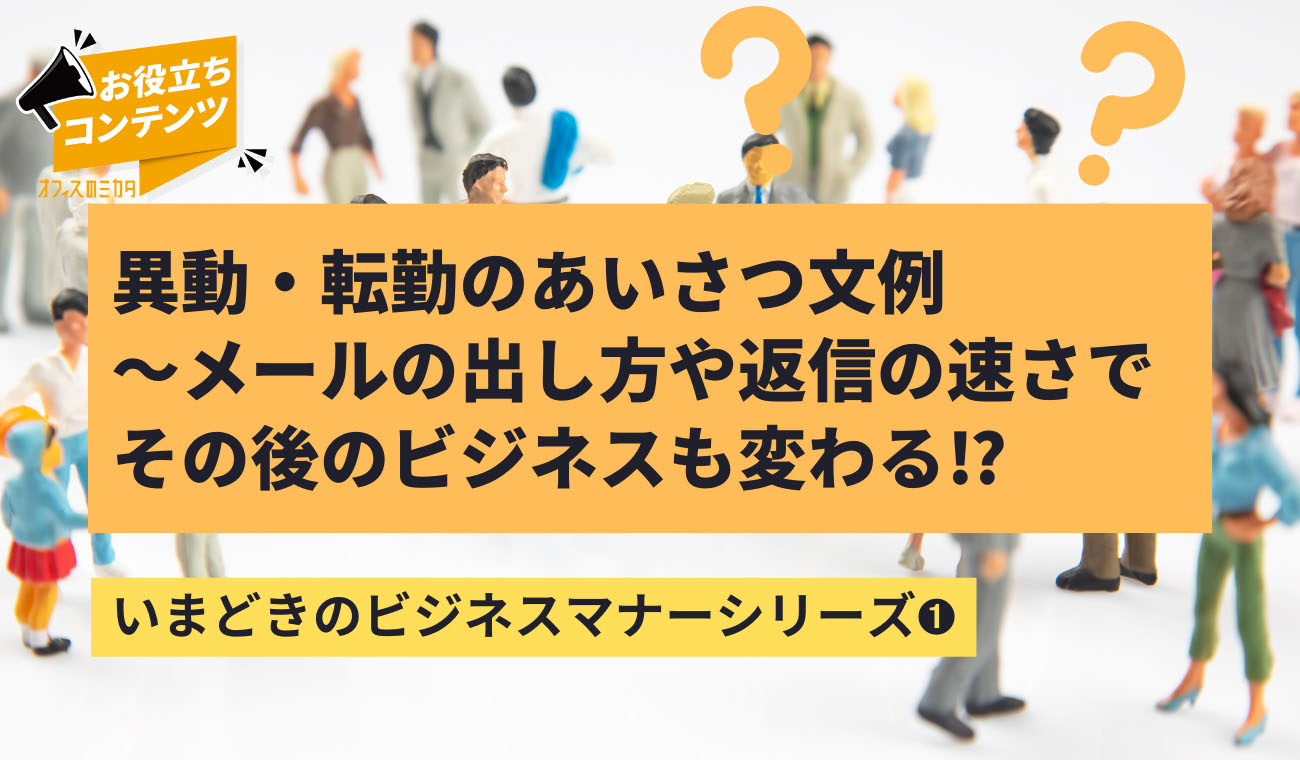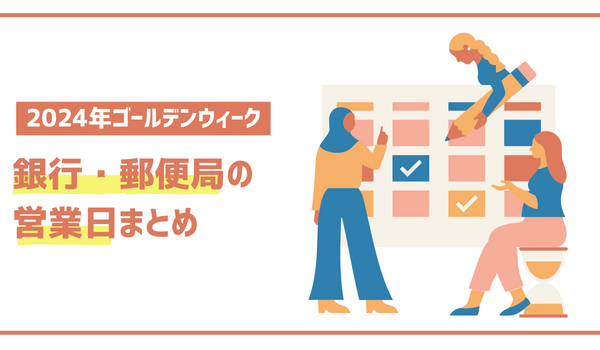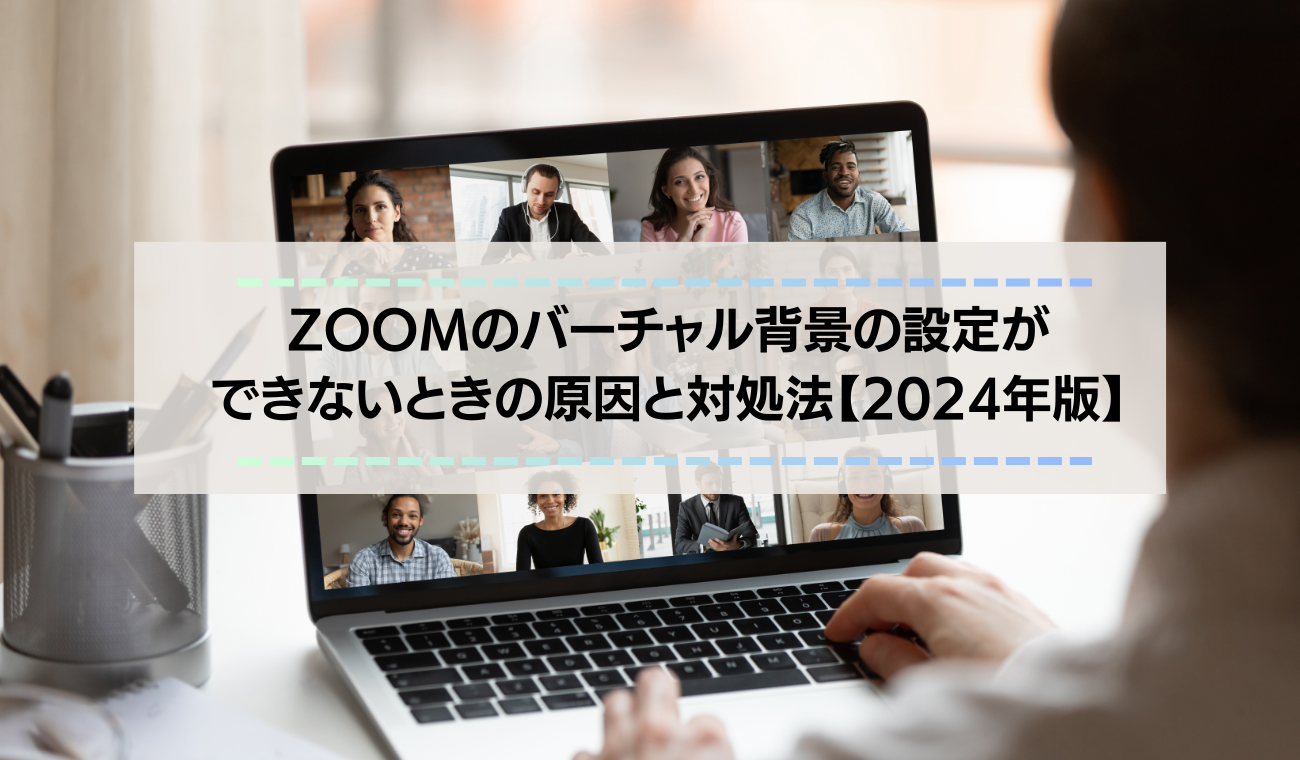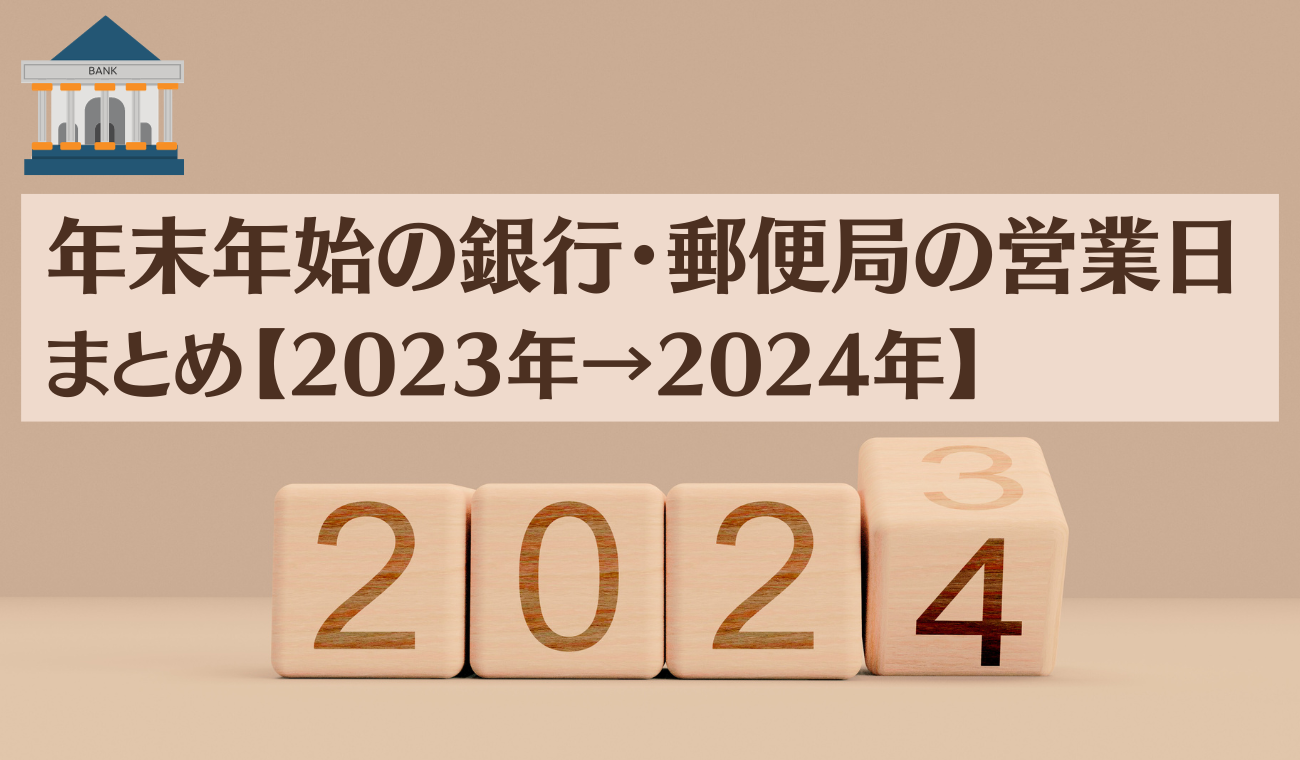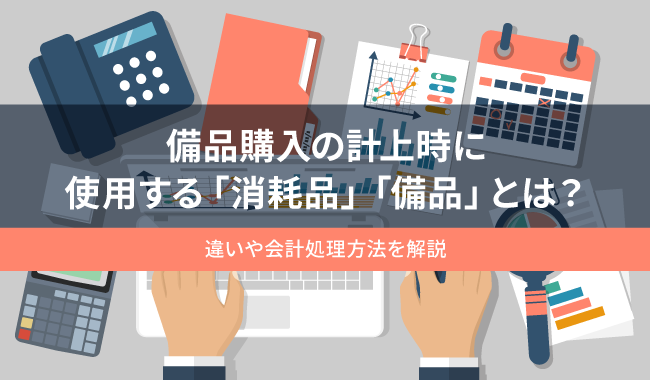給与計算ソフトのおすすめ比較。会社規模・業務フローなど自社に適した選び方も解説
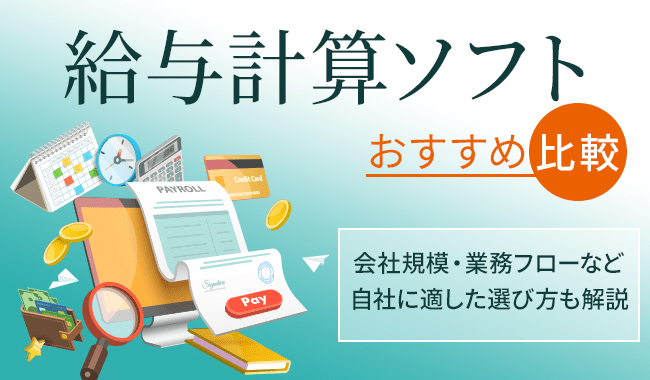
給与計算業務による負担を軽減させるため、給与計算ソフトの導入を検討している企業が多いのではないだろうか。本記事ではおすすめの給与計算ソフトの比較と、会社規模や業務フローなどによる選定ポイントについて解説する。
会計ソフト派生・連携に強みがある王道な給与計算ソフト
まずは会計ソフトを展開している、あるいは連携に強みがある王道な給与計算ソフトを紹介しよう。給与計算だけでなく、HR業務全般の効率化を検討している場合には下記4ブランドをチェックしてほしい。
「 マネーフォワードクラウド給与 」
「マネーフォワードクラウド給与」は給与計算業務全般の処理を自動化できるソフトだ。ペーパーレスやリモートにも対応できるほか、無料アップデートにより社会保険の料率変更なども最新の状態で利用できる。
また、外部サービスや金融機関との連携も可能。さらに「マネーフォワードクラウドHRソリューション」と呼ばれる各種ソフトとの連携によってHR業務全般の効率を改善できるだろう。
【料金】
個人
年額プラン:800円/月
月額プラン:980円/月
従業員30人以下の法人
年額プラン:2,980円/月
月額プラン:3,980円/月
従業員31人以上の法人
要問合せ
サービス詳細はこちら
「 freee人事労務 」
「freee人事労務」は給与計算だけでなく、勤怠や入退社手続きなど労務関係の業務を一元化できるソフト。労務管理に必要な書類を一括で出力できるほかweb上で給与の振込も可能だ。
【料金】
ベーシックプラン
年額:3,980円/月
月額:4,480円/月
サービス詳細はこちら
「 弥生給与22 」
「弥生給与22」はWindows用デスクトップアプリの給与計算ソフトだ。給与計算だけでなく作業手順を確認できる「年末調整ナビ」やヌケ・モレ防止の「ふせん」機能などの便利機能を搭載。マイナンバー管理なども行える。
【料金(「あんしん保守サポート」付き初年度優待価格)】
セルフプラン
88,000円
ベーシックプラン
88,000円
トータルプラン
121,000円
サービス詳細はこちら
「 ジョブカン給与計算 」
「ジョブカン」はシリーズ累計12万社が導入している人気ソフトだ。給与・賞与の自動計算し、役所に提出する必要書類を自動出力してくれる。また、給与計算担当者の業務をサポートする便利機能も複数搭載。ジョブカンシリーズとの連携によって、必要な情報をボタン1つで取得できることが最大の特徴だろう。
【料金】
月額400円(1ユーザー)
サービス詳細はこちら
中堅・中小企業におすすめの給与計算ソフト
続いては中堅・中小企業におすすめの給与計算ソフトを紹介していく。低コストで運用が可能なクラウドタイプを中心に解説していくので、導入費用やトータルコストを抑えたい場合はこちらを参考にしてほしい。
「 給与奉行クラウド 」
「給与奉行クラウド」は給与業務全般の効率化のほかに、各種保険の手続きや年末調整などの業務にも対応している。顧問の社会保険労務士・税理士に提供できる「専門家ライセンス」を1ユーザー分無償で付属しているため、給与奉行クラウドをお互いに利用できるという特徴がある。
【料金】
iEシステム(従業員数20名まで)
60,000円〜/年
iAシステム(従業員数50名まで)
96,000円〜/年
サービス詳細はこちら
「 KINPIRA CLOUD 」
「KINPIRA CLOUD」は給与計算を行えるクラウド型勤怠管理システムだ。交通系ICカード・モバイル・ブラウザによる3パターンの打刻が可能で、有給管理なども合わせて行える。賃金割増率を設定し、雇用形態に応じて条件を登録することで基本給+残業手当の給与計算が可能だ。
【料金】
フリープラン(従業員数30名まで)
0円
スタンダードプラン(1ユーザーあたり)
110円/月
プレミアムプラン(1ユーザーあたり)
220円/月
サービス詳細はこちら
「 GLOVIAきらら人事給与 」
「GLOVIAきらら人事給与」は富士通が提供する人事給与ソフト。給与明細書の入力は実際の給与明細と同じレイアウトのため入力がしやすい。社員やパートなど複数の賃金形態や支給日にも対応しているのも便利なポイント。
【料金】
クラウド版(従業員数50名まで)
12,000円/月
パッケージ版
450,000円~(税別)
サービス詳細はこちら
「 MJSLINK DX 給与大将 」
「MJSLINK DX 給与大将」は給与計算から賞与計算、社保算定及び年末調整までをカバー。人事構成シミュレーションや昇給賞与シミュレーションなどのオプション機能が充実している。その他シリーズと連携させることでERPの構築を行い、基幹業務をシステム化したい場合におすすめだ。
【料金】
要問合わせ
サービス詳細はこちら
大企業におすすめの給与計算ソフト
使用する従業員が増えると通常の給与計算ソフトではなく、情報の一元管理や柔軟な連携システムが重要になってくる。そのためここではERPやパッケージシステムを中心として、大企業におすすめの給与計算ソフトを紹介しよう。
「 EXPLANNER/S 」
「EXPLANNER/S」は人事システムと給与計算システムを統合したパッケージ製品。人事・給与情報を一元管理できるため社員のデータの検索や管理の利便性が上がるというメリットがある。また、セキュリティ面も強く権限設定や操作ログの取得、マイナンバーの暗号化による保存などが可能となっている。
サービス詳細はこちら
「 SmileWorks 」
「SmileWorks」はクラウドERP・統合基幹業務システムだ。給与・賞与から年末調整・社会保険まで給与計算業務をトータルサポートしており、ボタン1つで会計と連動可能。振替伝票などが自動で作成できる。
【基本契約】
初期費用
30,000円
給与ワークス
10,000円/月
サービス詳細はこちら
「 フリーウェイ給与計算 」
「フリーウェイ給与計算」は従業員5人までは永年無料、6人以上では何人でも月額1,980円で利用できるクラウドサービス。保険料率の変更や法改正があってもすぐにアップデートを行うことで対応できる。シンプルなUIで馴染みやすい点も魅力だ。
【料金】
無料版・有料版あり
有料版
初期費用:無料
1,980円/月
サービス詳細はこちら
「 TimePro-NX給与 」
「TimePro-NX給与」は「就業・給与・人事・セキュリティ」を1つにまとめた統合型人事労務パッケージだ。各種データを一元管理できるという強みと、3段階の保守契約プランによる柔軟な保守サービスが魅力である。
【料金】
要問合わせ
サービス詳細はこちら
給与計算ソフトの導入・検討時の選定ポイント
給与計算ソフトを導入・検討する上でどのような点に着目すれば良いのか、ここでは選定ポイントとその理由について解説していく。
導入目的の明確化と対象ソフトのコンセプトのマッチ度
まずは給与計算ソフトを導入する目的と期待する効果を明確にしよう。その上で自社にとって必要な機能やサービスなどを整理ししよう。そして対象ソフトそれぞれの機能を把握しコンセプトを理解した上で、どのソフトが目的と一番マッチしているのかを確認してみると良い。
機能要件の優先順位化と対象ソフトの機能の網羅度
まず自社にとって必要な機能は何なのか、最低限どんな機能が欲しいのかを洗い出して優先順位を設けよう。そして検討している複数のソフトが優先順位を設けた機能を網羅しているかどうか確認すると良いだろう。
既存システムと対象ソフトの連携性
すでに何かしらの関連システムを導入している場合には、新規で導入を検討しているシステムとの連携性を必ずチェックしておく必要がある。新規・既存システムはそれぞれボタン1つで連携できるものもあれば、対応していない可能性もあるので二度手間にならないよう注意が必要だ。
既存業務プロセスと対象ソフトによる業務改善の相性度
既存業務のプロセスを一度確認し、対象ソフトを導入することでどの程度改善ができるのか相性を見極めよう。この時、属人化している箇所はないか、ソフトを導入する必要は本当にあるのか見直す機会にもなるだろう。
ガバナンス要件と対象ソフトのセキュリティの対策度
給与計算業務においては、従業員の個人情報を取り扱うことになるため漏えいリスクを考慮しガバナンス要件を定義しておく必要がある。特にセキュリティ要件についてはソフトによって差があるので、自社の要件を満たしているか必ず把握しておこう。
給与計算の業務効率化・コストダウンのための最適な手法はどれ?
給与計算ソフト以外にも給与計算の業務効率化を行う手法があるため、自社にとってどのソフトやサービスを利用することでより業務効率化・コストダウンを図れるかを見極める必要がある。ここではそれぞれの活用メリットについて解説していく。
クラウド給与計算ソフト(Web型)の活用メリット
クラウド型の給与計算ソフトでは、給与計算業務を自動化することでデータの正確性の向上・業務の効率化が図れる。また、法改正などによって税率や書式の変更が起きた場合でもアップデートで最新の環境へと対応してくれる。ソフトによってはほとんど専門知識がなくても取り扱えるようなUI設計がなされているため、担当者が変更になっても対応が可能で属人化を排除できるというメリットも挙げられる。データをクラウド上に保存し常にバックアップを取れるという点とデータの共有がリアルタイムで行える点はクラウドならではの強みと言える。
パッケージ給与計算ソフト(インストール型)の活用メリット
パッケージの場合のメリットは、クラウド型で挙げた自動化による業務効率化及びデータの正確性の向上、属人性の排除だ。上記以外のメリットを強いて挙げる場合、PCに直接インストールするためインターネット環境が無い場合でも作業が行えるという点になるだろう。また、買い切り型でランニングコストがかからないため、継続利用をすることでクラウド型よりもコストを抑えやすい傾向にある。
Excelなどの表計算ソフトを用いた給与計算を行なうメリット
Excelなどの表計算ソフトは初期からインストールされていることが多いため、費用をかけずに給与計算を行いたい場合に利用されることが多い。また、従業員が少ない場合に気軽にトライできることも魅力だろう。
社労士や会計アウトソーシングサービスの活用メリット
社労士などにアウトソーシングで依頼する場合には、専門知識がある人物が作業を行うため法律などの観点によるリスクが保証されることになる。また、完全に外部へと切り出すため従業員のリソース確保も行える。
まとめ
給与計算ソフトは種類が数多くあるため、自社にとって最適な製品を選ぶことが重要になってくる。中でもクラウド型は初期導入費用が抑えられる他に、短期間での実施がしやすいという特徴がある。無料デモ期間が設けられているサービスも多いため、まずは問い合わせを行い実際に試してみることをおすすめしたい。
<PR>


 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする