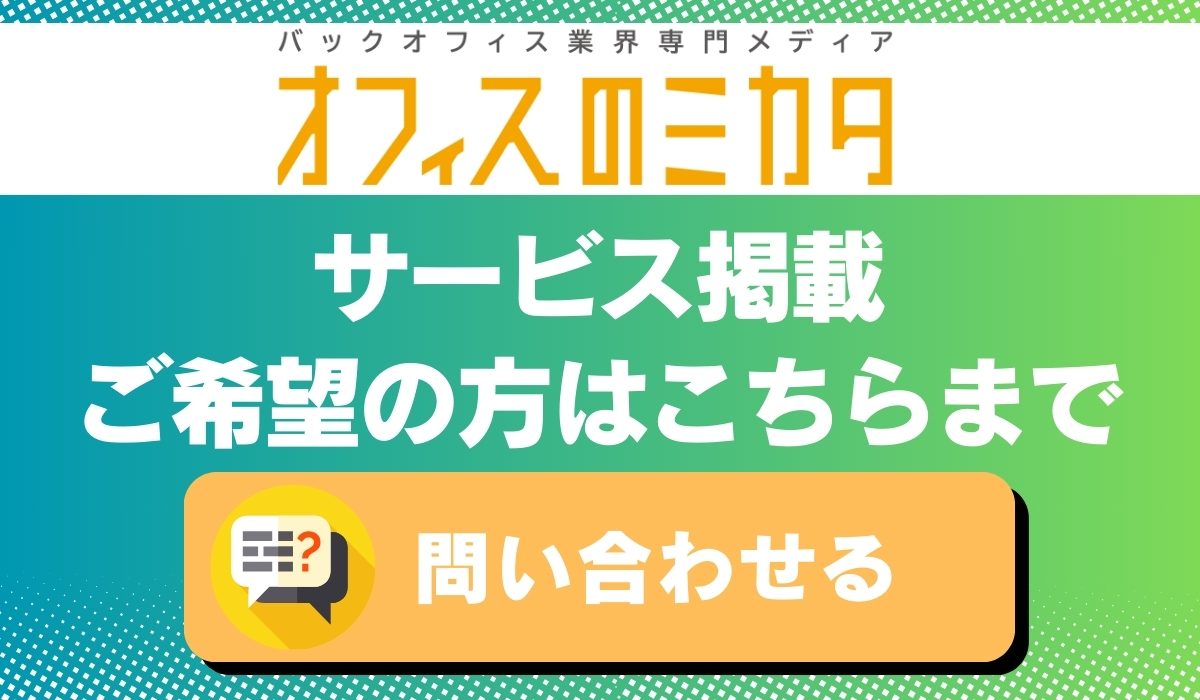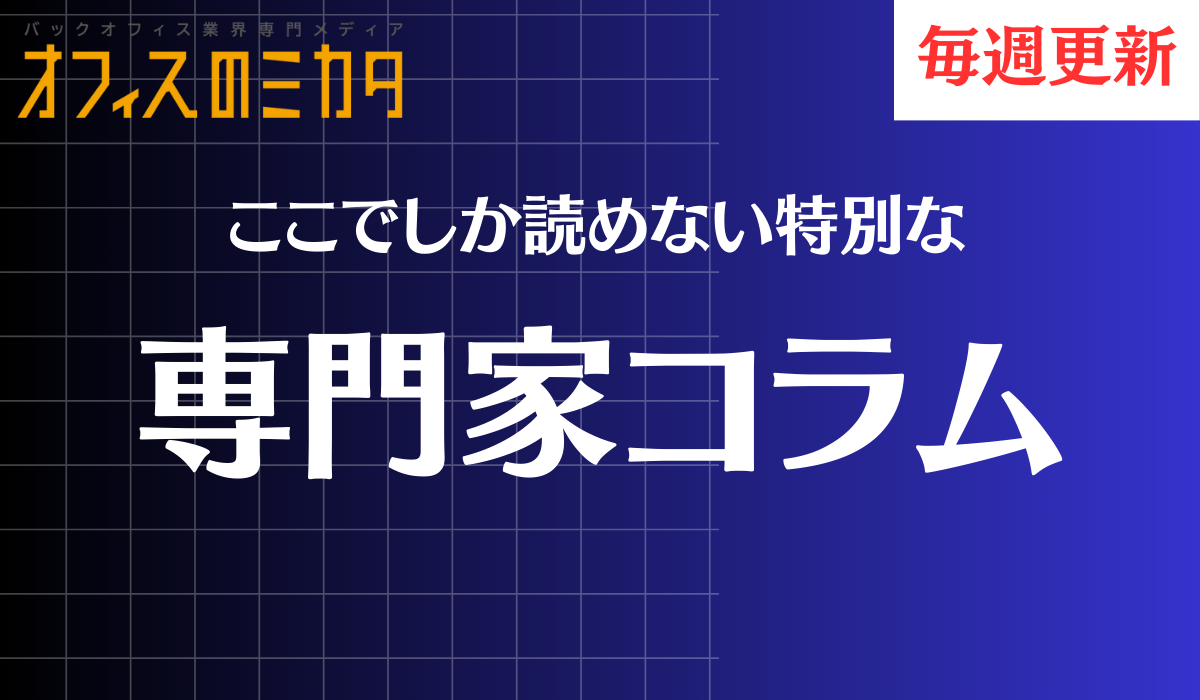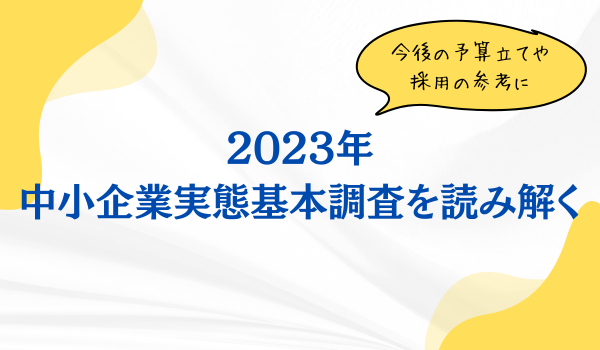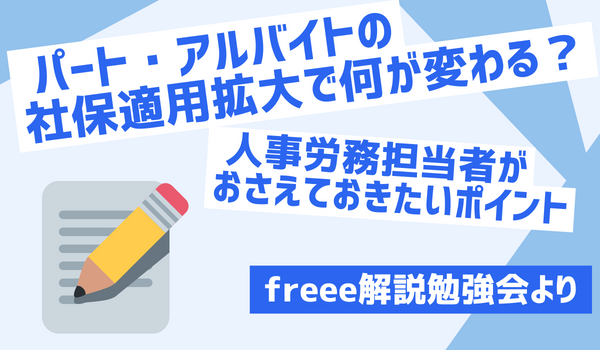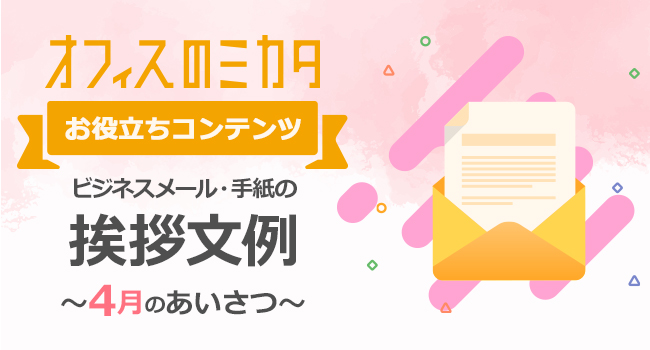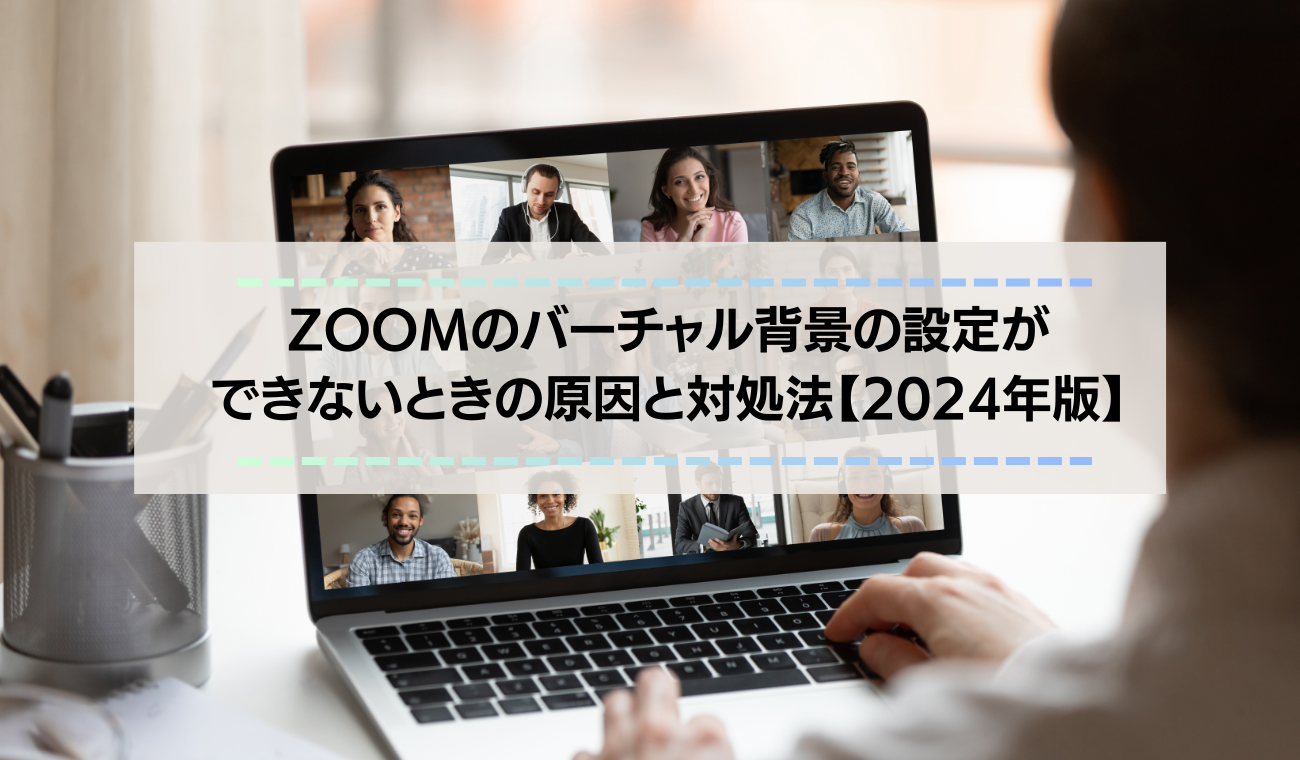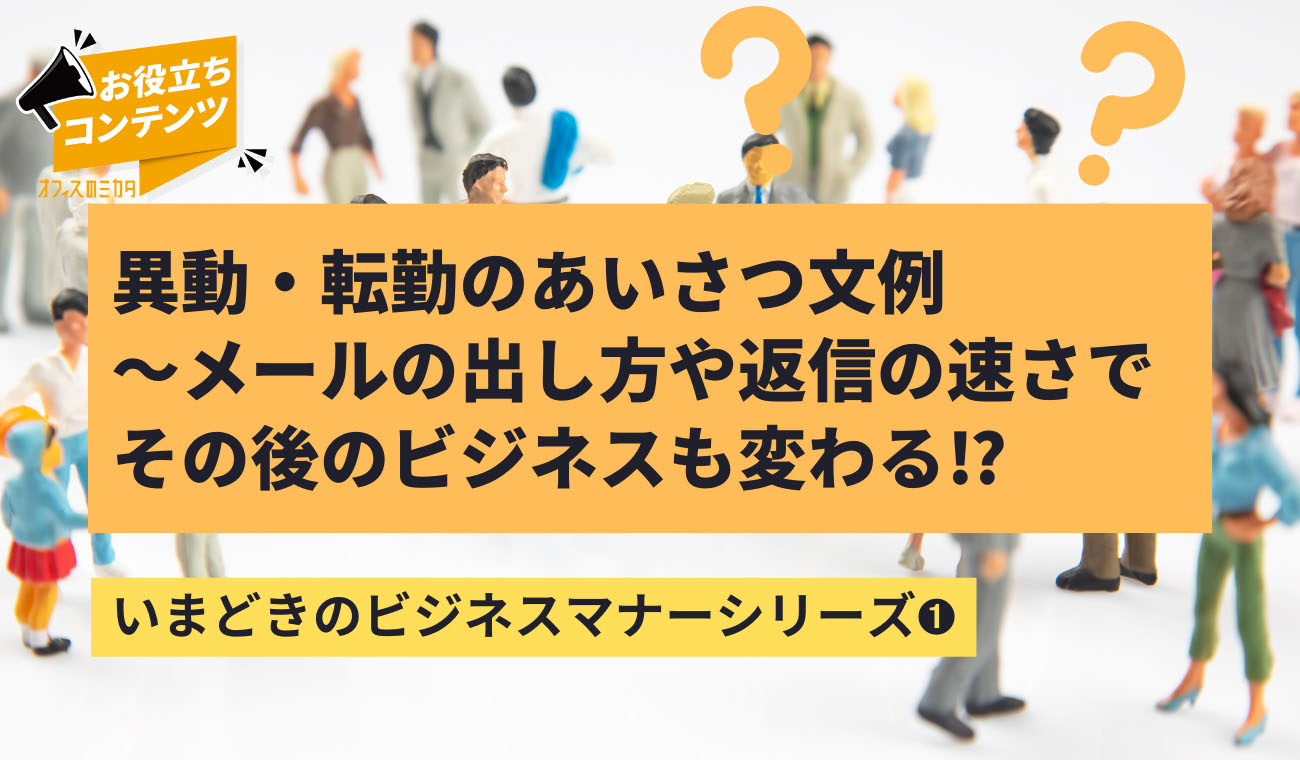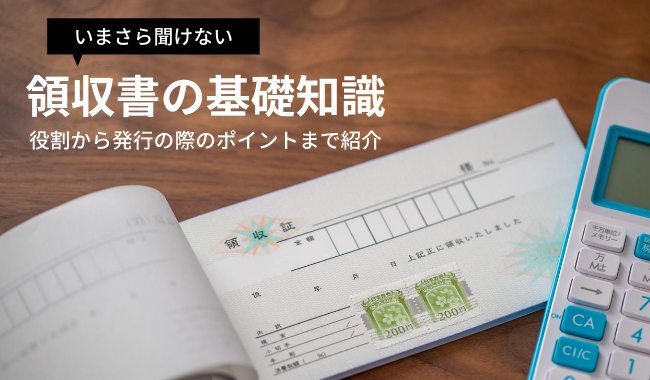電子契約システムの選び方とクラウドサービス6社を厳選して紹介!【DL資料付】

電子契約システムを選ぶ上では、導入によって得られる効果や解消する課題を意識するとともに、システムの機能や料金体系などもよく検討することが重要だ。この記事では、電子契約システムの選び方で特に押さえておきたい6つのポイントと、数ある電子契約システムの中から厳選して6つのサービスを紹介する。自社に最適な電子契約システム導入の参考にしてほしい。
目次
●電子契約システムとは?
●電子契約サービスの選び方のポイント6つ
●厳選して紹介!電子契約サービスおすすめ6選
●まとめ
電子契約システムとは?
電子契約システムとは、インターネット上で契約の締結を行えるシステムのこと。紙の契約書で用いられてきた署名押印に代わり、PDFなどの電子文書ファイルを利用する。「電子署名」や「タイムスタンプ」機能を活用することで、なりすましや改ざんといった不正を防止しながら、契約業務の効率化を図ることが可能だ。電子契約システムは、官公庁の公的機関をはじめとしてあらゆる業界で導入が進んでいる。
電子契約システムのしくみや導入のメリットなどは、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてほしい。
関連記事:『時代はデジタルへ!電子契約の仕組みからメリットまで徹底解説』
電子契約システムの選び方のポイント6つ
多くの企業が導入している電子契約システムは、市場の拡大が見込まれる分野であるため、サービスを提供するベンダーも多い。ここでは、多数のサービスから自社に合ったものを選択するための選び方を、6つ紹介する。
<選び方1>必要なコストと得られる効果
電子契約を利用するメリットの一つに印紙税が不要になるという点がある。交わす契約書が多く、その金額が大きい企業では、かなりの経費節減効果が見込まれるだろう。また、紙の契約書のやり取りで発生する郵送代や作業代も削減できる。
しかし、電子契約システムでは「月額基本料金」に加えて、契約締結1件につき100円~200円の従量課金を採用しているサービスが多い。従量課金の場合、締結する契約書数が多いほど、毎月の請求額も増えるため、注意が必要だ。無料プランを利用できるサービスであっても、利用上限などが設定されている場合もあるため、自社の年間契約数なども踏まえながら費用対効果を検証しよう。
<選び方2>タイムスタンプ・電子署名は必須
法的な効力や信頼性を担保できるかも重要な視点となる。契約書の法的効力で最も重視されるポイントは以下の3点だ。
・契約締結の時期(契約はいつから有効か)
・契約者の情報(本人性)
・契約書の正確性
契約書の信頼性担保のために、電子契約システムには「タイムスタンプ」「電子署名」「電子証明書」の3つの機能があるのが一般的だ。このうち、「タイムスタンプ」は契約締結日時と非改ざん性の証明に有効であり、「電子署名」は契約相手本人によって締結されたことと、契約書の非改ざん性の証明に欠かせない。そのため、電子契約システムの選定では、特にタイムスタンプ機能と電子署名機能が標準的に利用できるかは確認しよう。
<選び方3>セキュリティ機能(安全性の担保
契約書の情報漏えいや改ざんを防ぐためには、安全性の確保も欠かせない。そのため、セキュリティ面の充実度合いも比較したいポイントといえる。
ただし、本人認証のような高度なセキュリティ機能は多大なコストがかかり、契約相手に導入費用が発生するケースもある。また、ログインに時間がかかるなど作業効率を低下させてしまうことも考えられる。自社に合ったセキュリティ機能の選択が重要だろう。
<選び方4>利用用途との適合性
自社の利用目的に合ったサービスとなっているかも確認したい。たとえば、社内稟議や承認のワークフローが複雑で時間がかかっているという場合では、ワークフロー機能のあるシステムを選定すれば、業務効率化が望める。
また、締結する契約書の種類が多い場合は、ひな型が充実していると便利だ。さらに、営業システムや会計システムなど、契約前後の関連業務との連携機能を備えていれば、データの反映が簡単に行える。
<選び方5>サービスのターゲット層
電子契約システムは、「幅広い規模の企業の利用を想定して作られたもの」と「特定のターゲットに向けて作られたもの」に分けられる。
電子契約システムは、本人確認の方法により「立会人型」と「当事者型」に分類できる。「立会人型」は、利用者の指示に基づいて、システムの事業者が電子署名を付与するもので、主に中小企業向けと言われている。立会人型には、サービス利用者が電子証明書を取得する必要がない、相手方(受け取り側)がアカウントを保有していなくても利用可能といったメリットがあるが、当事者型に比べて、本人確認性には劣る。
一方「当事者型」は、電子認証局による本人確認後発行される「電子証明書」を利用して、契約当事者が自ら電子署名を付するもので、主に大企業向けと言われている。
システムによって想定顧客層は異なり、料金や機能も多様だ。想定の顧客層に自社が合致するサービスを選ぶことで、「機能面」「効率化効果」「コスト面」のいずれにおいても、より効果を得られやすいだろう。
<選び方6>サービス提供会社の持続可能性
電子契約システムは、サービスを展開するベンダーに契約書データの管理を委ねる。そのため、運営会社の信頼性や将来性を検討することも重要な比較ポイントといえる。サービスの知名度や導入企業数、口コミなどから自社の機密情報を委ねるに足りるかをきちんと検証しよう。
厳選して紹介!電子契約システムおすすめ6社
ここからは、電子契約システムのおすすめ6社を、厳選して紹介する。
クラウドサイン|弁護士ドットコム株式会社
弁護士ドットコム株式会社が提供しているクラウドサインは、導入者数・実績数とも国内屈指を誇る電子契約サービスだ。紙と印鑑を使った従来の契約業務を、PDFのアップロードとメールでの通知という方法に変換させることで、1週間ほど必要だった契約までの作業時間を、早ければ数分で完了できる。契約書一通あたりのコストは300円と、人件費や郵送・収入印紙代に掛かっていたコストを大幅に削減することも可能だろう。月額固定費用は10,000円~利用できる。
公式HP:『 クラウドサイン』
関連記事:『クラウドサインとは?メリット・デメリットから適法性までをわかりやすく解説』
電子印鑑GMOサイン|GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
電子印鑑GMOサインは、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が運営するクラウド型の電子契約サービスだ。契約印タイプ(立会人型)の送信料は、1件あたり110円と格安で利用できる。電子帳簿保存法に準拠しており、権限設定や閲覧制限機能で、大事な⽂書を管理することが可能だ。また、月間5件までなら無料で試せるフリープランもあるため、導入を迷っている企業も試しやすいだろう。
公式HP:『電子印鑑GMOサイン』
BtoBプラットフォーム契約書|株式会社インフォマート
株式会社インフォマートが運営している電子契約サービスが、BtoBプラットフォーム契約書だ。タイムスタンプ、電子著名が付与され、自社の会社を含めた最大5社間契約まで実施可能で、過去に"紙"でやり取りしていた文書もクラウドで管理・共有ができる。電子帳簿保存法の保存要件を満たし、税務調査対策も可能だ。契約締結が5件までなら月額使用料0円で試せるフリープランを採用しているため、契約数が少ない企業には特に導入しやすいサービスだ。
公式HP:『BtoBプラットフォーム契約書』
CONTACTHUB|日鉄ソリューションズ株式会社
CONTACTHUBは、日鉄ソリューションズ株式会社が提供している電子契約システム。2013年にサービスを開始した、業界のパイオニア的存在だ。金融や製造、小売など多様な業界の大企業を中心に導入されており、2022年5月現在で50万を超えるユーザーが利用している。電子契約を取り巻く環境変化に対応し、継続的なバージョンアップを実施。また、定期的なユーザー会・勉強会の開催などを通し、顧客ニーズを継続的にサービスに反映する取り組みを実施している。
公式HP:『電子契約サービスCONTRACTHUB』
paperlogic電子契約|ペーパーロジック株式会社
ペーパーロジック株式会社が展開しているpaperlogic電子契約は、文書に応じて「立会人型」と「当事者型」の署名を使い分けることができる、電子契約サービスだ。電子契約のほかにも、電子稟議、電子書庫にも対応しているため、ワークフローの複雑さや文書管理に課題を持つ企業にもおすすめしたい。請求書や納品書なども全て電子化できるため、事務作業の効率化につながるだろう。フラットな固定料金制(20,000円/単一プラン)を採用しているため、契約数の多い企業ほど、一件あたりのコスト削減につながる。
【無料】資料DLはこちら:『paperlogic電子契約 - オフィスのミカタ』
かんたん電子契約forクラウド|セイコーソリューションズ株式会社
かんたん電子契約forクラウドは、セイコーソリューションズ株式会社が提供する、電子契約と電子帳簿保存法に対応した書類の保管ができるクラウドツールだ。電子契約はじめ、捺印業務の電子化、文書保管などの電子化用途でも利用できる。
最大30名に対応した三者間契約や立会い型署名のほか、契約ステータス確認やアカウント管理機能、契約書のひな形登録など多数の機能を搭載しており、契約業務の効率化を実現できるだろう。電子帳簿保存法に対応した電子契約を1カ月間月額使用料無料(別途送信料100円/件・アップロード代20円/件他)で試せるほか、月額10,000円~で利用できる。
【無料】資料DLはこちら:『かんたん電子契約forクラウド - オフィスのミカタ』
まとめ
電子契約システムは、今回紹介した「コスト対効果」「セキュリティ機能」「サービスのターゲット層」などの選び方を踏まえて選定することがポイントだ。自社の月間契約数や、契約にかかっている総コストをあらかじめ計算しておくと、サービスを選定しやすいだろう。無料で試せるプランを採用しているサービスも上手に活用しながら、自社に合ったサービスをみつけよう。

 ツイート
ツイート

 シェアする
シェアする